

[JavaOne2000 レポート]
written by
株式会社 オージス総研
オブジェクト技術ソリューション部
小浜 宗隆
6月6日から9日までの4日間、サンフランシスコ モスコーン・センターにて、Java開発者会議「JavaOne」が開催されました。今回、それに出席する機会に恵まれましたので、その模様についてレポートします。

モスコーン・センター前
JavaOneも、今年で5周年を迎えました。そのせいもあってか、全体的に、どことなく「お祭りムード」が漂っていました。基調講演などでも、踊りはあるは、コントはあるは、大物ゲストはばんばん登場するはと、そういった雰囲気を盛り上げていました。ただ、内容的には、例年のような新技術の発表などはなく、現在のJavaの成果、特に普及ぶりを示すことが中心であったように思います。それでは、基調講演、セッション、展示会場などの様子を簡単に紹介します。
開催期間中の4日間とも基調講演は行われたのですが、Javaの現状を如実に表すものとして、特に初日の内容が興味深かったので、それを中心に書くことにします。
初日の基調講演は、Sun Microsystems社CEOであるScott McNealy氏。
名物スピーカーとして高名な彼らしく、いきなりMicroSoftをネタにしたジョークを連発し、会場の爆笑を誘っていました。
さて、内容の方はというと、Javaの勝利宣言およびさらなる宣伝とでも言ったところでしょうか。まず、Java2 SDKのダウンロード数が300万件に達していること、開発者数も250万人を超えていることなどを挙げ、Javaが広く受け入れられていることについて言及しました。また、Javaの成功要因を、セキュリティとネットワーク親和性にあったと分析し、さらに、それらの特性をキーとして、「Javaをありとあらゆる機器の開発・実行のためのプラットフォームとし、各機器が共通の言語を話す基盤を作る。それにより大きなメリットが得られることになるであろう」というビジョンについて語りました。
特に印象的であったのは、そういったビジョンの達成およびその過程で、ビジネスチャンスが無数に転がっていることを強調し(表現としては、もっと直接的で「大金を手に出来る」でした。)、開発者を煽っていた点です。Sunにとっての、Javaの課題は、既にビジネスへの展開に移っているのでしょう。
その後は、上述したビジョンに対する賛同者を多数壇上に招き、各社がJavaに本気で取り組んでいる様子、さらに、最新の成果として、多数の機器でJavaが動作する様をデモして見せ、Javaの普及ぶりをアピールしました。特にデモの内容は、Javaの対象がPCより、ポストPCを担う携帯端末やゲーム機などの組み込み機器へ移りつつあることを明瞭に感じさせるものでした。
その時のトピックスを挙げてみますと、以下のようになります。
■次期MacOSに、J2SEを搭載
なんと、Apple Computer社CEOのSteve Jobs氏が登場。
次期MacOS(MacOS X)には、J2SE v1.3が標準搭載されることを発表。そのJ2SEでは、次期Mac OS用のAquaルック&フィールもサポートされるとのこと。
■DreamCastに、Personal Java搭載
セガ・エンタープライズ社副社長の入交昭一郎氏が登場。
ゲーム機DreamCastにPersonalJava環境とWebブラウザを搭載し、インターネット対応にすることを発表。さらに、Motorola社と提携し、携帯電話向けのゲームコンテンツやゲーム用APIの開発を行っていくことも発表。■様々な機器でJavaが動作
この日、デモで紹介されていたJava対応の製品としては、他に以下のものがありました。
- Sonyのビデオカメラ
- MotorolaやNTT Docomoの携帯電話
- Research in Motion社のBlackberryという双方向ページャ
- Golfクラブ(実際にスイングすると、その動作がゲームに取り込まれる、バーチャルもの)
なお、2日目以降の基調講演で、印象に残っているのは、リアルタイムJavaについての話題でしょうか。その日の基調講演には、Sun MicroSystems社の副社長(というより、Java言語の開発者と言った方がいいでしょうか) James Gosling氏が登場しました。
彼は、最近の仕事がリアルタイムJavaの仕様をまとめることであったと語り、その成果として、出版されたばかりの「The Real-Time Specification for Java」を紹介していました。また、リアルタイム仕様のインプリメンテーションのデモとして、リアルタイム制御で、2本のアームが箸を使って、キーボードを演奏するという自動演奏ロボットを見せていました。
開催期間中に開かれたセッションの数は、約150。さらに、BOFと呼ばれる小セッションも加えると、優に250を超えていたでしょう。また、セッションの内容も、実に多彩。一応、J2SE、J2EE、J2ME、Java+XML、Developmentなどのカテゴリに区分されてはいたのですが、1つのカテゴリの中でも、様々なレベルのトピックスを扱っていました。例えば、J2ME関連のセッションでも、概要を紹介するものから「Inside KVM」といった実装を解説するディープなもの、また開発事例を扱うものまでと、非常にバラエティに富んでいました。
同一時間枠に約10程度のセッションが組まれていたので、聞きたいものが重なると、はしごせざるを得ない状況だったのですが、ころころ変わるスケジュール、巨大な会場などで、慣れるまではかなり右往左往させられるはめになりました。
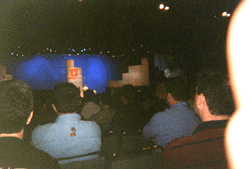
会場内の様子
さて、内容の方ですが、何せ参加人数が人数なので(話によると、今年のJavaOne参加者は25000人を超えていたそうです)、どのセッションも満杯でしたが、やはり時代を反映してか、J2ME関連のセッション、特に携帯機器を扱ったものが人気を集めていたように思います。
ただ、個人的には、開発手法やパターンなどのJavaによる開発を扱ったセッションの盛況ぶりが、印象に残りました。例えば、日本でもお馴染み(?)のMartin Fowler氏がリファクタリングのセッションを行っていたのですが、入場制限が出るほどの人気を博していました。
さらに、そういったセッションの参加者の有識度にも驚かされました。同セッションにおいて、XP(eXtream Programming)について知っている人、実際に使ったことのある人に手を挙げさせていたのですが、約半数くらいの人間が挙手していました。
日本では、まだ馴染みの薄い開発手法が既に導入されている事実を目の当たりにすると、JavaOneが「開発者」会議であることを意識させられるとともに、開発者の関心がJavaで何ができるかというところから、Javaで如何に開発すべきかというソリューションに向けられているのを強く感じました。
後、付け加えておくべきこととして、UMLの浸透振りがあげられると思います。上記のような開発手法に関連したセッションだけでなく、開発事例を扱ったセッションの多くで、UMLのモデルを使った説明が行われているのを目にしました。そのようにUMLがごく当たり前のものとして使われている事実。UMLの要素技術としての性格を考えれば、その事実こそが(特に米国での)浸透ぶりを表していると思います。
出展社数は、約300と発表になってましたが、なぜかそれほど多い感じはしませんでした。
展示会場の周りのほとんどをSun Microsystems社のブースに固められていたせいもあるかも知れません。
さて、各ブースでは、様々な分野のJava対応製品、それもまだコンセプトレベルのものから、既に実用レベルに入っているものまで、多数出品されていました。勿論、サーバサイドのJava製品、例えばアプリケーションサーバなども出品されてはいたのですが、やはり、ここでも組み込み機器が目を引きました。
特に目に止まった製品について、紹介します。
■携帯機器
J2MEに対応した携帯機器は、今年のJavaOneを象徴する存在であったと言っていいでしょう。
Motorola社のブースでは、基調講演でも紹介された、セガのゲームが動作する携帯電話が展示されていました。また、Webにもアクセス可能な、腕時計型の携帯電話も展示されていました。
他には、同じく基調講演で登場した、Research in Motion社のBlackberry、NTT Docomoの携帯電話などを見かけました。
■自動車
Ford社やBMW社がJ2MEに対応した自動車を展示していていました。
どちらも、インターネットに接続可能で、電子メール、リアルタイムなトラフィック監視、MP3レコーダーなどの機能を提供する他、種々の携帯機器との連携が可能であるということでした。
BMW社の方は多機能なカーナビがついている車という感じでしたが、Ford社の方は、ダッシュボード全体がスクリーンになっているコンセプトカーでした。
■家電製品
やはり、セガ・エンタープライズ社のゲーム機DreamCastが一番の目玉だったようで、多数の人がネットワーク対応型ゲームに興じていました。
ただ、それ以外には、期待していたような、インテリジェントな家電製品(Jiniに対応した炊飯器やら電子レンジなど)などを見かけることはできませんでした。
■産業機器
Cyboronix社のブースで、流れてくるジェリービーンの色を識別し、所定の位置に配信する制御機器のデモが行われていました。オーダをWeb経由で出したり、リアルタイムに監視したりするための機能も提供されているとのことでした。
FA系のJava対応機器としては唯一の出品であったと思います。
■クレジットカード
AmericanExpress社のブースで、「Blue」というJavaCard仕様に対応したスマートカードが出品されていました。
なお、私は見逃したのですが、基調講演中に、そのカード用のアプリケーション開発コンテスト(CodeBlueと呼ぶらしいですが)が開かれることが発表になっていたようです。最優秀者は、賞金5万ドルとのこと。
今回のJavaOneは、Javaに対する焦点がテクノロジー面からビジネス面へと移行しつつある、そんな過渡期での開催であったと思います。
まず、Javaのテクノロジーは、成熟の域に達しつつあると感じています。(そういう気分にさせられるのは、今年は、特に新しい発表がなかったことも無関係ではないと思いますが。)
勿論、解決されるべき問題点(経験から言えば、異なるバージョンの互換性、異なるOS上での一貫したルック&フィールなど)は残っていますが、基本機能はほぼ整備されてきており、より高い完成度を求める段階に入ってきているのではないかと思います。
また、今年のJavaOneでは、Javaのテクノロジーが、様々な分野・業種で着実に浸透しつつある様を見ることができました。特に、今回、ポストPCを担う携帯電話などの組み込み機器への普及ぶりは目を見張らされるものがありました。また、Javaは、その優位点(移植性、安全性、開発の容易さなど) により、今後さらに市場を拡大する可能性も秘めていると考えられます。
要は、Javaのテクノロジーは、「使える」段階に来ており、それに興味を持つ業種・分野が広く存在する状況になってきているといえます。
今後は、Javaのビジネスへの展開、つまり、「使える」テクノロジーをもとに、どのようなサービスやコンテンツを提供できるのかが、積極的に議論されるようになるでしょう。
そのような時代に、開発者に課せられるのは、高品質なサービスやコンテンツの開発を可能とするソリューションの提供です。言うまでもなく、それを支えるのは、ソフトウェアパラダイムとしてのオブジェクト指向ということになるでしょう。Javaはオブジェクト指向言語であり、その言語のパワーを引き出すには、その知識は不可欠なものです。
繰り返しになりますが、今年のJavaOneは、Javaに対して興味を抱いている業種・分野が拡大していることを感じさせるものでした。そのことは、これまでオブジェクト指向が、それほど浸透していない(と考えられる)業種・分野に対しても、その重要性がアピールされるべき時代になってきたことも意味しているのではないかと考えています。
■怠惰ゆえに・・・
実は、初日の基調講演は2人でした。その2人目として、Sun MicrosystemsのPat Sueltz氏が登場したんですが、彼女のハイテンショントークは、時差ぼけの体にきつく、途中で退席してしまいました。
そのおかげで、AmericanExpress社のCodeBlueコンテストの宣伝に来ていたMagic Johnsonを見逃すはめになってしまいました・・・ま、Javaとは関係ないし、いいですけど。
■食事
JavaOneは昼食つきでした。大体、チキン2つに、パン、サラダ取り放題といった感じの食事でしたが、2日目にはあまりの人出のせいか、途中で「No Food!」という状況に出くわしてしまいました。
でも、特に謝られたりもしませんでした。おいおい。
■おまけ
今年のJavaOneのおまけは、JavaCardでした。
会場の一角に、参加者が使用できるように、ワークステーションがずらっと並べてあったんですが、それを使うと、ログイン(といっても、認証機能はなし)できるという代物でした。それ以外の使い方がよくわからなかったので、あまり文句を言える筋合いではないんですが、これって、昔のJavaRingより、ちゃっちいんじゃ…
後は、Tシャツが2枚ついてきました。1枚は黒の長袖、もう1枚は白の半袖です。胸にはJavaOneのマーク、裏面には、ずらっとスポンサーの名前が載った貴重(?)ものです。
これを各1名の方にプレゼントいたします。(勿論、未使用なので、ご安心を)
応募要領については、下記を参照してください。
|
■サイン James Gosling氏がサイン会をやっているところに遭遇。ありがたくサインを頂戴してきました。 ということで、こちらの方も、以下のサイン本を2名の方にプレゼントいたします。 (本当は、「The Real-Time Specification for Java」が良かったのでしょうが、売れきれてたので…) 「The Java Language Specification, Second Edition」 「The Java Programming Language, Third Edition」 どしどし、ご応募ください。 |
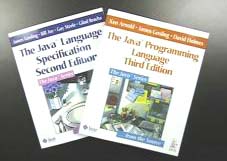
|
 |
 |
| James Gosling氏 サイン会 | James Gosling氏のサイン入り本 |
|
| © 2000 OGIS-RI Co., Ltd. |
|