
[ObjectDay2002特集]
小島@福井コンピュータ
2002/08/19
2002/06/25 〜 07/24
ストリーミング配信を利用したインターネット上での開催
昨年も OBJECT DAY に参加した (*1) のであるが,この時は福井から品川まで JR で四時間半.前日から品川に泊り込んでの参加であった.
それが,今年はなんと「ストリーミング配信を利用したインターネット上での開催」である.
私は福井県の会社 (*2) に勤務しているが,福井に居ながら参加出来る訳である.
ざっと計算してみたところ,四〜五万円の節約になる.
長引く不況で昨年より更なる経費削減が必要な昨今 (当社比),これはありがたいかも知れない.
また,沢山の (数十の) セッションが有るが,今回は参加したいもの全てに好きな順に参加することが出来ることにもなる.
# 唯,多くの熱心な技術者の熱気を感じる楽しみは減るかも知れない.
#
# こうした新しい技術を扱う会では,気合が入っている参加者が多い.
# 東京まで足を運ぶことで,日頃書籍やメール等でしか知らなかったりするそうした
# 「鼻息の荒い」人達と直にお話させてもらったり,或るいは,飲み会に参加して
# 「UML」だの「XP」だのの濃い話を酒の肴に二時間以上飲んだりするのは,
# なんとも「非日常的」で嬉しいのである.
(*1) 昨年の『ObjectDay2001』参加レポート
(*2) 全くの余談だが,今回講師の平鍋 さん も福井の会社にお勤めである.たまに関東の人で福井県の場所を良く把握していない人が居る.「京都の隣」と教えてあげると,「えー京都の隣にそんなの無いよ」とか言われたりする.「そんなの」ってこたないだろう (悲).
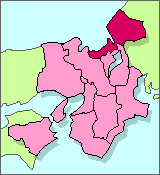
早速,手始めに特に面白そうなセッション「モデリング座談会 --- UML の現状と今後」 を視聴してみることにした.
講師は (株) 永和システムマネジメント 平鍋 健児 氏,(株) テクノロジックアート 長瀬 嘉秀 氏,(株) エクサ 児玉公信 氏,(株) オージス総研 藤井 拓 氏 (司会) の各氏である (順不同).
# ちなみに,昨年はパネルディスカッション『XP談義 -その有効性を問う-』というのが
# 有り,八人のパネリストが XP 擁護派と XP 対立派に分かれて討論を行ったが,
# これが実に楽しかった.
# 平鍋 さん と 長瀬 さん はこの時のパネリストでもある.
の四人の皆さんの講演は,いずれの方も以前に何回もお聞きしたことがある.もし仮にソフトウェア技術者に称号というものがあるとすれば,是非グランドマスター (名人) と呼ばせていただきたい方々である.
# 今流行りの映画「スターウォーズ」でいえば,ヨーダが四人で話をしているような
# ものである (訳判らない喩えで申し訳ないが).
今回は,この方達が UMLの現状と今後を語られるというので楽しみである.
---------------------------------------------------------
早速ステレオ イヤホンを準備して「モデリング座談会」に入ってみる.
やがて平鍋 さん 達のゆるやかな話声が聞こえてきた・・・
資料 (PDFファイル) を見ながら,印象に残った部分のメモを取りながら聴くことにする.気に成った部分は,途中で止めて戻して聞き直したりすることが出来る.
メモの内容:
- 司会者あいさつ・講師紹介
- 討論内容について
- ポジショニング
- ポジショニング: 児玉氏
・大切なのは,モデリング.UML は単なる道具
・ソフトウェアを作るためにはモデリングはそんなに要らないかも知れないが,情報システムを作るのには必要
- ポジショニング: 長瀬氏
・コンポーネントベースの方法論「カタリシス」
・モデリングと開発プロセス
- ポジショニング: 平鍋氏
・UML は普及したのか
・Understandable が重要
・UML に対するポジション
- UMLの教育について
- UML よりはモデリングを教えよう
・でも実装から遠い抽象論になり勝ち
- 実際に動かせることも大切
- 何故モデリングが必要か
・理解するためにモデリングは必要
・理解の道具として UML が有る
- 同じ題材でモデルを描かせてみる
- 良いモデルを沢山見なければ駄目
- UMLによるビジネスモデリング
- 活動図を因果図に拡張
・大きなシステムの中の問題点を図で明らかに出来ないか
- きちんとしたモデルを作る必要があるか?
- モデルが酷いと作っている最中にモデルがぶれる
・生産性が落ちる- 実際のシステムでは巨大なモデルに成る
・構造がうまく出来ていないとうまく行かない- 要求は作っている途中に変わる
・其れを受け入れるのがアジャイルだが,或る程度見越したモデルを作っておかないと破綻する- モデルは仮説
・仮説を立てて実装で其れを実証する- 「システムを作る」にはモデルは必須.
- マッピングさえうまくいってれば必ずしも詳細な UML は必要ない
- コミュニケーションは互いのボキャブラリによって詳細さが変わる
- UMLの将来像
- 要求を描くツールになれば良い
- どんどん拡張していっているが,シンプルさ判り易さが失われている
- 仕様は今の儘で十分.どう使っていくか,どう楽しんで行くか,実験的なアプローチが今後必要かも
今回特に Agility (アジャイルさ) の高い方が多かったせいか,話が形式的な方へ行かずに楽しい方に向かったような気がする.
改めて,大切なのは UML そのものの正確な書き方ではなく,モデリングが出来るように成ることである,と思った.
もっと UML が高機能に成ってその文法を覚えれば開発がうまく行く,というものでは多分ない.
私は,多くの危ういプロジェクトを抱えたソフトウェア開発の現場に特に欠けているのは「モデリング能力」と「開発プロセス」であることが多いのではないかと考えている.
少なくとも私のところではそのようである.そして,今後はこの二つの教育にこそ力を注いでいく必要が有ると思っている.
但し,UML はモデリングのための単なるツールなのかも知れないが,やはり UML の基本的な部分は,マスターすべきだと思う.
日本語を話す人が日本語のボキャブラリや語順に思考を左右されるように,オブジェクト指向の考え方に不慣れな初学者が,UML を覚えて UML を「話す」ことで,思考プロセスがうまくオブジェクト指向型に制限されていくような気がする.オブジェクト指向のグランドマスター (名人) にも成ると逆にこの制限が邪魔になることも有るかも知れないが,初心者マークのうちはこの制限が良い方に働くような気がする.
開発プロセスにしてもデザインパターンにしても同様で,最初は名人や達人のやり方を,パターンとしてどんどん積極的に模倣していくようにする.そうすることで,理解が困難だった思考プロセスを,体験の中で徐々に掴み取って行けるのではないか.
このセッションの途中で平鍋 さん が「何かを学ぶためには,自分で体験する以上にいい方法はない」というアインシュタインの言葉を引用されていた.その通りだと思う.そして,同じくアインシュタインの言葉を借りるなら「若いうちはすべての規則に従ったほうがいい.そうすれば年をとってから規則を破る力が手に入る」.
最初から講師の方達 (つまりはグランドマスター) のようには行かない.
XP 等のアジャイルな方法論の良いとこ取りをしているつもりで,若葉マークのうちから,「きちんとした UML を描く必要はない」とか「デザインパターンも必要ない」とかやっても多分幸せはやって来ないのではないか.
例えば,書道の達人が草書ですらすらと書いているのが格好良く見えるからといって,書道を始めたばかりの者が最初から「くずし字」から入ろうと思っても無理が有るだろう.
最初は面倒に思えても,たとえ非効率に思えようとも,モデリングをきちっとやってクラス図もきちんと描いて,描いた図のメンテナンスもして,UML 対応の CASEツールなんかも試してみて,つまりは,楷書から徐々に使えるようになって,そしていずれ「楷書は書くのに時間が掛かるし無駄が有るなあ」ということに気が付いて行ければ良いのではなかろうか.
・・・というようなことを考えた.
講師の皆さんは,いずれも,初学者には難しい概念を,御自身の中で十分に消化されて出て来たらしい言葉で判り易く語られていたのであるが,たまに話の抽象度がずーっと上がっていくことが有ったような気がする.
思うに,今回は多分ビデオカメラを前にしての座談会で,聴衆が目の前に居ないためではなかったろうか.
つまりこの場合,グランドマスター同士が話をしているために,四人の間では,その抽象度で話が十分に通じてしまっていたと.
GoF のパターンを知っているもの同士が,「このクラスは Mediator だ」という説明でそれ以上言葉を必要としないように.
キリストや釈迦が説法でいつも喩えを使って話をしたように,適当なメタファが有るとぐんと話が判り易くなるものである.もしそこに聴衆が居たならば,その反応を見て抽象的な話の中に具体的な話が適度に混ざって行ったのではなかろうか.
座談会の中で出て来た言葉だが,「コミュニケーションは互いのボキャブラリによって詳細さが変わる」のである.
唯,今回に限って云えば,そうした雰囲気も楽しかった.
抽象度の高い話を聴く時は,自分の持っている既成の概念に新しい概念を自分でつなげて行くことに成るが,その緊張感がなんとも楽しかったのである.
盆休み中に,テレビで「POP HILL 2002」という音楽番組を観た.
私が子供の頃遠足で良く行った「石川県森林公園」という公園が有るのだが,そこに野外ステージが作られ,若いミュージシャン達がジャズを演奏していた.
ドラムスやウッドベース,ピアノ等が交互にソロを取る.勿論テーマは有るのだが,各自が自由にアドリブを聴かせる.
私は,その演奏を楽しみながら,「モデリング座談会 --- UML の現状と今後」のことを,テレビで観るジャム・セッションのようだったな,と想い起こしていた.

| © 2002 OGIS-RI Co., Ltd. |
|