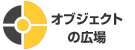7 月に 6 日間にわたって実施した当社の新入社員向け研修をレポートします。Creation Style 新人研修は、オージス総研が独自に開発した「OGIS-Creation Style」をベースに、筆者らが所属するビジネスイノベーションセンターがカスタマイズしたものです。
目次
1. はじめに
当社の Creation Style 新人研修は、2021 年から技術部ビジネスイノベーションセンター(以降、BIC)が主催し、今年で 4 回目を迎えました。この記事で、BIC がオージス総研に入社した新人向けに行っている研修について、紹介・公開していきたいと思います。
なぜ、BIC が新人研修を行うのか
元々は社外のお客さまに提供したり教えたりしている「OGIS-Creation Style1」の更なる進化のための実験も含めて、社内でも「デザイン思考」や「アジャイル開発」について知識だけでなく経験を広めたいと思ったことがきっかけでした。
とはいえ、デザイン思考やアジャイルとなると座学だけでも相当量あり、学んだことを身に着け、自分自身が扱えるツールボックスの 1 つとするにはワークショップのような体験も必要になります。特に組織やチームを率先するマネジメント層やリーダー層に研修を受けるまとまった時間を取ってもらう事は難しく、白羽の矢が立ったのが「入社したての新人」なのでした。
いつ、新人研修を行うのか
それなら人事部が行う 4 月、5 月の新人研修に追加したい!と考えましたが、新人研修のスケジュールは既に組まれています。配属後の所属が行う 6 月頃の OJT 期間も検討したのですが、オージス総研は大阪だけでなく、名古屋や東京にも事務所があり、配属後に引っ越しもある新人さんの新社会人生活を考え、生活が落ち着く 7 月中ごろに行う事が慣行となりました。
BIC が新人研修を始めた 2021 年はまさにコロナ禍だったため、在宅でオンライン研修しながら、チームで成果を上げる!そんな無茶も 4 年続けば恒例行事になっていきました。当初は「忙しい」「新人に無理」と言われた研修も、年々、参加者も増え、今では全ての新人さんを預けていただけるようになっています。
OGIS-Creation Style"新人"研修の目的
本研修は、「OGIS-Creation Style1」の考え方をベースとして、デザイン思考とアジャイル開発を融合して体験する形になっています。座学よりもグループワークを中心として進めています。

BIC としては、デザイン思考やスクラムそのものだけでなく、新人研修の最初に以下を伝え、「期待を上回る新人」になることを目指しています。
- 自己組織化チームを目指すこと
- チームとして目標達成に貢献できるように学ぶこと
- 教え合い、助け合うことでチームになること
- 0.5 歩先に挑戦し、失敗を歓迎すること
- 以上を通じて、自分たちのチームとしてベストを見つけだすこと
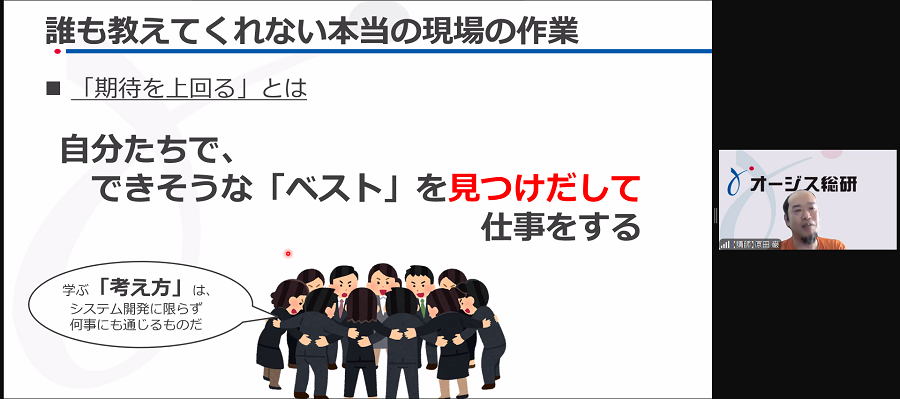
研修の特徴
研修の目的を達成するために、あえて「正解のない」お題を受講生には考えてもらっています。
2024 年度は、社内からお悩みを持ち込んでくれる人を募集し、その人を「ユーザー役」と見立てて、真の問題を発見し、それを解決する IT サービス(スマホや WEB で操作できるもの)を作ります。講師陣は、研修のプロセスとしてやって欲しいことを細かく指導はしますが、「正解はユーザーの中にしかない」ため、受講生と共に何ができたら良さそうか、それに気付いてもらうためにチームにどのように介入すべきかを、伴走しながら考えるしかありません。
そのため、受講生だけでなく講師陣も必死に学び、共にユーザーに役立つソフトウェアを提供することに頑張るしかない仕組みです。
グループワークで受講生が議論している様子を眺めては、講師陣は裏で情報交換しつつ、チームごとに介入したり、伝わっていないことや理解して欲しい事があれば、後続のグループワークの内容やテキストの補記を考えたりしながら進めています。
「ユーザー役」も本当に困っている事を持ってきていただき、真正面から受講生に真摯に向き合う必要があります。時には真意が伝わらなかったり、ユーザーの態度や表情から漏れる情報を受講生が見逃したりしながら、それでも複数回のインタビュー、受講生が考えたプロトタイプのテスト、実際に操作できる画面を通してユーザーの真の要望を捉えるようなプロダクトを「みんなで」探し続ける研修になっています。
研修の内容
研修は 6 日間(2021 年度 4 日間、2022 年~ 2023 年度 5 日間)で実施しています。延びていった内訳は、デザイン思考が 1.5 日→ 2.5 日、AWS 環境構築を 0.5 日の追加です。

「OGIS-Creation Style1」を元に、外側のループをデザイン思考、内側のループをデザイン思考のプロトタイプとアジャイル開発として実装しています。そのため、プロトタイプの検証や、スクラムでプロダクトを実装したレビュー結果によって、ユーザーインサイトが違うと分かれば外側のループに戻って考え直すことも推奨しています。
主なタイムテーブルは以下のようになっています。
▽1日目
- 研修概要と目的の説明
- AWS環境構築
- デザイン思考(共感)
▽2日目
- デザイン思考(共感のつづき、問題定義、創造)
▽3日目
- デザイン思考(創造つづき、プロトタイプ、テスト、サービスブループリント)
▽4日目
- アジャイル、スクラム(座学)
- 要求開発(全体イメージ、MVP、プロダクトバックログ作成、スプリント1)
▽5日目
- グループワーク(スプリント1つづき、スプリント2、スプリント3)
▽6日目
- グループワーク(スプリント3つづき、スプリント4)
- お披露目会
- 全体振り返り(Fun/Done/Learn)
いかがでしょうか。盛り沢山ではあるのですが、研修を通じて、新人にはゼロからモノゴトを考えて作り上げていく困難さと喜びを感じてもらえたのではないかと思っています。
2. 研修の実施形態
全日程をオンラインで実施
本研修は全日程の 6 日間をオンラインで実施しています。
研修中は講師も受講生も自宅やオフィスなどそれぞれが受講しやすい場所から参加します。物理的に離れた場所からの参加になるため、画面越しのコミュニケーションも重要です。このため、研修の冒頭にはオンラインで気にかけるとうまくいく「オンラインコミュニケーションパターン2」を紹介しました。
その中でも「うなずきマシマシ」は早い段階からうまく取り入れることができました。うなずくなど反応することで声を出さなくても双方向のコミュニケーションが実感できて、講師にとっても受講生が理解できたかどうかの把握がしやすかったです。
グループワークを中心に進む研修
研修はグループワークを中心に進めます。グループ構成は、受講生が主体的に参加しやすいこと、講師がグループのサポートをできるボリュームを考慮して、6 人前後×6 グループとしました。グループのメンバー割り振りは全体的なバランスを考慮して講師が事前に決定しました。
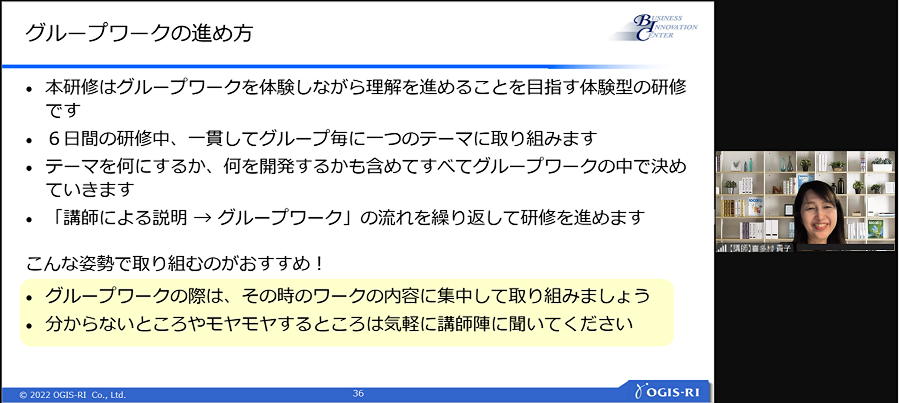
グループワークの際は Zoom3 のブレイクアウトルームを使っています。一斉にブレイクアウトルームをスタートし、各グループは別々のルームに分かれて集中してグループワークを行いました。研修後半の開発などタスクを分担して進めたい時のために予備のルームも用意。開発が活発になると複数のルームに散らばって作業する様子が見られました。
オンラインホワイトボード Mural を活用
グループワークで話し合ったことや検討したことは、オンラインホワイトボード Mural3 に記録しました。Mural は複数のメンバーが同時にアクセスして付箋や画像を参照したり編集したりすることのできるクラウドサービスです。

グループ毎に Mural を用意し、デザイン思考からスクラムまで、実装以外の全てのグループワークは Mural を使って行いました。

3.ユーザーに向き合うグループワーク
研修の特徴でも触れましたが、この研修ではあらかじめ正解の分からないお題に向き合います。そのためにユーザー役が本当に困っているお悩みを持ち込みます。ユーザー役はインタビューなどに協力的な姿勢で対応しますが、ユーザー自身が「本当は何が欲しいか」の答えは持っていません。
デザイン思考とスクラムのグループワークを進める中で、自分たちが考えた仮説がユーザーにとって有用なのかをテストし、ユーザーの反応によっては仮説やアイデアを考え直し、ユーザーにとって本当に必要なものを提供するために探索します。
自分でもどうしたら良いか分からない悩みを持ったユーザー
ユーザー役は社内からの公募で 3 名の社員が担いました。
それぞれのユーザーは自分が抱えるもやもやした悩みを持ったまま、あまり深く考えすぎないようにして研修に臨みます。ユーザーが持つ悩みはユーザー自身の本当の悩みです。研修用に設定した架空の悩みではインタビューに答えるなどユーザーとしての振る舞いは難しく、ユーザー役は務まらないのです。
あるユーザーの悩みは以下のようなものでした。(ユーザーによって悩みは異なります。研修では 1 グループが 1 人のユーザーを対象としました。)

これに対して、まずはデザイン思考でアプローチします。ユーザーに共感するためにインタビューを行い、インタビューの内容を分析してユーザーの本質的なニーズを探ります
インタビューをもとに段階的にインサイトに近づく
ユーザーにインタビューして共感しても、ユーザー自身が気付いていない本質的なニーズが何かを考えるのは難しいことです。できるだけ段階的に検討できるように、今回はインタビューの分析で上位下位関係分析を用いました。
本研修の上位下位関係分析では、インタビューで得られた事実をもとに、グループでインタビューを思い出して話し合いながらユーザーがなぜそのような行動をするのか、さらに、ユーザーの本質的なニーズは何だろうか、と段階的に検討して付箋に書き出していきました。
検討の過程が Mural 上にすべて付箋で示されるので、立ち戻った時に分かりやすく、講師のアドバイスもしやすかったです。グループワークの時間はかかるのですがそれよりもメリットが上回った印象です。

そして、上位下位関係分析をもとにインサイトを定義します。講師はユーザーではないのでインサイトが正しいのか間違っているのか答えることはできません。ユーザーのフィードバックが第一です。
ただ、それだけを言っていてはグループワークが進みにくいことがあるので、今回は講師がグループへアドバイスする時間も設けました。グループが考えたインサイトをいくつかピックアップし、深いところまで考えられているか(良さそう)、まだ表面的なレベルでしか考えられていないか(もう一息)を全体に共有しました。
インサイトを定義した後はアイデア出し、プロトタイプ作成、テストを経て、開発対象の全体像を決めてスクラム開発に入りました。スプリント(各スプリントの開発時間は 100 分)を 4 回実施して AWS 上の開発環境で動くものを作りました。
開発したプロダクトの社内向けお披露目会
研修最終日の 6 日目には社内向けに研修成果を発表するお披露目会を行いました。お披露目会は最終スプリントのスプリントレビューに位置づけているのでユーザーにも参加してもらいます。当日は 100 名ほどの聴講者がいて盛況でした。
グループ毎に、対象としたユーザーの紹介、インサイト、作成したプロダクトのエレベーターピッチを説明してデモを行いました。デモは Amazon CloudFront を利用して Web ブラウザからアクセスします。操作は発表者にナビゲートしてもらいながらユーザー自身が行いました。

筆者はユーザー役として 2 つのグループが開発したサービスのデモを体験しました。短いスプリントの時間でよくこれだけ作り上げたと感心する出来栄えで、画面を触りながら本当にわくわくする体験をしました。前半のフィードバックをもとにユーザーのことをじっくりと考えてくれたのだと感じられるアイデアが盛り込まれていたのもうれしかったです。
お披露目会の後は、Fun/Done/Learn で研修を振り返り、 6 日間の研修が終了しました。

4.受講した新入社員の声
前章までは講師から研修内容を紹介しましたが、受講した新入社員はこの研修をどう感じていたのでしょうか。本章ではアンケートとインタビューの内容を紹介します。
アンケートのコメント紹介
アンケートでは研修の満足度や理解度に加えて、今後さらに学習や実践をしたい分野についても聞きました。「AWSなどクラウド開発環境を使った開発」に並んで「チームとしての協働」をもっとも伸ばしたいと答えた方が多く、以下のようなコメントがありました。
- この研修を通してチームとして協働することの大切さを感じた。
- チームの話し合いで出た意見がユーザーからの評価がよかった。自分一人では絶対になしえなかったことと感じた。
- 実装の部分で壁にぶつかることが多かったが、それをチームメンバーと乗り越えることができた。
- グループ間のコミュニケーションで定期的な進捗報告をすることや、オンラインでうなずきだけでなく声を出して反応するなどのやり取りは、仕事ですぐにでも実践できそうだと思った。
これら以外にもチームの協働に関するコメントは多かったです。また研修を通じて以下のようにさまざまな気付きが得られたことが分かりました。
- デザイン思考でニーズをくみ取って、構想が形になっていく過程がとてもわくわくした。
- もっと本質的なところを考えた方がいいのではないかと思いながら見せたプロトタイプはやはり反応が良くなかったりして、初めに思っているより数段階本質を考えるべきだと実感した。
- 自分のアイデアを好きなだけ他人と共有する機会は今までなく、良い経験になった。
- 今回は時間が短かったので、今後、より本格的なスクラムを体験してみたい。
- AWSなどの開発環境を使った開発は今後非常に役に立つと思った。
- 役割決めやスケジュール管理、ユーザーの本質的なニーズを引き出すなど、チーム開発の難しさを痛感した。
新入社員へのインタビュー

さらに新入社員の生の声も聞こうと、技術部データエンジニアリングセンターに配属となった木村 優斗さん(写真)に後日お話を伺いました。
── 研修を振り返ってどうでしたか?
4 月から新人研修を共にしたメンバーと久しぶりに一緒にグループワークに取り組むことができたのが有意義でした。
配属されてから同期とまったく会わなかったので不安なところもありましたが、実際に顔を合わせて近況を話すこともできたのが良かったです。今後のモチベーションにもつながる機会になりました。
── 研修で印象に残ったところはありますか?
デザイン思考の共感の部分が印象に残りました。共感は、同情とは違う、もっとお客様の側になって考えることだと教わりましたが、この意識はこれからの仕事においても、仕事以外においても大切にしなければいけないことだと実感しました。
自分たちのグループではユーザーへのインタビューの際に、ユーザーが答えられないことであっても寄り添う形で問題を解決していこうと方向性を決めたのですが、共感を学んだことがそのような意識付けにつながりました。実際にインタビューする際もそのことを意識できたことが印象に残っています。
── 大変だったところは?
スプリントが短い中でどのように分担してどこまで完成度を目指そうか、というところに苦労しました。チームとしては、一人のメンバーの負荷が高くなってしまったので、感謝もありつつ申し訳なさもあるという気持ちでした。
── 研修のグループワーク全体を通してうまく分担ができればと思っていましたが開発での偏りを気にしていたチームが他にもありました。開発でスプリントを4回繰り返しましたがそこで変化はありましたか?
最初のスプリントは作業の進め方をあまり考えずに始めてしまいましたが、スプリントを進めるうちに、最初に休憩時間や役割分担を考えるなどしっかりと準備ができるようになりました。
── スプリント毎に振り返って良い変化ができたのでしょうね。今回の研修で今後に活かしたいところはありますか?
先ほど述べた共感のところは業務でも活かしていきたいです。また、これから AWS を使う機会があるので AWS の講義で聞いた内容も役立てたいです。
── 今回の研修を他の人に勧めるとしたら?
来年の新人に向けて言うとしたら、新人同士で集まって一つの仕事を進められるので、コミュニケーションの面で楽しんで進めてもらえたらなと思います。6 月までの研修で教わっていないことも基礎的なことから教えてもらえるので勉強になります。
── それでは最後に。オージス総研でこれから何をやりたいですか?
大学と大学院で画像認識の研究をしていました。業務でも画像認識に携わりたいと思っており、その予定です。画像認識で社会の困りごとに取り組んでいきたいです。
── 今回の研修の内容も活かして、ぜひがんばってください!
5.講師の声
最後に、本研修に携わった講師の声を掲載して本レポートを終えたいと思います。

原田:
全体の企画・設計およびスクラム講師として、Creation Style 新人研修は毎年、改善を重ねて4年目となりました。
今年は部署を超えた協力や、ユーザー役を社内公募し、多くの人の連携によって開発環境構築から要求開発・システム開発まで全工程をカバーするに至りました。
新人にとっては無茶な挑戦に感じたと思いますが、それを体験できることが「研修」の良さであり、その経験が普段の仕事から大きな問題や課題に直面した時まで全てにおいて活きると信じ、頑張ってくれた新人の皆さんに伴走する形で貢献できたことを嬉しく思います。

喜多村:
今年はデザイン思考のメイン講師を担当しました。新たに増やした狙いは二つ、「開発前にユーザーのインサイトに腹落ちできている」と「毎日成長を実感し合えている」。インタビューや分析やアイデア創りや検証等に取り組む姿勢は、真剣だけど楽しむことを忘れない皆さんでした。それってとても大事で、なかなかできないことです。
この学びや経験は職場で活かせるところがありますが、もし相談してみたいと思う時は遠慮なく声をかけてください。私たちの学びにもなりますので!

山中:
Creation Style 研修はデザイン思考やスクラムがメインですが、今回新しく AWS の学習も兼ねた AWS 環境構築を研修内容に追加しました。
約半日という短い時間に AWS の基礎学習から環境構築まで詰め込んだのでわかりにくい点もあったと思いますが、まずは実際にさわってみて AWS に興味を持ってもらうことを目標に研修内容を考えました。なので、アンケートで AWS を今後さらに学習したいという声をもらえたのはうれしかったですし、やってみて良かったなと思います。
今回は基本的な内容だけでしたが、これを足掛かりにどんどんスキルを伸ばしていってください。

荘司:
入社後に実施された新人研修の個人開発研修、そして今回の Creation Style 研修で、主に技術的な面のサポートとして参加させていただいています。
新人の皆さんの開発レベルが上がっていることを実感しています。開発以外の職種でも開発のことがわかっているとスムーズに話を進められることもあると思います。これからの仕事の糧として学んでいただけたなら幸いです。
以上、講師からのコメントでした。
1ヶ月前に本研修を終えた新人の皆さんは、現在は配属先の部署で新たな業務に取り組んでいると思います。今回の研修はそれぞれの仕事の場面で必ず役立つ内容だと思っています。ぜひこれからもがんばってください!
-
「OGIS-Creation Style」は、従来のデザイン思考にオージス総研独自の方法論 「行動観察」を加えた顧客の本質的な「価値発見」と、頻度高くクイックなアジャイル開発による「価値検証」を繰り返し行うモデルです。詳細は OGIS-Creation Style をご覧ください。 ↩
-
本文中に掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。 ↩