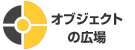「話すことが好きだけど相手は無理していないかな」「一度の説明で相手に伝わればいいのに」——そんなリアルな悩みを出発点に、54名の新入社員が10チームに分かれ、7日間でプロダクトを開発。デザイン思考とスクラムを用いて、ユーザーが本当に必要なプロダクトを創りました。本レポートでは Creation Style 新人研修2025の様子をお伝えします。
目次
- Creation Style 新人研修とは
- ユーザーは新人に近い先輩たち
- 本当のニーズを捉え、フィードバックで軌道修正
- 実践を意識して取り入れた UI 視点とビジネス視点
- 一人ではできないことも、チームで生み出す
- 受講者の声
- 運営側から見た研修の振り返り
- おわりに
Creation Style 新人研修とは
私が所属する技術部ビジネスイノベーションセンターでは2021年度から新入社員向けに「Creation Style 研修1」という研修を実施しています(2024年度のレポートはこちら)。Creation Style 研修は、ユーザーの声に耳を傾けながら、チームでデザイン思考・スクラム開発を段階的に体験する構成です。今年は、UIデザインの基本や事業化の視点を加え、より実践に近い形へと進化させました。
ユーザー役は社内の若手社員5名。それぞれ“コミュニケーションの悩み”を持ち寄りました。受講者である新人たちは、ユーザーの話を聞き、どんな問題をどのように解決するか考えます。この研修では、正解が用意されているわけではありません。ユーザーのフィードバックを得ながら、プロダクトをかたちにしていきます。
研修のおおまかな流れ
下の図は、7日間にわたる研修のおおまかな流れです。全て Zoom2 を使ったオンライン形式で実施しました。

研修の最初は、まず「誰の」「何を」解決するのか、実際にユーザーの話を聞いてチームが自分たちで定義します。そして、「どのような価値を提供するか」アイデアを形にして、ユーザーのフィードバックを得て検証を繰り返し、ユーザーが本当に必要なプロダクトを開発していきます。
ユーザーは新人に近い先輩たち
今回の研修では、2年目から5年目の若手社員5人がユーザーとして参加しました。事前に講師はそれぞれのユーザーからコミュニケーションに関する悩みを教えてもらい、テーマを設定しました。
仕事やプライベート、その両面など様々なテーマが挙がりました。研修日程の都合上、各チームは1人のユーザーに対応します(各チームは1つのユーザーテーマに対応します)。
ユーザーテーマ(一部)
- ぐいぐい話しかけたいが、相手の反応が薄くて気後れしてしまう
- 話すことが好きだけれど、相手が無理していないか気になってしまう
このような、年の近いユーザーたちのリアルな悩みに、受講者たちはまず共感するところから始めました。
本当のニーズを捉え、フィードバックで軌道修正
最初のグループワークはデザイン思考。ユーザーにインタビューするところから始まります。聞いたことをそのままニーズとするのではなく、さらに奥にあるユーザーの本当の望みや気持ち、本質的な要求を探るため、上位下位関係分析法を使って階層的に分析し、インサイトを導きました。
次に、インサイトを満たすアイデアを、ブレーンストーミングと強制発想を用いて発想。プロトタイプをユーザーにテストし、方向性を決めたら、UI デザインとクラウド・AWS の基礎講義を経て、ユーザーの定期的なフィードバックを得ながらスクラム開発を進めました。
ここで大切にしたのは、チームで協働し、意見を出し合って考えること。そして、ユーザーからのフィードバックをもとにした検証サイクルです。
7日間の研修期間中に5回のフィードバックを実施しました。受講者はフィードバックの必要性を素直に理解し、ユーザーの反応をもとに、初期のプロトタイプから大きく方向転換したチームが複数ありました。
もちろん、ユーザーの反応が思わしくないときには肩を落とす場面もありましたが、すぐに立て直し、次にぶつけたアイデアで良い反応を得られた瞬間には、メンバーの表情が一気に明るく変わりました。その変化は画面越しにもはっきり伝わってきました。
実践を意識して取り入れた UI 視点とビジネス視点
また今年は新たな試みとして、研修の中盤と終盤に新しい要素を取り入れました。
ひとつは、スクラムの前にUIデザインの基本を学ぶ時間を設けたこと。ユーザーの悩みを“伝わるかたち”にするプロセスとして、UIの視点を持つことが、アイデアを実装する上で助けになりました。
もうひとつは、終盤にリーンキャンバス3を用いた事業化の視点を導入したことです。自分たちのプロダクトがビジネスとして成立する可能性を考える機会を設けました。
ここまで1人のユーザーに向き合って考えたプロダクトの事業性を検討し、持続可能なビジネスモデルを構築するためにどのような要素が必要か、リーンキャンバスで言語化しました。
新人研修としてはチャレンジングな内容でしたが、自分たちのプロダクトのビジネスについて楽しく構想できたチームもありました。
一人ではできないことも、チームで生み出す
チームメンバーは、受講者の特性を考慮し検討しています。受講者はそれぞれ、チームをまとめる力、コミュニケーション力、技術力など様々な得意分野やバックグラウンドがあり、個性もいろいろです。できるだけ多様なメンバーになるようチームを構成しました。
また、研修の冒頭で「1+1=2以上」のチームになろうとメッセージを伝えたり、グループワークの度に、メンバーで話して意見を出し合って考えようと伝えました。

作業スピードだけを優先すれば、得意な人に任せて分業する方が速いかもしれません。けれど、大切なのは価値あるものを速く届けること。そのためにチームが協働して、より良いものを作るために進めていくことが大事だと伝えました。
その結果、オンラインでのグループワークという難しさはありながらも、チームで協働して新しいことに挑戦できたこと、チームで1つのものを作り上げたことなど、共同作業でしか得られない達成感を得たという声が聞こえたのでうれしく思います。
研修で生まれたプロダクトを少しだけご紹介
さて、この研修でどんなアイデアが実現されたのか興味がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで、少しだけここに紹介します。
あるチームは、「ぐいぐい話しかけたいが、相手の反応が薄くて気後れしてしまう」という悩みに向き合いました。インタビューを通じて、ユーザーが踏み込んだ話をしたいのは、多くの人の価値観に触れたいという欲求があるからだと考え、「深みのある人間になりたい」というインサイトを捉えました。そして、価値観共有アプリを開発。初対面でも深い話ができる仕組みをうまく機能に取り込みました。

別のチームは、「話すことが好きだけど、相手が無理していないか気になる」という悩みに取り組みました。インタビューを通じて導いたインサイトは、「自分も含め、コミュニケーションで無理している人を減らしたい」。このチームが開発したのは、カジュアル名刺です。

名刺には、自分のコミュニケーション傾向を動物タイプで記載できるようになっており、お互いに無理のない会話の入口をつくることができます。ユーザーからは、「タイプを選ぶという形式が気軽だし分かりやすくて良い」と評価されていました。
10チームいずれのプロダクトも、ユーザーの悩みに真剣に向き合うところから出発し、短期間ながら実際に“使われるもの”を目指して開発を進めました。
受講者の声
7日間、頭も手もフル稼働で挑んだ研修。アンケートには、一人ひとりが学びを自分のものにしている様子が表れていました。アンケートを抜粋、一部加工してご紹介します。
体験することで学んだことや気づきがありました。
- 顧客の本質的な要求に答える、という当社の武器となるプロセスを実際に体験しながら学べた。
- インタビューを試行錯誤しながら実施する経験は貴重だと感じた。
- スプリントが100分×3回は短いと感じたが、全員で頑張れば案外どうにかなることが分かった。
この研修を通じて、自分の興味分野に気づいた人も!
- ユーザーと接し、ユーザーに近いところで行う開発は非常に面白かった。
- 自分が意外とビジネスの視点に興味があることに気づいて驚いた。機会があればビジネスに関することも携わってみたい。
- コーダーを AI が担う時代を見据え、自分が目指すエンジニア像が明確になった。
本研修は、入社後3か月間の人事部主催の集合研修を終え、配属先で2週間ほど過ごしてから実施しました。アンケートや研修最後の振り返り(Fun/Done/Learn)では、同期と再会できたこと、そして、同期と議論しながらアイデアをかたちにできたことを喜ぶ声が多くありました。

一方で、オンラインにおけるグループワークの難しさを感じた受講者もいました。これらの声は、より良い研修にするため、来年度に活かしていこうと思います。
運営側から見た研修の振り返り
ここからは、受講者としての体験から視点を切り替え、研修を運営する側の立場で振り返ります。
ユーザー役としての学び
今年のユーザーは前述の通り入社2年目から5年目の若手社員でした。これまで講師がユーザーになることも多かったのですが、受講者と年の近いユーザーの方が、より共感しやすいのではないかと考えて、今年初めて試行しました。ユーザー役は事前の準備や研修中のインタビュー対応、スプリントレビューへの参加など時間も負担もかかる役割です。
実際、ユーザー役を担ってどう思ったのか気になるところでしたが、全員がユーザー役を他の人にもおすすめできると言ってくれ、ホッとしました。そして、ユーザー役によって得られた気づきも教えてもらいました。
- ユーザーの立場はどのようなものか。こちらの対応によって、ユーザーがどのように感じるか体感できた。
- どのように伝えると技術面が分からないユーザーでも理解しやすくなるか、考えさせられる機会となった。
- インタビューを通して自己理解にもつながった。
また、新入社員と触れ合って刺激を得た人も。
- 自分にない発想でテーマに対する考え方やアクションを教えてもらえた。
- 真っ白なキャンバスに描かれる自由なアイデアが面白く、研修に参加するのが楽しかった。
これらの気づきは、ユーザーの皆さんそれぞれが真摯にユーザー役に取り組んでくれた結果だと思います。それとともに「ユーザー役にも学びがある」ということをあらためて実感できました。
過去最大の参加人数に対応する運営の工夫
今年は新入社員が増え、参加者が過去最大の54名、10チームでの実施となりました。そこで以下のような運営面の工夫をしました。
- 各チームが自律的に進められるよう、説明テキストをブラッシュアップ
- 講師は計13名に強化し、それぞれ、講義、グループワークのサポート、技術面のサポートを担当
- 研修中は Teams2 の投稿を使った情報共有で、全講師がチームの様子を把握

スペースの横に目的・ゴール・進め方を記載した説明テキストを貼りつけ、チームが自律的に動けるようにした。
講師は、部署を越えて必要な専門知識を持つメンバーを集め、合計13名が関わりました。
研修中は講師たちが Teams の投稿で、グループワークの進め方や理解度などの内容についてはもちろん、話し合いの雰囲気、体調など様々な情報を共有し、グループワーク全体の様子を把握しました。Zoomのブレイクアウトルームを10チーム見回るのは大変4ですが、投稿された内容なら追うことができます。
こうして様々な経験を持つ講師たちが準備を整えて研修に挑んだ結果、混乱もなく規模拡大に対応できました。講師自身もチームとしてこの研修を作り上げたのだと実感しています。来年度も、この場から多くの挑戦と成長が生まれることを楽しみにしています。
おわりに
本記事では2025年度に実施した Creation Style 研修の様子をお伝えしました。
この研修では、一人ではできないことをチームで実現する協働の力、そしてユーザーの声を起点にプロダクトを形にする過程など、多くのことを体験しました。特に、同期の仲間と議論を重ねてプロダクトを創り上げた、という声は印象深く、受講者の成長を感じました。ここで得た経験や姿勢を、これからの現場で存分に発揮してくれることを願っています。
本記事が当社の取り組みに興味を持ってくださった方にとって、少しでも参考になれば幸いです。

-
Creation Style 研修は、「OGIS-Creation Style」をカスタマイズして社内の新入社員向けに行っている研修です。「OGIS-Creation Style」は、従来のデザイン思考にオージス総研独自の方法論 「行動観察」を加えた顧客の本質的な「価値発見」と、頻度高くクイックなアジャイル開発による「価値検証」を繰り返し行うモデルです。 ↩
-
本文中に掲載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。 ↩
-
リーンキャンバスは、自分たちが考えたプロダクトやサービスが、社会に価値を提供し続け、持続的に成長する「事業」として成立するために、どのような要素が必要かを構造的に整理し、検証可能にするためのツールです。顧客、課題、提供価値、収益構造などを一枚のキャンバスに書き出し、全体像を俯瞰しながら改善していくことができます。 ↩
-
本研修は全て Zoom を使ったオンライン形式で実施しました。グループワークはチーム毎に Zoom のブレイクアウトルームに分かれて行います。チームが主体的にグループワークを進めるのが前提ですが、グループワーク中は講師が各ルームを見回り、やることが違っていたり、困った様子をしているなど、講師が必要だと思ったタイミングで声をかけてグループワークをサポートしました。 ↩