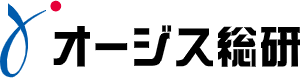WEBマガジン
「なぜマーケティングが重要なのか?(7)― 現在のマーケティング(中) ―」
2014.03.12 株式会社オージス総研 水間 丈博
今回は、本連載第5回「マーケティングが求められる背景」までの連載で提示した現在のマーケティング
- 新規顧客開拓のための伝統的ファネルマーケティング
- 国内の顧客維持競争に勝ち残るための競合優位追求型マーケティング
- グローバル市場で新たな顧客獲得競争に勝ち残るためのグローバルマーケティング
- 企業独自の魅力を発信し顧客を惹きつけるためのブランドマーケティング
- 顧客の潜在意識、購買動機などを徹底的に追及する顧客経験価値マーケティング
◆競合優位追求型マーケティング
(1)競合優位とは
ネバダ州の幹線80号沿いにあるガススタンドや富士山頂の山小屋とかでない限り、どの市場にも"競合"が存在します。例えば、日本の寡占業界の代表例とも言える「ビール業界」・「携帯電話キャリア」・「自家用車」のベンダーは誰もが上位三社を具体的に挙げることができ、その三社が熾烈なシェア争いをしていることも知っています。
企業は成長するにつれ自然と競合する環境にさらされることとなり、互いに相手を意識し抜きん出ようとします。なぜ企業は業界トップを目指すのでしょうか?
業界トップ企業はマーケット・リーダーと呼ばれます。マーケット・リーダーは市場を牽引することが可能で市場価格を主導することができ、社会的認知が高いため信用度が高まり、新製品を発売する際も自社に有利に展開できるとされています。シェアが高いために投資効率が向上し利益率もチャレンジャーやフォロワー(リーダー企業を追う企業)よりも高くなることが通常です。
一方、先頭のランナーがもっとも風の抵抗を受けるようにマーケット・リーダーは真っ先に市場の厳しい評価を受ける運命にあります。また市場維持や拡大のために多額の継続的投資を余儀なくされます。すぐ後ろには競合企業が控えていますから、小さな戦略のミスやフォロワーのイノベーションによりリーダーの地位から転落する危険性もあります*1*2。
- *注1:
- アサヒに逆転されたキリンビール・軽自動車車種別販売一位をホンダに奪われたダイハツ・やせ細る一方のシェア NTTドコモなどが代表的な例である。
競合優位の戦略や業界内での地位による戦略の選択については、M.ポーターの戦略論やP.コトラーの競争地位戦略論が有名で、いずれも30年以上前に発表された古典的著作です。
この間、戦略論も世界の市場環境の変化やグローバル化の進展により数々の論考がなされ、批判的論評も多いですが、戦略の基本として今でも有益な示唆に富んでいると考えます。
(戦略論はマーケティングと密接に関係しますが、本題の趣旨からやや外れますので、参考コラムで触れています。)
- *注2:
- シェア逆転の事例
- ・1960年代から長期にわたりビール業界第3位だったアサヒビールだったが、1987年に発売した「スーパードライ」が大ヒット、ビールの新たな定番の座を獲得した。その後少しずつシェアを伸ばし2001年ついにビールシェア第一位を獲得するにいたった。以後ビールシェアトップの座をほぼ維持している。
- ・2013年度の年間軽自動車販売台数トップはホンダのN-BOXで約235,000台だった。ダイハツ「ムーヴ」は懸命に追い上げたものの205,000台で約3万台及ばなかった。N-BOXはマーケットリサーチで「ハイトワゴン」と呼ばれる全高の大きいキャビンを持つ車種が存在しなかったことから、2011年に新発売されたホンダの戦略商品だった。斬新なデザインが評判となって大ヒット、2年連続20万台以上を売り上げている。2012年度には「カーオフザイヤー」や「グッドデザイン賞」も受賞。ダイハツ・スズキの軽自動車2強と下位メーカーのシェアを浸食し、2012年度シェアは18.4%で前年度から倍増させた。
- ・携帯キャリアのNTT DoCoMoは2002年当時、契約シェアがほぼ60%に達し純増数も断トツで1位を続けていた。その後CDMA2000を引っ提げたKDDIの台頭、ソフトバンクによるVodafone買収と新規参入、Apple iPhone導入などによる追い上げにあい、2013年4月にはシェア46.5%にまで低下、純増数もソフトバンク・auの後塵を拝することが多くなった。ここ10年程の間に移動体通信の国内総契約数はほぼ2倍(2002年約7千万台→2013年約1億32百万台)に増えているが、ドコモの契約数は約50%増えたに過ぎず、競合2社がそれぞれ約3倍に増やしたことと比較すると大きく劣る結果となっている。
参考:「一般社団法人電気通信事業者協会統計」
(2)現在の競合優位追求型マーケティングとは?
現在の競合優位を確立する鍵は
● 「イノベーション」
● 「顧客の納得する新しい価値」
● 「反復型組織的学習」
の3つと考えます。
現在はインターネットによる情報革命やソーシャル・メディアの進展により市場の勢力分布や競合の戦術、市場の反応などをかつてとは比較できないほど迅速に把握することができます。それは競合相手にとっても同じです。ネットは空間に依存しませんので、これが国内だけでなくグローバルな競合市場でも同じ条件になります。従って現代は極めて競合優位を持続することが難しい時代になったといえます。そのため、競合ひしめく市場(「レッド・オーシャン」とも呼ばれる)を回避し新たな市場を創造しようとする戦略(「ブルー・オーシャン」と呼ばれる)が現れています*3。
しかしブルー・オーシャンも遅かれ早かれレッド・オーシャンになることが目に見えています。どのような工夫も、いずれは模倣され差別化できなくなる可能性が高いのです。ポーターの「競争の戦略」はできるだけ競争しない戦略と呼ばれました。今は競争を避けるための策を極める方向ではなく、イノベーションを絶えず継続させて常にブルー・オーシャンの一角を占め続けることが重視されています。そのためにはイノベーションから顧客にとっての新しい価値を提供続けることが必須となるのです。新しい価値とは、顧客が感じる新たな魅力や共感と置き換えることもできるでしょう。
現在、イノベーションはR&D部門だけで生み出されるものでないことはもちろん、新規事業部門など限られた事業セグメントにのみ期待されたものでもなく、企業全体で取り組まなければならない時代と言われるようになりました*4。それを実現するために反復型組織学習能力を企業として身につけなければならなくなりました。小さく始めて素早く試行し、改善を続け、進化し続ける学習する組織の確立が必要とされてきたのです。
MITスローン校のP.センゲは、その著作「最強組織の法則」で"情報化時代の複雑性や変化が加速する世界で、競争優位は個人と集団の両方の継続的学習から生まれる"*5と指摘しています。
以下に、「イノベーション」、「ブルー・オーシャン」、「組織的学習」を上手く取り込んだと考えられる事例を挙げます。
- <事例1>油を使わず揚げ物を作る「ノンフライヤー」
- フィリップス(蘭)が2010年に発売した油を使わないフライヤー「ノンフライヤー」はまたたく間に100万台を売上げ、大ヒット商品となった。日本には2013年4月に上陸、調理家電で2万円台という価格にもかかわらず高評価を維持している。
- 【解説】
- "油を使わずに揚げ物を作る"という固定概念を覆したイノベーション製品と言える。食物に含まれる油分を熱風で高温にして調理するもので、余分な油が防げるため、ヘルシーさを打ち出したこともヒットの要因と言われている。現在数々の競合品が追従しているが、イニシエーターのブランド力は強く、高価格を維持できているようだ。
- <事例2>「コンビニコーヒー」
- 国内大手コンビニチェーンの店頭における「低価格コーヒー戦争」が白熱化している。元々は2008年にマクドナルドが100円コーヒーを提供してヒットしたことに倣ったもの。しかしコンビニ各社の予想を超えてこれが大ヒットし、セブンイレブンでは年間4億5千万杯を販売する勢いと言う。2013年度「日経トレンディ」の年間ヒット商品第1位に選定された。セルフ式・店員が入れる方式、さらにメニューを豊富にするなど各社戦略はまちまちで、各社が差別化戦略を試行中。しかし、新たにネスレ日本がリアル店舗「カフェ ネスレ」展開を開始するなど、競合乱立の状況になりつつある。
- 出典:日本経済新聞ネット版 2014年1月18日
- 【解説】
- コンビニ内の一角を活用した本格的なコーヒーサービスへの人気はコンビニ各社も予想外だったようで、"ついで買い"も喚起して売上増に貢献した。コンビニ商品がかつての"常温・保冷食品主体"から、「熱い」「冷たい」「生」「良い匂い」など五感に訴える商品の拡充が進み、これがヒットに繋がっている。おでんのヒットもその一環、と日経トレンディでは分析している。
- <事例3>「ファッションセンター しまむら」
- 郊外型衣料専門店「しまむら」はベビー用品、紳士用品も扱うが、主力ターゲットは20代から50代の主婦層。"シマラー"と呼ばれるファン層も産んだ。多品種少量生産を徹底し圧倒的な低価格で伸長し続けている。平成25年2月期連結売上は4,911億円、経常利益475億円。店舗数は全国1800店を超え、仕入・物流・販売まで一貫した低コストを追求。これをわずか約2,300名の社員で運営する(パート比率は80%を超える)。店舗はドミナント方式(地域約8000世帯を1エリアとして定義)で、ユニクロなどとは一線を画し郊外から都市部へと浸透する戦術を採る。店舗も300坪の標準型が基本。低コスト・商品高回転率経営のモデルとされる
- 参考:http://www.shimamura.gr.jp/finance/results/
- 【解説】
- しまむらとユニクロとの差別化の特徴として、SPA(製造小売)対全量買い取り/完全売り切り、少品種大量対多品種少量、商品を店頭に並べるまでのスピード、などが挙げられるが、しまむらの強さの源泉はローコストオペレーションを徹底するビジネスプロセスや情報システムの細かな改善の積み重ねと人事管理にある。パート社員のモチベーション向上にも配慮しつつ、改善提案を積極的に奨励している。その数は毎月3千件にものぼり、こうした継続的かつ小さな改善の積み重ねがローコストと高効率経営を実現し、競合の追従を許さない強みとなっている。
- 参考:http://www.j-cast.com/2010/08/18073352.html?p=1
- *注3:
- ブルー・オーシャン戦略
- INSEAD(フランスのフォンテンブローおよびシンガポールにキャンパスを持つ世界トップクラスのビジネススクール・大学院)の教授であるW・チャン・キム 、 レネ・モボルニュが共著『ブルー・オーシャン戦略――競争のない世界を創造する』の中で主張した、競争の激しい既存市場「レッド・オーシャン(赤い海、血で血を洗う競争の激しい領域)」を避け、競争のない未開拓市場である「ブルー・オーシャン(青い海、競合相手のいない領域)」を切り開くべきだとする経営論。顧客にとってあまり重要ではない機能を「減らす」「取り除く」ことによって、企業と顧客の両方に対する価値を向上させる「バリューイノベーション」が必要だとしている。そのための具体的な分析ツールとして、「戦略キャンバス」などを提示している。(Wikipediaより引用)
- *注4:
- "イノベーションは組織全体で取り組むべき・・"については、"The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving As Fast As Your Business" Rita Gunther McGrath Alex Gourlayによる。
筆者は「競争優位を確保した瞬間からその優位が崩れ始める。今の時代には、競争優位を確保し続けることは幻想にすぎない。」とし、そのため業種を超えて"アリーナ"という概念で自社の陣地拡大を目指すべきで、それには"イノベーションの重要性"を個別の製品・サービスのレベルではなく、企業戦略の中心に位置付けなければならないとする。事例として米国コダック社と日本の富士フイルムが対照的に論評されている。 - 参考:【書評】「競争戦略の終わり」The End of Competitive Advantage
- *注5:
- 複雑性や変化が加速する世界に組織がどのように適応しているかを研究したMITスローン校のP.センゲが、その代表的著作『最強組織の法則』(The Fifth Discipline)で主張した組織論。この結果「学習する組織」という理論が世界に拡散した。
参考:「学習する組織 ピーター・センゲ」Diamond Online
(3)まとめ
巷間には様々な戦略論が溢れています。しかし、成功事例を見ると"戦略ありき"とは限らないことがわかります。その場その場で適切な意思決定(判断)と努力を重ねた結果といえます。
今回様々な事例を見てきました。かつては競合を出し抜くような戦略や戦術が一世を風靡しましたが、競合を含めた事業関係者間の力関係よりは、企業が本来持ち合せている能力(ケイパビリティ)から戦略をスタートさせる理論(RBV:リソースベーストビュー)に置き換わった感があります。そして今は、イノベーションの重要性が再認識されています。イノベーションは新たな顧客価値を生み出す源泉です。イノベーションはそれを生み出す一人ひとりの主観的バリューが根底にあり、それを合意形成していくための組織が戦略以上に重要である、という主張もあります。(野中郁次郎氏など)
現代はモノではなくコト(またはストーリー)で世界を作ることが重要であり、顧客との関係性の中で一貫性をもってユニークな価値を提供していく必要があります。それが変化しやすい環境に適応する競合優位性に繋がります。そのためにも組織的に知識を修得する能力が必要になると考えられます。
<<コラム>>競争戦略論について
(1) ポーターの3つの競争基本戦略
競争優位のための戦略では、M.ポーターの確立した3つの戦略と5つの競争要因を無視することはできません。
3つの戦略とは
- コスト・リーダーシップ戦略(規模を拡大して価格の主導権を握る)
- 差別化戦略(4Pで非価格競争)
- 集中化戦略(商品絞り込み、顧客絞り込み、地域絞り込み)
「コスト・リーダーシップ戦略」は、経済学で示される「経験曲線効果」(経験を蓄積することによりコストが削減される)に基づき大量生産と大量販売によってコストを引き下げ、その結果として商品価格を引き下げることによって競争に対抗すると言う戦略、「差別化戦略」は文字通り「商品特性」、「流通政策」、「プロモーション(広報・宣伝・販売促進策)」などで競合他社とは異なる特色化を進めることにより「非価格競争」を仕向け、優位を確立する戦略、そして「集中化戦略」は特定の購買者や特定の市場など(特定セグメントという)へ自社の資源を集中させ、そこで業界平均を上回る収益を得ようとする戦略です。以下にポーター戦略の概念図を示します。
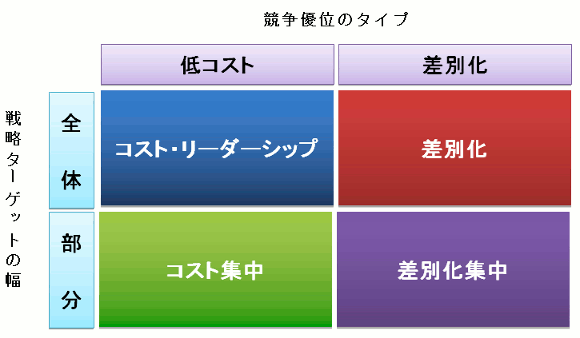
図14 ポーター3つの基本戦略
出典:『競争の戦略』M.E.Porter(1989)
この3つの戦略の原則を一つも満たしていなければ厳しい競争に巻き込まれて利益を得ることは難しく、一方、同時に複数の戦略を追求することも困難であると説きます。なぜなら、このどれもが満たせないとすれば市場での一貫性が保たれず、特に成熟市場ではリソースに配分に破綻をきたし競合に足元をすくわれる、というものです。日本企業はかつて「良い製品を安く提供」して先進国で圧倒的優位を築きましたが、その後新興工業国の追い上げを受けて圧倒的低コストの前に長期間苦心することになりました。
(2)ポーターの5つの競争要因(5フォース)
5つの競争要因もM.ポーターの主張した競合環境における重要な概念です。これは5フォースとも呼ばれ、「競合(敵対関係)」・「供給業者(の交渉力)」・「顧客(の交渉力)」・「新規参入者(の脅威)」・「代替品(出現の脅威)」の5つを指し、そのうちどれか一つでも力が強まると競合環境に重大な悪影響を及ぼすというものです。業界内の競合環境を地社との対比において分析する際に有効な手法です。
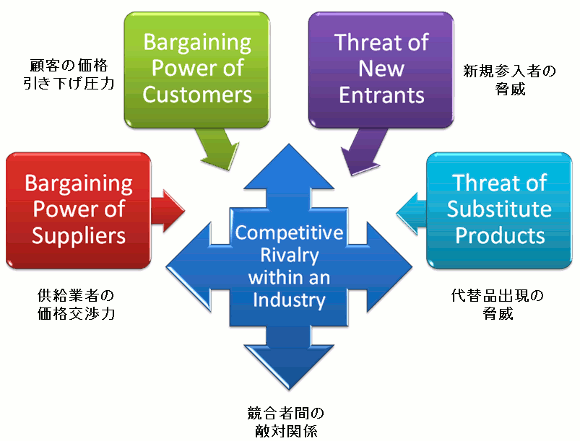
図15 ポーター5つの競争要因
出典:Wikipedia マイケル・ポーター
(3)ポーター理論への批判
ポーターの理論は今でも有効であり、研究し実践の余地があるとする意見も多くありますが、
(1)顧客の視点が一切含まれていないこと
(2)自社対競合などの、自社以外の存在との関係性を重視するが、企業自身の内部的特性や潜在的強み(後にコア・コンピータンス理論に繋がる)を一切考慮されないこと
などが批判の対象となりました。今では、5フォースの相互が絶対的な対立者という関係を超えて企業間コラボレーション、業務提携、アライアンスが盛んになっており、かつての競合者同士が協調する例も増えてきました*6。
従って、M.ポーターが5フォースを想定した時代とはかなり世界の様相が変わってきたことは確かなようです。
- *注6:
- 現在は業界内で相互に得意分野を補完する協調政策(相互補完)や、業界を超えた(ベンダーと顧客の関係から互恵パートナーとして提携する場合など)アライアンス契約を結ぶ例が増加している。また、国境を越えたEMS(Electronics Manufacturing Service:電子機器の受託生産)活用などのいわゆる製造アウトソーシングも発達し、自社内完結型ビジネスモデルの優位性が崩れてきた。
- <事例1>日本電気とHPとの協業
- 日本電気とヒューレット・パッカードカンパニー(HP)は2013年7月、エンタープライズ領域における戦略的なグローバル・アライアンスを拡張することを発表した。
- http://www.rbbtoday.com/article/2013/07/22/110123.html
- <事例2>大日本印刷と日本ユニシス、異業種提携で新規ビジネスを創出
- 大日本印刷と日本ユニシスは2013年1月、新規市場拡大を図るために「マーケティングプラットフォームの共同開発」など4つの領域で提携することを発表した。
業界の枠を超える成功事例(富士フイルム・オリンパス多角化戦略の成功など)が増えるにつれ、新たな戦略の枠組みを提唱する例が増えていきました。
(4)コトラーの競争地位戦略略
市場における競合する各企業の位置付けに関する理論としてはコトラーの「競争地位戦略」が有名です。これは競合者の集合は「リーダー」/「チャレンジャー」/「ニッチャー」/「フォロワー」の4つに分けられるとし、それぞれが取りうる戦略と原則が存在することを明らかにしました。
「リーダー」は業界内のトップ企業、「チャレンジャー」は第2位か第3位でトップの位置を狙う企業、「フォロワー」は業界内のシェアが低い追随者、「ニッチャー」は業界内のシェアは低いものの、上位企業に追随するのではなく、独自の市場を切り取って(特定市場:サブ市場ともいう)そこだけで「リーダー」を志向する企業です*7。
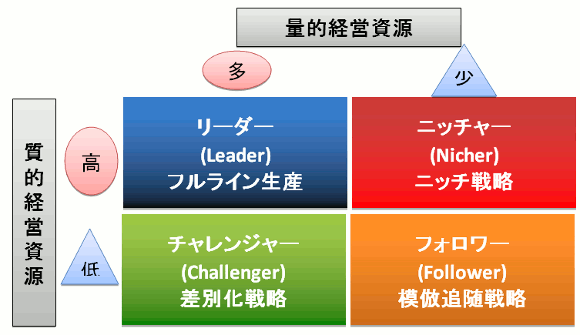
図16 コトラーの競争地位戦略
出典:「マーケティングWiki」~ マーケティング用語集
- *注7:
- 例としては、フォロワーは製薬業界のジェネリック医薬品専業メーカーがこれにあたる。ニッチャーであれば電器製品業界におけるダイソンや日本におけるフィリップス、高級オーディオ機器メーカーなどが該当する。
◆グローバル市場で新たな顧客獲得競争に勝ち残るためのグローバルマーケティング
(1)グローバルマーケティングとは
グローバルマーケティングという言葉は1990年代になって産まれたと言われています。それまでは多国籍企業で実施されているマーケティングが国際マーケティングと呼ばれ、国境を越えて存立させた海外子会社(R&D、生産、物流、販売会社など)を組織化し原材料の調達と生産のコスト低減、効率的な物流、大量消費地などを勘案してコントロールする中に位置付けられていました。20年ほど前から爆発的に普及したインターネットによる情報のグローバル化と世界的な規制緩和により様々な業種で国境を超えるブランドが急激に拡大し、大企業だけでなく中小企業もグローバルマーケティングを志向するようになりました。コンシューマ向けEC(ネットショッピング)の拡大もこれに大きく寄与しています。
グローバルマーケティングは文字通りマーケティングを海外で展開することですが、3Cや4Pを考慮するだけでも世界各地に偏在する市場の特性や競合環境、自社の位置付け、さらに製品種類、調達、品質、量、物流ルート、販売価格と原価、広報宣伝方法など数多くの戦術要素を組み合せる必要があります。国内で培ったマーケティングノウハウを活かせるとしても、格段にリサーチ量やオペレーション負荷が増加し意思決定が難しくなることはご想像頂けるでしょう。
こうした世界に点在する数々のリソースを海外の国々の市場に合わせて最も効果的、効率的にマネジメントすること、それがグローバルマーケティングなのです。
(2)日本企業のグローバルマーケティング
日本企業の海外進出は電機・機械、自動車関連、精密、食品など多岐にわたりますが、戦前の蚕糸を中心とする繊維輸出勃興期を経て本格的に海外進出が盛んになったのは第二次大戦後です。当初は国内で生産した製品を、海外販社や現地パートナーを通じて輸出することが主体でした(これを輸出マーケティングといいます)。その後海外に工場を建設して現地の市場拡大を目指す動きが進展しました。(例:トヨタの最初の海外工場設立は1959年ブラジル)
日本の海外マーケティングは、先ずは付加価値の高い製品を機能優位性を前面に海外市場へ投入する性格が強かったため、現地の事情に合わせた広報などのマーケティング的考慮はあまりされていませんでした。
ただ、古くは味の素(1910年には当時日本領だった台湾などに進出)やキッコーマン(1905年に朝鮮半島に工場を設立:1967年に米国で生産開始)のように古くから現地化を開始して深く根付き、今にいたっている企業もあります。
現在はコンビニや即席麺など日本で培われたビジネスモデルや商材が海外で受け容れられ、国際的な競合を勝ち抜きつつある企業も増えてきました。一方、国境を超えたM&Aが盛んになり*8、名実ともに古くから存在する欧米多国籍企業と伍してグローバル競争の只中に躍り出る企業が増加しています。現在の日本ではグローバルマーケティングが緒についたところといえます。
- *注8:
- 最近の主な大型海外M&A事例
- サントリーによるオランジーナ・シュウェップス買収(2009年 3000億円)
- アサヒHDによるインデペンデント・リカーグループ(ニュージーランド)買収(2011年 976億円)
- 損保ジャパンによる英キャノビアス買収(2011年 992億円)
- 武田薬品工業によるナイコメッド(スイス)買収 (2011年 1兆円)
- ソフトバンクによるスプリント・ネクステル買収 (2013年1兆8000億円)
- ソフトバンクによる米ブライトスター買収(2013年 1234億円)
- LIXILによるGROHE(グローエ)買収(2013年 3800億円)
- 東レによる米ゾルテック社、韓ウンジンケミカル買収(2013年総額1000億円)
- キリンHDによる一連の海外M&A:ナショナルフーズ、デアリ―・ファーマーズ、ライオンネイサン、サンミゲル、不フレイザー&ニーブ、スキンカリオールなど(総額1兆2000億円)
- サントリーによる米ビーム社買収(2014年 1兆2500億円)
(3)グローバルマーケティングの課題
本連載第5回「マーケティングが求められる背景」【グローバル化への腰が重い日本企業】で示したように、日本企業はマーケティングを語る以前に"グローバル化"が不得手のようです。
以下に一般的に挙げられている課題を幾つかの事象を交えて整理しましょう。
・国々の事情を考慮したオペレーション:
文化、制度、慣習、宗教、商習慣などにより人々の情報の受け止め方や感性が異なるのは当然です。法律も様々で日本国内と同様に振る舞うことはできません。為替の影響も受けます。また、競合企業も名うてのNB(ナショナルブランド)や地場ローカルの企業など様々です。競合製品の特徴・商圏分布、シェア構成(寡占状態か群雄割拠状態かなど)も異なります。
- <事例4>「グリコポッキーの現地化」
- グリコのポッキーは世界約30カ国で販売されている人気商品だが、ヨーロッパでは別の意味の言葉が存在するため「MIKADO」に商品名を変えている。イスラム圏ではタブーである豚肉'pork'に語呂が近いことから「Rocky」(ロッキー)に変えている。中国では「百奇」と表示し、烏龍茶味、ライチ味など中国限定のバリエーションを加えている。タイなど暑い国では融ける温度が高いチョコレートを使う。
<参考>「ポッキーのグローバル展開」
<参考>「現地化をどう組み立てるか」
・製造環境と物流の最適化:
製品を海外で展開する場合、自国から輸出するのか、海外他拠点工場から輸送するのか、進出国に製造拠点を設けるのか、コア部品だけ供給するのか。またそれぞれの場合により配送ルートをどのように確保するのか、現地事業者と提携することができるのか、または販路をM&Aで確保するのか。海外展開で採りうるオプションは千差万別です。要するにSCMが決定的に重要になるのです。これは大きな投資が伴うことでもあり、慎重な調査と予測が必要な事業戦略から緻密に検討し組み立てる必要があります。また、どの製品群を展開するのか、当初は絞り込みが欠かせません。国内ならフルラインで販売できているとしても、進出国では当初はセグメントやターゲットを絞って慎重に始めることが普通です。
- <事例5>「中国市場で明暗を分けた花王とレブロン 販売網とネームミングのどちらが重要か」
- 「露華濃(Luhuanong)」という素晴らしいブランド名を冠したレブロン。この名は楊貴妃の美貌を謳う李白の詩に由来するのだ。一方、花王は1998年から長らく赤字に苦戦してきた。
しかし、中国から撤退を決断したのはレブロンだった。世界市場の2%しか得られなかったのである。花王は2015年ようやく黒字化する見込みが出てきた。明暗を分けたのは「物流」だった。
出典:http://diamond.jp/articles/-/47917 - <参考>「グローバルマーケティングは4PのPLACEから始まる」
- 日本企業が海外進出で良く失敗するケースは、チャネル構築に失敗するためだと言う。その原因は営業とチャネル構築の区別がつかないまま海外進出することにある。チャネル構築はアーキテクチャであり、プロが必要。そして適切な現地パートナーと組むことが成功の条件である。
出典:「日本企業はチャネル構築を強化せよ」Innoovations-i(フジサンケイビジネスアイ)
・現地浸透の困難さ:
マーケティングは市場や顧客とのコミュニケーションが基本なので、現地でマーケティングを展開するには(現地でモノを販売するには)現地の市場や文化を良く知る人材を確保することが必要です。ここで重要なのは現地で販売するカテゴリーの"売らんかな志向"に流されることなく、企業の成り立ちと歴史、ポリシー、そして提供しようとしている製品やサービスの価値を十分理解してもらうことが鍵になります。そして、なぜこの国ではこのような製品展開なのか、その国ではどのようなマーケティング戦略を立案し、その理由は何なのかを上から目線ではなく、現地担当者(できれば消費者も含めて)対等に良く話し合って決めていくことです。
- <事例6>「モバイル決済サービス「スクエア(米)」の日本上陸」
- 米国のモバイル決済サービス会社「スクエア」が日本進出の際、CEOのJ.ドーシー(米Twitter共同創業者)が関係社員に課したことは、日本人の文化や感性を理解させることだった。そのために採った方法は「わび・さび」の本を読ませることだった。「わび・さび」の文化が、デザイン・内的存在・外部世界を融合した素晴らしいコンセプトであると評価し、日本人の美意識とテクノロジー進化の受容性の両方を理解させようとした。
出典:「スクエアCFOサラ・フライアーに聞く、同社の強みと日本市場」DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー ブログ(2013/10/02)
- <事例7>「ヤマハ発動機のグローバルWEBサイトの構築」
- バイクを主力とするヤマハ発動機の海外売上比率は約90%である。2011年に世界のWEBサイトをリニューアルしようとして調査した。すると当時すでに130ものサイトがあり、各国バラバラで手が付けられなかった。国によって販売する商品が異なり、ブランドイメージも違っていた。WEB戦略を組み直し目標KPIを作った。海外のWEB担当者と何度も話し合い、本社はグローバルサイトを制作し、海外は現地に任せ本社が必要なサポートをする体制にした。本社では企業ビジョンも設定、グローバルサイトでは創業以来の製品15,000点の写真を公開することにした。こうしたサイトは本社でなければ作れない。ブランドを訴求するショートムービーも制作した。社員でも知らなかった情報もあり、この成果は海外子会社から大いに感謝された。
出典:『日本企業のガバナンス形態に合わせたグローバルWeb戦略』(ネットPR Day2014:News2u主催 2014.1.21)
参考:「ヤマハ発動機 グローバルサイト」プロダクトライブラリー
・かつての日本型成功体験へのこだわり:
日本は高度経済成長期(1955年から1973年まで)からオイルショックを挟んで安定成長期(1973年から1991年まで)を経てバブル崩壊するまでの約40年間、紆余曲折はありましたが欧米から"Japanese Miracle"と称される長い右肩上がりの成長を歩んできました。産業界や企業の隅々まで"永遠に成長するはず"と信じて疑わなかったかのように努力してきたのです。その後環境が一変しても急にハンドルを切ることは難しく、意識するしないにかかわらずかつての成功体験に基づく意思決定をする以外の術を持ち合わせませんでした。海外市場においても、こうした志向を見直すことがかなり遅れたと言わざるをえません。
- <参考>海外進出で成功する理由・失敗する理由
- 海外進出で失敗する理由は数々あるが、ここでは「資金不足」「日本流オペレーション」「事前準備不足」の3点が挙げられている。
海外進出ナビ - <参考>「過去の成功体験を捨て去ることが新たなイノベーションを生む」
- セブン&アイHLDGS CEO兼会長 鈴木敏文 早稲田大学ビジネススクール教授 内田和成(対談)
- <事例8>「ガンホー社長が明かした"パズドラ"ヒットの舞台裏」
- 「ゲーム制作には破壊と創造が大事。僕はパズドラという文化を壊していきたい。いつまでも成功体験にこだわっていては、それを超えるものが生み出せずに失敗する。」
- <参考>「コカ・コーラのようなマーケティングが日本でできない理由」
- このコラムでNeo@Ogilvy(ネオ・アット・オグルヴィ)でチーフ・マーケティング・プロデューサーの山崎氏は「日本企業は、良いモノを作れば売れるという成功体験が長かったため、いつまでも「機能」と「価格」でしか勝負できない」と指摘している。
以上の4点は様々なところで指摘されている課題です。グローバルマーケティングの課題であると共に、グローバルビジネスへの日本企業の課題、と置き換えることもできるでしょう。前述のように欧米のNBと比較すると、日本企業は海外ビジネスの歴史が浅いこと、そして起業時から海外展開することを当然のように成長した米国IT企業などとは経験も成り立ちも異なります。言語の壁は今でも大きいものがあります。海外での事前調査や事前準備の大切さ、ゼロベースで現地事情を鑑みた戦略立案の重要性、そして現地市場、ターゲット顧客層、現地拠点スタッフやパートナーの思いを理解することの重要性を強く感じます。
(4)グローバル化成功への条件
それではグローバルマーケティング成功への条件は何なのでしょうか?
例えば、三井物産戦略研究所のレポート(注:日本の食品産業を対象としている)では、「海外進出に成功した企業の共通要因」として以下の三つを挙げています。
- ・訴求力ある独自製品を持つ
- 進出先の国に存在しないかまたは低品質品しか普及していない場合に訴求力ある独自製品(他国で実績ある普遍的な価値あるキラー商品)を展開できれば成功の確率は高まる。
(例:ネスレのインスタントコーヒーと粉ミルク、コカ・コーラのコーラ、ダノンのヨーグルト、ハインツのケチャップ) - ・価値とコンセプトを伝える
- 進出先に今まで存在しなかった商品は消費者の馴染みが無く、浸透させることは極めて困難である。プロモーションやチャネル構築も重要であるが、最大のポイントは時間が掛かることを見越して地道な努力を続けることである。(例:味の素は新興国で近代的な流通が未発達であった中、一軒一軒の個人商店や小売事業者を訪ね歩き、UMAMIを浸透させていった。ヤクルトは現地浸透に苦労していたが日本型のヤクルトレディの採用・研修から開始し対面販売による浸透策で成功した。)
- ・先駆者利益を守る
- 現地市場への浸透がある程度進むと競合が追随する。ここで先駆者利益をいかに守るかが重要になる。よく採られる方法は、製品またはコア部分のブラックボックス化である(例:コカ・コーラは製造原料が厳密に秘匿されている)。しかし、現地生産を継続したり特許戦略を実施してもいずれは模倣されたり特許が切れたりする。そのため、先駆者としての知名度とシェアを活用し新たな新製品や独自商品を進化させ続けることがポイントとなる。
また同レポートでは、食品業界の世界売上上位50社のうち、ベスト20社には日本企業が4社しかランクされていないこと(キリン・サントリー・アサヒ・味の素)(注8参照:ビール会社3社がランキングされているのは、ここ数年の間に海外M&Aが盛んに進められたことによる)、さらに海外企業の平均利益率が12%に対し、日本企業の利益率は4%に過ぎない問題点を指摘しています。
これは海外における日本企業のマーケティング能力が低いことが一因かもしれませんが、確証は存在せず、別途検証が必要な課題です。(日本企業の海外での利益率が異常に低いことは第5回 参考「立ち遅れたBtoBマーケティングがようやく動きだす」参照)
出典:『世界進出を目指す日本食品産業』(三井物産戦略研究所レポート)
以下、さらに幾つか成功事例と提言を見ていきます。
- <事例9>『メキシコで食文化をも変革させたサンヨー食品』
- メキシコの即席麺市場が拡大しており、その85%のシェアを誇るのが東洋水産のMaruchan(マルちゃん)ブランドである。海外展開に成功したMaruchanは、あたかも現地で生まれた食品であるかのように、日常の食生活に深く溶け込んでいる。メキシコでは「マルちゃん」は単に食品としての普及のレベルを超え「簡単にできる」「すぐできる」という意味の言葉として浸透している。
- 出典:グローカライズで世界に羽ばたく即席麺
- <事例10>『インドで成功したスズキに先見の明はなかった』
- 1981年にインドに進出してシェアNo.1となり確固たる地位を築いたスズキ。「良く"スズキさんは先見の明があって素晴らしい"と言われるが、そんなものはなかった。本当は我々も先進国に進出したかったのだが、それは叶わなかった。やむをえず誘われてついて行った先がインドだった。」と鈴木修会長が語った。
- 出典:Tech-On 「日経ものづくり」スズキのインド進出のエピソード
- <事例11>『値下げなし、中国高級ブランド街で人気を博す良品計画』
- 香港から進出した「無印良品」。徹底した定価販売でディスカウントやセールを一切行わない代わりに、徹底した顧客視点でのビジュアルマーチャンダイジング(VMD:見やすく、選びやすく、買いやすく)でブランドを育てた。
- <参考>「100店舗到達、「無印良品」が中国で快走」
- <事例12>『キッコーマン老舗企業の挑戦』
- 1955年(昭和30年)には醤油の国内消費が落ち始めて危機感を持ち、1957年にアメリカに進出した。しかし5年経っても赤字のまま。1961年にアメリカ留学を終えた茂木友三郎(現会長)は、アメリカでのビジネスには現地に工場を作るしかないと考えた。そこで立てたマーケティング戦略は、和食などでは無く"肉のレシピに絞ること"だった。
- http://katamuki.acenumber.com/2013/04/nagano-miso-bankrupt-and-kikkoman-success.html
- <事例13>『東レが炭素繊維を米ボーイング採用に漕ぎつけるまでの長い道のり』
- 東レが炭素繊維をボーイングへ売り込むためには航空産業を監督する米国のFAA(連邦航空局:Federal Aviation Administration)をクリアする必要があった。そこで、米UCC(Union Carbide Corporation)社とアライアンスを組むことにした。この契約が締結されたのは1970年のことだった。時間はかかったが、このアライアンスは現在の大きな成功をもたらした。
- 出典:「第15回 生産財グローバル・マーケティングのケーススタディ ~東レ・炭素繊維事業~」Nuture Networks
- <提言>『グローバルマーケティングのポイントは「スピード」「現地適合化」「チャネル」』
- 明治大学経営学部の大石教授は、グローバルマーケティングは商品やサービスに適した都市を選び3つのポイントを実践することだと語る。
- 出典:ADV(朝日新聞社広告局ウエブサイト)
以上幾つかの海外マーケティング事例と提言を見てきました。そこで以下の3つを"グローバルマーケティング成功の条件"に追加させていただきたいと思います。
- ・技術信仰を捨てる:
- 日本の技術や品質は世界有数であり(実際その通りであることも多い)、海外市場ではそのサブセットを組み合わせれば足りる、という思い込みが言わば"製品価値の上から目線"を醸し出してしまいます。それは"良いモノを作れば売れる"というかつてのモノ作り信仰に由来します。昔はそれで良かったのですが、今では通用しなくなったのは誰もが知ることとなりました。他に成功体験を持ち合わせていないために無意識のうちにそれが思考の起点になってしまいます。
- <参考>『第5回 インフラ海外展開推進のための有識者懇談会』平成24年11月11日 国土交通省
- "インフラの海外展開に当たっては、日本の良さを押し出すことも重要だが、上から目線ではなく、相手国の地域情勢や文化を大切にすることも必要"
- <参考>『日系企業のグローバル化に関する共同研究(要約版)』(PWC Japanと慶応義塾大学大学院の共同研究 2013年)
- 「・・日本本社の目線で技術や品質の高さを訴求した進出を図っても、新興国市場ではそのターゲットが限定されることとなり、結果的には「ハイエンド顧客と日本から進出した企業」しか相手にできないニッチプレイヤーに留まる。ニッチプレイヤーである限りにおいては「日本式経営の輸出」で良いとしても、マスマーケットの取り込みには至らない・・」
- ・販売志向からの脱却:
- 日本から海外へ行くと、"売り込む"という観念が強過ぎるために、無意識のうちに機能や性能で説明を始めてしまうという話を聞きます。それが現地で受け入れられるかどうかは分からないことは頭では理解していても行動が伴わず、また相手国の顧客の立場になって考えることに慣れていないため、どう行動し判断すべきかわからなくなるのです。
- <事例14>『タイにおけるハイアール事例』
- 中国家電大手のハイアールのCEO趙氏が回想する。"タイの冷蔵庫工場が三洋電機だった頃、新製品は年に一機種のみ。採算は赤字だった。管理職は日本人だったが工員との間に壁があり工場に活気はあまりなかった。ハイアールが買収した。権限を委譲し、技術者に店頭に行けと命じ、直接客と対話をさせた。市場は常に変わる。だから我々は変わりやすい顧客に常に接していく必要がある。新製品の頻度は6倍にした。するとたちどころに黒字になった。"
(出典)島耕作アジア立志伝(NHK BS1 2014.1.9再放送) - <参考>「ハイアールの行うイノベーションの目的は顧客に価値をスピーディーに提供すること」
(アジア・ビジネス研究分野 大阪市立大学大学院 2006ワークショップ講演録) - 中国の田舎の農民は洗濯機でサツマイモを洗っていた。そのため故障が頻発した。泥や根が排水ホースに詰まり、水が流れなくなってしまうからだった。このクレームが本社に届いてから24時間で技術陣はサツマイモが洗える洗濯機を開発した。ホースを太くし、ふたを大きくしたのだ。この洗濯機は中国の田舎でヒット商品となった。
- ・ブランディング:
- ブランドは企業の見えない価値を表出します。それは支持してくれる顧客の作り上げたイメージを象徴する存在であり、企業の提供する製品やサービスに伴う良い経験や共感、信頼を長い時間をかけて育て上げた果実とも言えるものです。これは価格や機能に優先するべきものであり、時として価格以上の価値をもたらします。機能優先で価値を訴求し続けてきた日本企業には不得意科目なのです。
(ブランド構築の重要性については次回解説します。)
(5)まとめ
グローバルマーケティングのための活動は、結局は"進出先を理解するための活動"である、と言い換えても良いかもしれません。進出先を理解することこそが日本人に限らず異郷の地でビジネスを進める第一歩であるはずです。次回詳述しますが、現代は"(個々の)顧客の共感を価値とするマーケティング"が世界的な主流になりつつあります。グローバルマーケティングでもそれは同様です。"グローバル市場で勝ち残る"とは、機能的優位性よりも海外顧客の心の中でどれほど強い愛着を獲得できるか?という争いに勝つことへ移っています。海外でももはや「プロダクトアウト思考」のマーケティングでは受け容れられなくなっています。
次回は『ブランドマーケティング』と『顧客経験価値マーケティング』を取り上げます。
参考文献:
| * | 『競争優位の戦略 ―いかに高業績を持続させるか』M.E.ポーター ダイヤモンド社 (1985) |
| * | 『新訂 競争の戦略』M.E.ポーター ダイヤモンド社 (1995) |
| * | 『マーケティング・マネジメント』(各版)P.コトラー ダイヤモンド社 |
| * | 『ブルー・オーシャン戦略―競争のない世界を創造する』W・チャン・キム, レネ・モボルニュ (著), ダイヤモンド社 (2013/5/17) |
| * | The End of Competitive Advantage: How to Keep Your Strategy Moving As Fast As Your Business Rita Gunther McGrath Alex Gourlay Harvard Business School Press 2013-06-04 |
| * | 『最強組織の法則』ピーター・M. センゲ 著/守部 信之 訳 徳間書店(1995:原著作は1990) |
| * | 『知識創造企業』野中郁次郎/竹内弘高 著 東洋経済新報社 (1996) |
| * | 『ストーリーとしての競争戦略 ―優れた戦略の条件』楠木健著 東洋経済新報社 (2010/4/23) |
| * | 『良い戦略、悪い戦略』リチャード・P・ルメルト 日本経済新聞出版社(2012) |
| * | 『コア・コンピータンス経営 未来への競争戦略』G.ハメル/C.ブラハード 日本経済新聞社(2001) |
| * | 『企業戦略論【上】基本編 競争優位の構築と持続』J.B.バーニー ダイヤモンド社(2003) |
| * | 『BtoBマーケティング』余田拓郎 東洋経済新報社 (2011) |
| * | 『失敗の本質 ―日本軍の組織論的研究』戸部良一/野中郁次郎ほか ダイヤモンド社 (1984) |
*本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。
『WEBマガジン』に関しては下記よりお気軽にお問い合わせください。