
エネルギーインフラを支える
大規模情報システム変革の裏側
OGシステム開発本部 コーポレートシステム部 第四チーム リーダー
工学部 出身
R.N
プロフィール
テクノロジーの活用なくして企業の成長はないと確信し、IT業界を志す。強固な事業基盤がありながら競合他社に勝てる魅力と実績がある点などに惹かれ、2008年オージス総研に入社。現在、Daigasグループ向けに、購買システムのSaaS利用化推進を担当している。

これまでのキャリアと仕事内容
-
- 入社1年目
(2008年〜) -
- 大阪ガス向けバックオフィスシステムの維持管理
- 配属後すぐ、大阪ガス向けに開発されたバックオフィスシステムの維持管理に携わる副担当に。先輩のサポートを受けながら、小規模システム改善案件のプロジェクトマネジャーなどを経験。お客さまや協力会社との仕様調整のほか、設計・テストなどの業務に携わる。
- 入社1年目
-
- 入社3年目
(2010年〜) -
- バックオフィスシステムの維持管理とオフショア開発プロジェクト
- バックオフィスシステムの維持管理の副担当から主担当へ。さらにプロジェクトマネジャーとして上海のオフショア開発チームを動かしながら担当するシステムの改善開発をリードするなど、入社1年目と比較して裁量範囲が大幅に広がる。
- 入社3年目
-
- 入社13年目
(2020年〜) -
- ガス自由化に伴う購買システムの分割プロジェクト
- ガス自由化に伴う法規制の変更により、購買システムを5社に分割する案件のチームリーダーを任される。法的に対応すべき期日が迫るなか、システム分割を成し遂げるため、要件の絞り込みや進捗管理、リスク対策を強く意識しながらプロジェクトを推進した。
- 入社13年目
-
- 入社17年目
(2024年〜) -
- 購買システムのSaaS移行プロジェクト
- 購買システムのSaaS移行計画に伴い、プロジェクトリーダーとしてシステム利用者の意向の取りまとめや、導入候補となるSaaS製品の絞り込みなどを担当。現在は選定したSaaSベンダーと協力しながら、導入に向けた最終調整に携わっている。
- 入社17年目
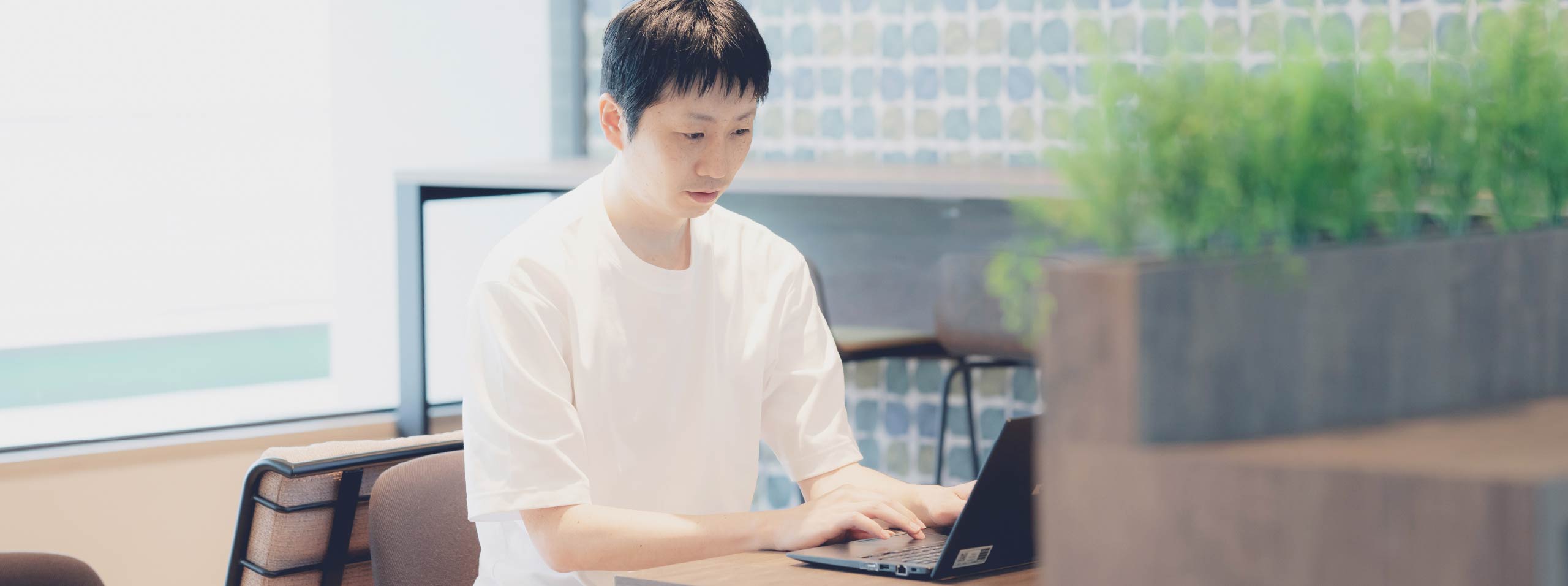
CHAPTER 01
限られた期間で挑んだガス自由化に伴う、
購買システムの分割プロジェクト
2020年に携わったガス自由化に伴う購買システムの分割プロジェクトは、とても印象に残っています。「ガス自由化」とは、2017年にはじまった都市ガス事業者を消費者が自由に選べる制度で、この新制度により関西エリアのガス供給を担っていた大阪ガスは5つの事業会社に再編されることになりました。会社が分割されれば、当然業務システムも分ける必要があります。大阪ガスが利用していた購買システムを、新設された4つの事業会社でも利用できるようにすることが本プロジェクトのゴールでした。
幸い入社直後から大阪ガスの購買システムの維持管理に携わってきたこともあり、システムの仕組みや状況は理解していましたが、事業会社特有の要件もあり、導入は容易ではありません。プロジェクト開始時点では既成の業務パッケージソフトを各社に導入して対処する方針が定められていましたが、システム要件と業務要件のギャップを埋めるために割ける時間は限られており、現実的な選択ではないように思えました。
期日は法的に定められており、後ろにずらすことはできません。購買システムの開発が期日までに完成しなければ、新設された4つの事業会社の基幹業務に悪影響をおよぼすことになってしまいます。そのような状況のもと、計画が進むにつれ、既成の業務パッケージソフトでは大阪ガスの現行業務に合わず、業務を変えていただく必要がある点と、業務パッケージソフトにも多数のカスタマイズが必要である点が、判明していきました。ここで期日に間に合わないリスクと、運用開始時にスムーズに業務開始するのが難しいリスクに目を向け、「業務パッケージソフト導入開発ではなく、スクラッチ開発(※)に切り替える」という抜本的な方針転換を行いました。期日が迫るなかでの大きな方針転換ゆえに重圧はありましたが、確度の高い実現性の提供がお客さまのためになると考え、この意思決定を正解にすべくチーム一丸となって成功をめざしました。
※スクラッチ開発:ソフトウェアや情報システムを既存のプログラムやパッケージソフトを使わず、オーダーメイドでゼロから作り出す開発手法を指す。

CHAPTER 02
幅広く周囲の力を巻き込みながら
「価値」にこだわる姿勢が、
信頼と新たな期待を生み出す
事態を打開するために取り組んだのは、WANT機能(ほしい機能)とMUST機能(必須機能)の切り分けでした。当然、お客さまはできる限り機能を盛り込みたいと考えます。ただし、その全ての声に対応することが、お客さまの価値につながるとは限らないと考えています。お客さまが必要だと述べる機能の背景を丁寧にひもときながら、業務とのひもづきと重要性を整理していきました。時にはお客さまにとって耳が痛いような提案すらも提言することで、必要不可欠な機能を保有しつつ、将来的な拡張も可能な情報システムが実現できます。また、お客さまに納得いただくために、幅広く関係者を巻き込みながら進めていきました。開発チームが一丸になって向き合うことは勿論ながら、大阪ガスのDX企画部門の皆さまにも相談し、同じ目線のチームになれたことがプロジェクト推進の大きな鍵となったと振り返っています。大きな方針転換を正解にすべくお客さまに向き合った結果、プロジェクト序盤こそ苦労はあったものの、プロジェクト後半は順調に進行し、無事リリースすることができました。
そのような姿勢が信頼につながっているのか、お客さまからは「次のプロジェクトでは、あるべき要件や課題を私たちと一緒の目線で考えてほしい」「改めて業務とシステムのあるべき姿を議論し、一緒にSaaS製品を視野に入れた次の購買システムの製品選定してほしい」といった、1社のSIer/発注先業者の枠組みを超えた期待をいただいています。その期待を超える価値を生み出すために、より一層技術を磨いています。

CHAPTER 03
価値を生み出すことに、
誰よりも「誠実」であること
お客さまにとってオージス総研は、システム構築の依頼主・依頼先としての間柄というより、同じ視点に立つパートナーであると言っても過言ではないと考えています。当然、会社間、担当者間の信頼関係は何よりも重要です。相互理解と信頼関係構築のため、私が入社1年目から大切にしていることがあります。それは「誠実であること」です。「誠実であること」が大事だといっても、お客さまのご要望どおりのシステムをつくり上げればいいという意味ではありません。お客さまの言葉の背景や真意をしっかりくみ取り、拡張性や保守性、コストパフォーマンスを念頭に、本当に届ける価値を生み出す提言をすることまで含めて初めて「誠実」であると言えると思うからです。より良いシステムはどんなに伝えにくいことであっても、忌憚なく話し合える関係性と誠実な仕事ぶりから生まれる、私はそう信じています。
CHAPTER 04
挑戦を連鎖させ、エネルギーインフラを通じて、
新しい価値を社会に生み続けたい
Daigasグループは、エネルギー業界のなかでもDXへの取り組みが盛んな企業グループとして知られる存在です。今進めている購買システムのプロジェクトが一段落したら、新たなDaigasグループ各社の業務効率化や付加価値向上につながるプロジェクトに挑戦してほしい、とのお声をいただいています。私たちの挑戦により、Daigasグループがまた新たな挑戦ができる。そして、その先のお客さまや社会に新たな幸せを生み出すことができる。このように、挑戦を連鎖させ、新しい価値を社会に生み出していくことはオージス総研の仕事の醍醐味だと考えています。担当するプロジェクトを通じて豊かで便利な暮らしを実現できるよう、これからも最新技術の習得を怠らず成長していきたいと思います。
ある日のスケジュール
-
08:30
- 出社
- 基本は9時出社ですが、在宅勤務の日は8時からメールチェックをはじめ優先タスクを整理。
-
09:00
- 定例会議
- 毎週月曜に開催されるチーム定例会議に出席。進行中のプロジェクトの進捗状況を確認。
-
10:30
- お客さまと打合せ
- お客さまとSaaSベンダーを交えた次期購買システムの詳細について打合せを実施。
-
13:00
- 問い合わせ対応
- メンバーから届く相談事にチャットで返答。お客さまからの質問に直接お答えすることも。
-
15:00
- レビュー
- メンバーが作成したシステム要件書をレビューし改善点を伝達。
-
18:00
- 退勤
- 仕事を終え退勤。
※所属部署・役職・内容は取材当時のものです。
OTHER INTERVIEW
他の社員インタビューを見る




