人材育成は、企業にとって、最重要事項であることは、言を待たないが、こと「IT人材育成」となると、「大事なのは、わかっているけどね...」と言われながら、優先度の上がらない施策の代表選手だったと思われます。
しかし、「ITスキル標準(ITSS:IT Skill Standard)」と「情報システムユーザースキル標準(UISS:Users' Information Systems Skill Standards)」の2つのフレームワークが、今「IT人材育成」を脚光の浴びる施策に変えています。
ビジネスイノベーションセンターにおいては、ITSS/UISSを「ITガバナンスの下支えをする重要な取り組み」と考えておりますので、これから何度か、Webマガジンで取り上げる予定です。
今回は、ITSS/UISSの概要について、おさらいをしておきたいと思います。 【ITSSの誕生】
今から10年前の2000年11月27日に日本政府が、IT戦略会議にて打ち出したのが、「IT基本戦略」であり、その中では、4つの重点政策分野が掲げられました。 - 超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策
- 電子商取引ルールと新たな環境整備
- 電子政府の実現
- 人材育成の強化方針
これが、国家戦略としてのIT人材育成のスタートと言えましょう。
それを受けて、2002年4月に経済産業省が、ITサービス・プロフェッショナルの育成に関わる諸組織の有機的な連携を目指し、「ITスキル標準(ITSS:IT Skill Standard)」ベータ版を、同年12月に正式版を発表。翌2003年7月には、情報処理推進機構(IPA)内に「ITスキル標準センター」を設立しました。
その「ITスキル標準センター」の活動目的は、下記の2つに大別されます。 - ITSSと研修ロードマップを適宜改訂し、日々進展するITやビジネスの現状を常に反映した内容とすること。
- ITSSを広く知ってもらい、IT業界全体で有効に活用してもらうようにすること。
その出自の通り、ITSSは、ITサービス・プロフェッショナルの育成に関わる諸組織、つまりITベンダー・IT教育ベンダーなどITを生業にしている組織(以下、ITベンダーなどと表記。)が、それを活用することで、「IT基本戦略」に謳われている「すべての国民が情報技術(IT)を積極的に活用し、かつその恩恵を最大限に享受できる知識創発型社会の実現」に寄与するという理念の下で活用されるものと言えます。 【ITSSの普及】
前述の通り、ITSSは、「ITSSフレームワーク(図1)」を活用した人材育成の仕組みであり、ITベンダーなどが活用することを前提としたものです。 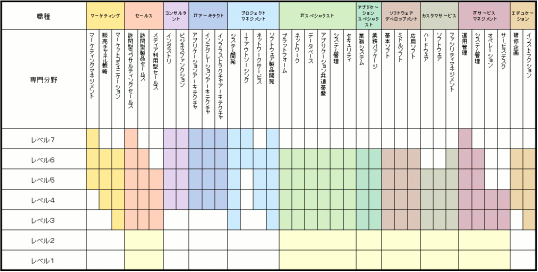
図 1 ITスキル標準V3 2008のキャリアフレームワーク
ITSSフレームワークとは、横軸に、11職種35専門分野のキャリアカテゴリーを定義し、縦軸にレベル1~7のスキルレベルを定義したものです。
11職種は、当然のことながら、IT関連サービスを「提供する側」の論理に立ったもので、そこに描かれるキャリアパスを11職種とハイレベル人材のマッピング状況からひも解くと、ITコンサルタント(ITサービスマネジャー含む)・ITアーキテクト・プロジェクトマネジャーを目指すようにも見えます。
このITSSフレームワークを見て、多くのITベンダーなどは、自社のIT技術者のマッピングを始めました。キャリアカテゴリーは、自社のビジネスドメインとの連携を考慮すると考えやすいのですが、スキルレベルについては、その客観性の確保に苦慮することになります。 (Tips)
ちなみにスキルレベルを簡略化して表現すると、
- エントリーレベル=上位者の助けが必要
- ミドルレベル=独力でできる
- ハイレベル=指導できる
となります。
上記の例示でも大まかなスキルレベルを把握できます。しかし、その判定結果は、
従来の人事考課と同様に上位者の評価によるところが実態でした。
|
そこで、2003年7月の「ITスキル標準センター」設立の半年後、2003年12月に、任意団体「スキル標準ユーザ協会」(現在は、特定非営利活動法人)が発足するなど、ITスキル診断をサービスとして提供するという団体あるいは、それをビジネスとするIT教育ベンダー/スキル標準診断業者が表れ始めました。
診断の客観性を担保する意味でも診断母数の多さは重要なポイントですが、開始当初は、数千のオーダーであった診断母数は、2006年4月に発表されたITSS改訂版V2が、ITベンダーなどに普及・定着してきたことも背景に、最近では、20万以上の母数を数えるサービスもあります。
このような普及状況を、わかりやすく例えるとITベンダーなど同一の業界で横の比較が可能になったと言えます。A社のITSSレベルは、平均X.XXで、ハイレベル人材の割合は、XX%で、B社を上回る/下回る等という会話が成立してしまうことになるのです。【ユーザ企業もITSS?】
一方で、ユーザ企業に所属するIT人材の育成についても、ITSSフレームワークが活用できるのでしょうか?実際にITSSフレームワークをIT人材育成に活用したユーザ企業の事例は散見されます。
しかし、ITSSはシステム開発プロジェクトを中心に策定されており、ITベンダーとしての視点しかなく、自社内に向けた視点はほとんどありません。ですので、ユーザ企業のIT部門にとっては、身に着けることはできても、どうもフィットしないのが実情であったと思われます。さらに、前述の通り、ITベンダーとしてのキャリアパスとして、ITコンサルタント(ITサービスマネジャー含む)・ITアーキテクト・プロジェクトマネジャー、つまり、顧客向けにサービスを行う現場でのトップが一番上のレベルであり、それらは、ユーザ企業のIT部門にとっては、通過点かもしれませんが、ゴールとはなりえないものです。ユーザ企業のIT部門のキャリアパスのゴールは、企業内の経営層、すなわち最高情報責任者(以下、CIO)であるべきだと考えられます。
そのような状況の中、ITSSから遅れること4年、2006年4月に経済産業省が、「情報システムユーザースキル標準(UISS:Users' Information Systems Skill Standards)」を発表し、パブリックコメントを募集、2ヵ月後の6月に情報システムユーザースキル標準第1版(UISS Ver1.0)を発表しました (Tips)
スキル標準の全体像としては、ITSS/UISSと並び、ETSS(組込みスキル標準: Embedded Technology Skill Standards)も経済産業省により定められています。
|
【UISSの逆襲】
発表当初のUISS Ver1.0については、情報システム部門の機能を可視化するための「タスクフレームワーク(図2)」というITSSにはなし、目新しい視点があり、一定の評価を得ることができました。
一方で、「人材像」と「キャリアフレームワーク」と類似の概念わかりにくい点、あるいはユーザ企業側でそれらをカスタマイズする前提が色濃くでており、個々のIT技術者の人材育成に関しては、使いづらいなど、なかなか厳しい評価も多かったことも事実です。
しかし、そのようなマイナス評価が、UISS活用への巻き返しを加速したのかもしれません。1年後の2007年6月には、UISS Ver1.1を、2008年10月には、UISS Ver2.0を、2009年3月には、UISS Ver2.1を次々と発表し、現在は、UISS Ver2.2とその関連文書が公開されています。
ITSSは、情報処理推進機構(IPA)が維持・管理をしており、職種別コミュニティを立ち上げるなど、毎年の改訂を基本として活動しています。それに呼応するように、UISSは、日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が積極的な活動を展開します。ITSS/UISSともに「活きた標準」として、標準を維持管理している組織自身が導入し、自らが活用する図式になっているのです。
特に、UISSについては、自らの危機感「このまま、ITにかかる外部委託が進むとIT人材育成ができない、いなくなる。」に直面したユーザ企業が、おのずとその活用にシフトしたと言えます。 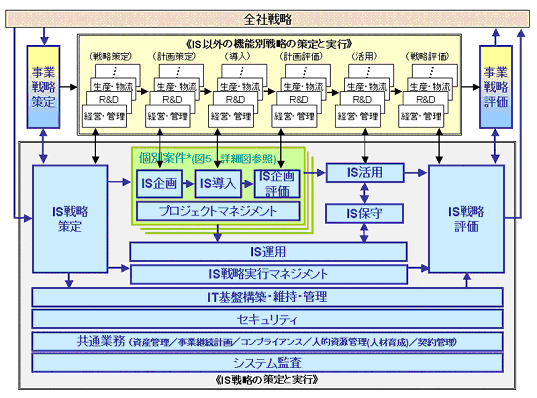
図 2 タスクフレームワーク
【活用可能なUISSへ】
短期間で大きな進化を遂げたUISSは、以下の関連文書をあわせて発表しています。 - 導入推進ワークブック(有効活用ガイド) Ver.3.0
- モデルカリキュラム
- 研修コース設計ガイド Ver.1.0
- 導入テンプレート Ver.1.0
特に、2010年3月に公表された導入推進ワークブック(有効活用ガイド)は、ユーザ企業が、それを参照しながら、UISSをはじめることができるレベルのガイドブックであり、「UISSは、使える!」と断言してもよいと思わせるレベルのものだと思います。
そして、この6月には、「情報システムユーザースキル標準導入活用事例集2010」を公表し、UISSの導入が、ユーザ企業にとって、もはや特別なことではなく、身近なものになったことを知ることができます。
オージス総研グループでは、ITベンダーなどの「IT単一業界」におけるITSSに加え、ユーザ企業などの「複数業界」におけるUISSという2つのフレームワークを駆使して、「本当に使えるIT人材育成」を支援しており、今後は、その実際について紹介していきたいと思います。 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |