第2世代のBSCのことを記述した上記の本の原題は「Strategy Focused Organization」です。このタイトルが示しているように、第2世代からBSCは「戦略マネジメントツール」として位置付けられるようになります。
この本の出版と前後して、私はJISAのミッションで櫻井教授らとともに米国でのBSC導入成功企業を訪問しました。キャプランとノートンが作ったBalanced Scorecard Collaborativeにも訪問し、Harvardでは実際にキャプラン教授と意見交換する機会も持つことができました。
2001年のこのミッションのレポートは、以下で参照することができます。初心者だけでなくわかったつもりになっている方も一度目を通されることをお勧めします。
「バランスト・スコアカードによる戦略的経営の実践に関する調査研究」
第2世代のBSCについては、Balanced Scorecard Collaborative(現the Palladium)の訪問時に多くのサジェスションをもらい、上記の本でより理解を深めました。
なぜBSCを戦略マネジメントツールと呼ぶようになったのか、その理由は以下の通りです。 企業では戦略の展開のしにくさが問題となっており、戦略を実践できるように仕組みを作ることが最も重要である。実際、企業内に戦略を浸透させることを成功した企業は10%程度でしかない。このような企業の経営課題に対し、Balanced Scorecardのフレームワークは、戦略の実践における次の5つの障壁を克服しうるものである。 <戦略の実践における5つの障壁> - ビジョンの共有化での障壁
- 測定を通じて戦略の持つ意味を企業内に理解させ浸透させることができる。
- コミュニケーション=人的な障壁
- 企業内での自分の位置付けを理解し、戦略の展開において、自分の役割を認識してもらうことができる。
- 経営資源の運用での障壁
- 経営資源(ヒト・モノ・かね)のどこに重点的に予算・計画を割り当て、戦略の展開に際しどこに投資すればよいかを決めることができる。
- マネジメント面での障壁
- 戦略は継続的にフィードバックをかけその遂行方法を学習していかなければならないこと、長期的な視点で戦略を経営陣に認識させることができる。
- リーダーシップ面での障壁
- Balanced Scorecardを利用することで、経営陣は戦略を経営にあわせて軌道修正を加えることができる。
|
この考え方を表すものの一つとして、BSCの4つの視点を以下の図のように示すようにかわりました。 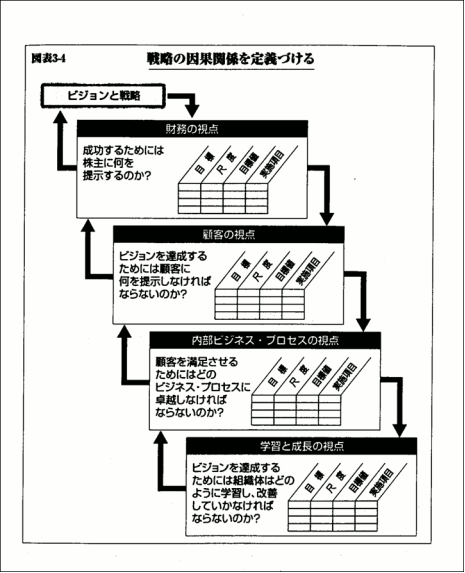
出典:「キャプランとノートンの戦略バランスト・スコアカード」ロバート S・キャプラン、
デビット P・ノートン著、 櫻井通晴 著(東洋経済新報社、2001年)
目標設定時には、「財務」から「学習と成長」の方向に検討を進めるのですが、一方、その実現は、「学習と成長」から「財務」へと成果の連鎖があります。
ここで注意しなくてはならないのは、内部ビジネス・プロセスの視点のところに記述されている「卓越」という言葉です。
顧客に対してどのような価値提案を行うのか(顧客の視点)、それを実現するためには、特にどのビジネス・プロセスを競合他社に比してすぐれたものとしないといけないのかを考えるということが「卓越」の意味です。
さて、この連鎖の上位に経営戦略が位置することから、バランスト・スコアカードを設計することは、自社なりの成功のシナリオを描くことに他なりません。
また、これらの指標を事業部門→部・課→個人へとブレイクダウンさせ、個人や部門の業績評価を経営戦略とリンクさせる機能も有しています。
次号ではBSCの持つ垂直構造と水平構造、そして「卓越」を明確にするための戦略マップのテンプレートについて解説します。 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |