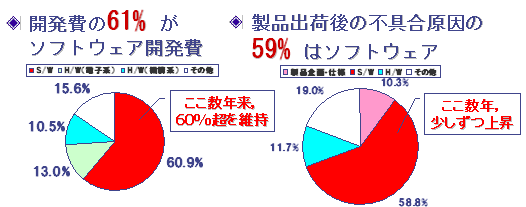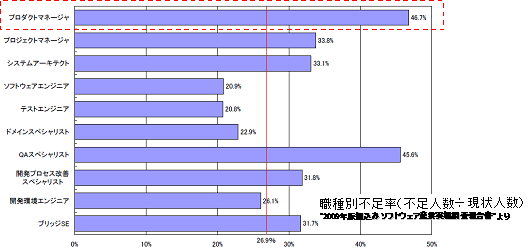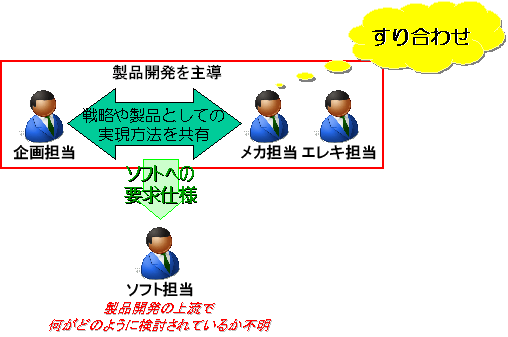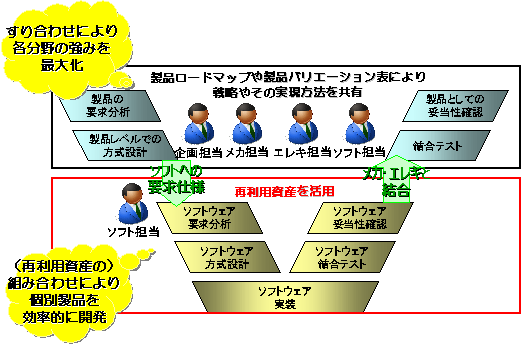Dive 4: Happyな組み込みソフトエンジニアに成長するための手段 皆さん、当ページにお越しいただきありがとうございます。 前回までは(Dive1、Dive2、Dive3)、「ソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリング(Software Product Line Engineering; SPLE)」の技術面や実践面について、事例を交えて述べてきました。
最終回の今回は切り口を変え、組み込みソフトエンジニアの成長の手段として、SPLEを捉えてみたいと思います。 1. 成長(育成)ビジョンを持つ 仕事柄、様々なメーカーの人材育成担当の方と、情報交換やディスカッションをさせていただく機会があります。そのなかで、しっかりとした教育体系(カリキュラムやコンテンツ)を持ち、効果的に運用されている企業には、共通点があると感じています。 それは、 人材育成に確固たるビジョンを持っている ということです。 より具体的には、以下のような点を踏まえて、育成の目標を明確にされています。 - 会社としてどうなりたいか?(経営理念)
- (そのために)今後、事業をどうしていきたいか?(経営戦略、製品戦略、等)
- (そのために)開発現場はどうなるべきか?
- (そのために)開発技術者をどう育成すべきか?
つまり、経営的な観点(経営理念、各種の戦略)から展開されたビジョンを持つことが、人材育成を成功させるポイントとなるのでしょう。
では、私たち組み込みソフトエンジニアの成長(育てる会社の立場から見れば育成)については、どのようなビジョンを持てばよいでしょうか? 2. 組み込みソフトエンジニアの成長(育成)ビジョンを考える(1)経営的な観点を求められている組み込みソフトエンジニア(統計調査から) 製品における組み込みソフトウェアの重要性が高まってきていることは、皆さんも実感されていることと思います。下図は、それを裏付けるデータです。 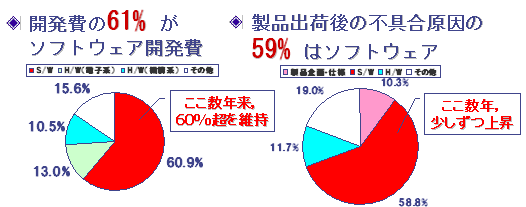
図 1 数値が示す組み込みソフトウェアの重要性
(2010年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書 より作成)
これらのデータは、製品の開発コストや品質が組み込みソフトウェアによって大きく左右されることを示しています。
下図は、このような実態を受け、どのような組み込みソフトエンジニアが経営者層(事業責任者)から求められているかを示すデータです。 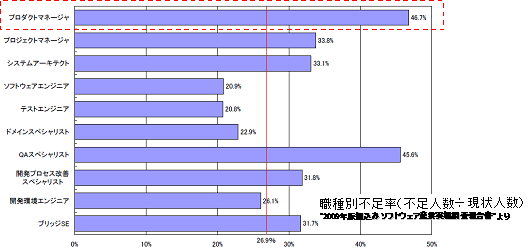
図 2 組み込みソフトエンジニアの職種別不足率
最も不足しているとされるプロダクトマネージャの役割は、組み込みスキル標準において、以下のように定義されています。 経営的観点のもとに、製品の企画・開発・製造・保守などにわたる
製品ライフサイクルを統括する責任者 多くの開発現場では、プロダクトマネージャとして専任者をアサインすることは現実的でないでしょう。図2は"製品戦略等を踏まえ、先々を見据えて開発できる組み込みソフトエンジニアが求められている"ことを意味している、と私は解釈しています。
実際、開発現場や育成の場において、このような組み込みソフトエンジニアを育成しようとする動きがあります。
例えば、あるメーカーにおいては、社内のソフトウェアの人材育成制度において、プロダクトマネージャの役割を担う人材タイプを定義し、対応した研修制度を構築されています(http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060516/238015/)。
また、第一線級の組み込み技術者の育成を目指している東海大学専門職大学院 組込み技術研究科では、事業計画の立案を含め、製品開発のマネジメントに参画できる組み込みソフトエンジニアを育成するためのカリキュラムが組まれています。 (2)製品開発のより上位への参画が求められる組み込みソフトエンジニア
(弊社の参画事例から) 私は様々なお客様のご支援を通じて、組み込みソフトエンジニアは製品や製品戦略に対するコミットをもっと高く持つべきだと考えるようになりました。
組み込みソフトウェアの重要性が低かったこれまでの経緯から、私たち組み込みソフトエンジニアは、メカ担当やエレキ担当が製品開発を主導するという意識になりがちです(図3)。 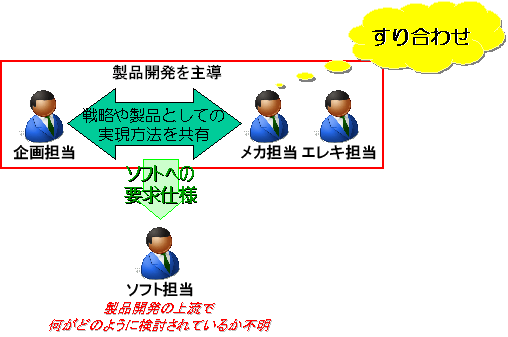
図 3 ありがちな製品開発の姿
組み込みソフトウェアの開発は、多くの場合、製品開発の後半工程に位置づけられるため、その時点で意見を出しても製品全体に反映させることが困難です。結果として、上記のような意識を中々払拭できないのは仕方ない面もあります。
しかし、その一方で、メカ担当者から"ソフト担当者にも、製品がお客様に提供する価値をもっと考え出して欲しい"という声をお聞きすることもあります。
昨今の製品における組み込みソフトウェアの重要性からすれば、製品開発のより上流工程から参画し、製品の価値を高め、かつ製品のQCDが達成可能な提案を、ソフトウェアの専門家として行うべきではないでしょうか。 (3)どのような成長(育成)ビジョンを持つべきか? 以上のことを踏まえ、私は、
経営的な観点を理解し
その実現に積極的に寄与できるエンジニア と考えています。
自分自身を振り返ってもそうなのですが、納期に追われ、どうしても目前の製品だけを見てソフト開発してしまいがちです。
これに対して、経営的な観点、すなわち製品戦略等を理解し実現するということは、視点を広げ先々の製品も見据えたソフト開発を行うことになります。なぜなら、通常、製品戦略は、今後の市場や競合他社の動向に対応するべく、様々な製品への展開を含んでいるからです。
さらに、先々の製品を見据えた開発を行うためには、製品開発の早い段階(工程)で、メカやエレキの担当者と、戦略やその実現方法についてすり合わせていくことも必要になるでしょう。 3. 成長(育成)ビジョンの達成手段としてのSPLE SPLEはこのような成長(育成)ビジョンを達成する手段としても有効だと、私は考えています。
なぜなら、経営戦略や製品戦略、技術戦略等に基づいて製品ロードマップや製品バリエーション表を作成すること(Dive2を参照)は、経営的な観点を理解していることになるからです。
また、そのような製品ロードマップや製品バリエーション表に沿った再利用資産を蓄積し、それらを活用して製品開発を行うことは、経営的な観点を製品として実現していることになります。
さらに、製品ロードマップや製品バリエーション表は、製品開発のより上位工程でメカ・エレキの担当者と議論したり認識合わせをしたりするためのツールにもなるでしょう(下図)。 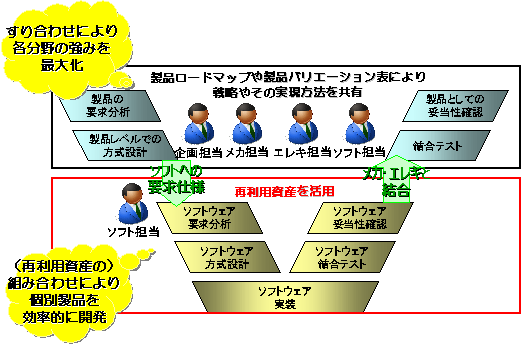
図 4 製品開発の上位工程にソフト担当が参画
4. 最後に 4回にわたり、SPLEについて、私個人の思いも含めてご紹介してきました。ここまでお読みいただいた皆様には、厚く御礼申し上げます。
既にSPLEに取り組んでいる皆様はもちろん、SPLEに関心を持ち、これから取り組んでみようとされている皆様にとって、何がしかご参考になれば幸いです。
それでは、またどこかでお会いできることを楽しみにしています。 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |  「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる(3)」
「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる(3)」
 「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる(2)」
「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる(2)」
 「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる」
「組み込みソフト開発現場でソフトウェア・プロダクトライン・エンジニアリングについて考えてみる」