最近の映画が、ファイナンスの考え方を忠実に駆使して作られているということ、皆さんは気づいておられますか?本稿ではこれからしばらく肩の力をちょっと抜いて、映画作りにおける「製作委員会方式」の話を通じて、ファイナンスの考え方の実際を見てみようと思います。できれば、シリーズ化の野望を秘めつつやってみようかと思っておりますのでお付き合いください。
昨年5月の拙稿「ビジネス・イノベーションの土台としてのファイナンス」の中で、ファイナンスをValuation(価値評価)、Risk Management(リスクマネジメント)、Transaction(実際の取引手法)の3つの側面から考えてみました。今の映画造りにおいては、例えば(図1)のような製作委員会の形で、こうしたポイントを様々な形でグリップしています。 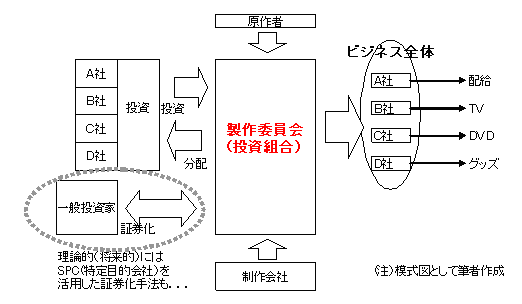
図1 映画の「製作委員会」方式
昔、映画といえば映画会社が全面的にリスクを負って作り、系列の映画館における興行収入で基本的には回収するという形でした。しかし、今の映画はリスクも高く、様々なビジネスが付随して複雑化しており、大作でなくとも1社でリスクを負いきれるという時代ではなくなっています。そこで、この製作委員会方式が1990年代以降主流になりつつあるわけです。
ともあれ、"Cash is King、 cashflow is queen."を旗印とする本稿としては、まずはキャッシュフローの視点にフォーカスして詳しく見てみましょう。製作委員会のスキームは、まず映画を「コンテンツビジネス」と広く位置づけていることが前提です。映画というコンテンツを源とするキャッシュフローとしては、映画館の興行収入だけではなく、例えばTVの放映権料、DVD販売とレンタル、キャラクタービジネス、ノベライズなど様々なものがあります。これらの関連ビジネス(その権利とキャッシュフローそのもの)は製作委員会で封じ込めます。すなわち、こうした主要なコンテンツビジネスの権利を持つ人たちが中心となって出資して製作委員会(組合)を作り、その利益の分配も製作委員会(組合)から受けるわけです。もちろん、製作委員会はペーパーカンパニーではなく、映画をつくる実際の組織であることは言うまでもありません。
このスキームをキャッシュフローやリスクの観点で紐解くと、色々と面白いことが解ります。例えば、昨年の3D映画「アバター」では劇場で絶賛公開中にDVDの発売に踏み切っています。昔だったら、映画館での公開が終わってからが常識でしたが、これもこうしたスキームで考えてゆけばナゾがとけるかもしれません。ビジネス全体のキャッシュフロー最大化のためには、どの時点でDVD発売するのがいいのか、TV放映はいつ頃がいいのか、などなど、全体最適の動きは、みんながバラバラに動くのとは答えが違ってきますね。
リスク低減と分散効果もポイントです。リスクファイナンスの理論では
(イ) 全体のリスク量は個別のリスクの総和より小さい
(ロ) 一つの籠にすべての卵を入れるな
というのが、何より重要なポイントです。(いわゆるポートフォリオ理論)
製作委員会方式は、この二つを見事に実現しているスキームでもあります。極端な話、映画館の客が入らなくても、DVDやプラモデルが売れてペイすればいいや、といった話が十分に成立するわけです。また、映画館の入りが悪かったからといって、DVDの売れ行きがそれに連動するとは限りらないというのがリスク分散効果であり、その結果個別のビジネスのリスク量の総和が全体のリスクより小さくなるということです。
オリビアニュートンジョン(大ファンです、昔も今も!)の80年代の映画でXanaduというのがありましたが、興行惨敗、映画評論家も酷評、なのにオリビアのアルバムだけは爆発的にヒット、なんていう事例もありました。TV放映が低視聴率で打ち切りになった、ファーストガンダムも、バンダイ(もちろんガンプラ)は放映続行を希望していたというというトリビアもあります。
映画ビジネスに関わる色々な会社も、一つの映画に社運をかける必要もなくなります。つまり一つの籠に自分の卵を全部入れる必要はないということですね。いろんな映画にちょっとずつチップをおく(投資する)リスクヘッジが極めて有効な上、色々な製作委員会に顔を出すというやり方で現実的にも可能となってきているのです。
次回はもう少しこのスキームを別の視点から見てみたいと思います。銀行や保険の黎明期と、こうしたスキームの接点のお話です。 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |