オージス総研では「百年アーキテクチャ」というキーワードを掲げて、できるだけ長く使っていただけるシステムをお客様に提供できることを目標にしています。そういった経験や考えを「百年アーキテクチャ~持続可能な情報システムの条件 」という本にまとめさせていただきました。この本では企業の情報システムに関して、開発技術、インフラ、運用、情報システム部門や情報子会社の体制・役割など様々な視点で長く使える、変化に強い情報システムをつくっていくためにはどうしたらよいかを、コンサルタントが各々の経験や知見に基づいて執筆しました。私もインフラ技術についての一部を執筆したのですが、本全体のバランスやボリュームのこともあり、まだまだ書き足りないことが多くありました。そこで、今回は「百年アーキテクチャ(インフラ編)」と題して、長く使える/変化に強いITインフラを構築するためには、どのような考え方に基づくべきかについてご紹介したいと思います。 長く使えるITインフラを構築するために、留意するポイントを3つのキーワードにまとめました。 オープンであること インターネットは世界で一番大きなネットワークインフラですが、同時に世界一長寿なネットワークインフラであるとも言えます。ARPANETから数えると、実に40年以上にわたって規模や機能を拡大しながら、常に利用可能なITインフラとして稼動し続けています。インターネットがこれだけ長く成長を続けられるのは、仕様がオープンであることが大きな理由の一つではないかと考えます。インターネットで利用される各種プロトコルは、ISOC(Internet Society)という団体によって管理され、RFCと呼ばれるドキュメントとして全て公開されています。またその仕様は草案段階からインターネット標準となるまで、議論も含めてオープンな場でおこなわれています。そのためインターネットを構成するハードウェアやソフトウェアは、これらの公開された仕様に基づいて、様々な企業、団体、個人が作ることが可能です。そのため特定の企業や団体、国の事情に左右されること無く、継続的に新しい技術/ニーズに対応することができ、結果として長期に渡る成長が可能となったと言えます。
我々が携わる企業のITインフラも、規模はインターネットと比較すれば小さいですが、継続的に新しいアプリケーションやシステムからの要件に対応することが求められています。これらの対応のために特定の企業のみが有する技術(=クローズドな技術)をなるべく用いないようにしましょう。一見コストが安く効率のよいやり方に思えても、拡張性を阻害したり、選択の幅を狭めたりしている可能性があります。
オープンソースの活用も、オープンであることの恩恵を受けられる有効な手段です。商用ソフトウェアの多くは、販売元の企業が決めたサポート期限があり、この期限を過ぎればバージョンアップをしないとサポートを受けられません。オープンソースであれば、自己責任で使用することや、障害が発生した場合に、ソースコードから問題の調査/対応をおこなうことで、より長く使い続けることが可能となります。 スタンダードであること スタンダード(標準)であることは、オープンと似ていますが、仮にそれが全て公開されたものでなくても、世間一般で標準的に使われているものは、同様のメリットを生む場合があります。例えばIA(Intel Architecture)サーバは、Windows ServerやLinux Serverなどの多くのサーバOSが動作し、多くの企業で利用が進んみました。そのため各サーバメーカーが主力製品として開発に力を入れたことで、品質が上がり、かつコストに対する性能比は飛躍的によくなりました。IAサーバを選択することで、より安く安定した高性能なリソースを得ることができ、ハードウェアの更新時期がくればさらに安く、性能の上がった機器が入手できるという、よいサイクルが生まれています。
また、最近注目されているサーバ仮想化技術ですが、この領域でのスタンダードは、現状ではVMware社が一歩抜きん出ています。オープンソースのXENやKVMといったものもありますが、実績や耐障害性のオプション機能などを理由にVMwareを選択されている企業も多い状況です。オープンという観点では、VMwareを選択することで、構築した仮想サーバはVMwareの独自フォーマットとなってしまい、拡張やリプレイスに制限を受けているとも言えます。仮想化に関する仕様の標準化はDMTFを中心におこなわれていますが、デファクトスタンダードまでには至っていません。(http://www.dmtf.org/standards)
ただし、これだけVMwareの利用者が多いと、対抗製品を持つベンダー企業は必ずVMwareからの移行を前提として考え、なんらかの移行ツールを用意するので、次期仮想環境の選択肢は狭まらないと思われます。これも世間一般の標準を選択しておくメリットの一つです。
また、社内での標準化もITインフラを長持ちさせるための重要な要素です。「オープンであること」で要件に対して、できるだけオープンな仕様/技術で対応する優位性を述べましたが、そもそもシステムから出てくる要件がクローズドな技術を必要とするものであった場合には、オープンな技術での対応が難しくなる場合があります。 例えば経済産業省が発行している「情報システムに係る政府調達の基本指針」では、オープン化の方針としてベンダー独自技術への依存を廃することが記述されています。(http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/index.html)
また、大阪ガスグループでも開発標準を設けて、その中でクローズドな技術を利用しないようなルールを記述しています。このようにITインフラを長持ちさせるためには、その上で動くアプリケーションやシステムの領域も標準化によるコントロールをすることが必要となります。 疎結合 アプリケーション開発の世界では、SOAという考え方でプログラム部品をサービス化し、部品間をサービス呼び出しとして疎結合にすることで、システム全体を変化に対応しやすくしていく方向にあります。疎結合という考え方は、変化に柔軟に対応できるITインフラを構築していくためには重要なポイントです。ITインフラの結合イメージは、SOAのようなサービスという単一の構成物ではなく、サーバやネットワークなど様々な領域に属する様々な構成物(実態はハードウェアやソフトウェアなど)によって複雑に構成されます。(図1) 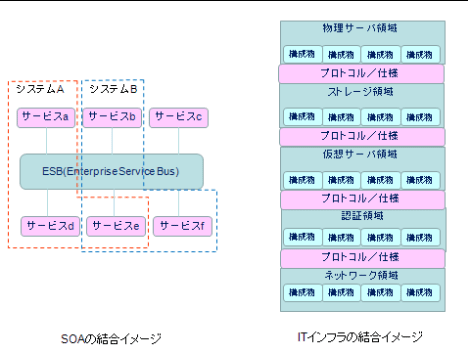
図 1 SOAとITインフラの結合イメージの違い
SOAの場合、結合はESBによるサービスインターフェイスですが、ITインフラの場合はプロトコルや各種仕様など様々なインターフェイスによってつながっています。このように複雑なITインフラを疎結合にするということは様々な条件が関係するため、決まった方式や解があるわけではありません。そのためいくつかの例によって、密結合/疎結合の違いを示したいと思います。
ITインフラを疎結合にする目的は、依存関係を少なくすることで一部の変化に影響をうけにくくすることです。例えば変化の例として、M&Aによる会社合併や分社化による離脱などでユーザーが属するネットワーク環境が変化する場合や、各構成物(ハードウェア、ソフトウェア)のリプレイス、パッチ適用、バージョンアップなどが挙げられます。領域ごとに密結合の例と影響を受ける変化、より変化を受けにくい疎結合の例を提示します。(表1) 表1 密結合の例と影響を受ける変化、より変化を受けにくい疎結合の例
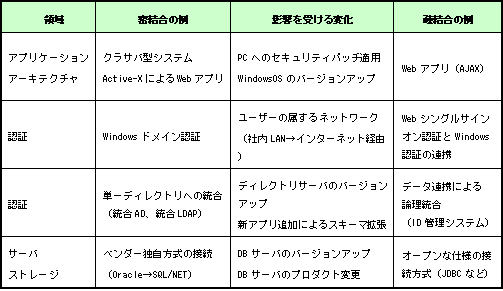 例えば2番目の例では、Windowsドメイン認証をすべての認証システムとして利用していた場合(密結合の例)に、これまで社内LAN経由で利用していたある所属が分社化により、別会社の別ネットワークに分離されたとします。この分社会社がインターネット経由となった場合に、これまで使えていたシステムがすべて使えなくなりますが、Webシングルサインオン認証とWindows認証の連携を行っていた場合(疎結合の例)、Webシングルサインオン認証で使っていたシステムは、そのまま使い続けることが可能となります。このように構成物の機能を分離して、影響範囲を狭くすることで、変化に強いITインフラが構築できると考えられます。
この3つのキーワードによる考え方は、私がこれまで担当したいくつかの企業でのインフラ設計や構築、運用した経験をもとにしたものであり、特に疎結合の考え方については、まだまだ整理できておらず、検討や議論が必要です。企業のインフラ担当をされている方の中には異論や反論をお持ちの方も多いと思われます。そのような意見をお伺いする場、議論をする場を提供したいと考えています。まずは興味がある方、ご意見・ご感想など、メール、twitter、facebookにてお送りください。 メール:Ikeda_Dai@ogis-ri.co.jp
Twitter:http://twitter.com/daikunjp
Facebook:http://www.facebook.com/profile.php?id=100001731336559 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |