第3世代のBSC その2 第3世代のBSCの最大の特徴である「レディネス」。このレディネスの概念を用いることで、IT投資を合理的に説明することができます。
このために、キャプランとノートンは表-1に示すように「情報資本」の詳細を定義し、そしてこの概念をもとに図-1に示す「情報資本ポートフォリオ」というものを準備してくれています。 表1.情報資本
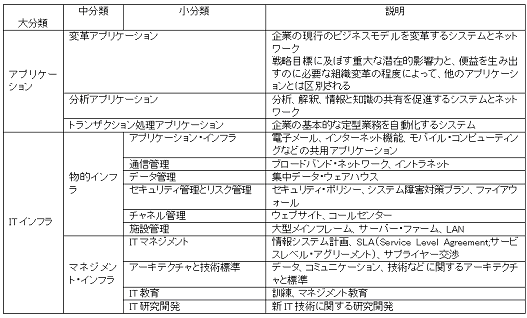 この情報資本の定義はPeter WeillのITポートフォリオの考え方を引き継いだものですが、EAの5つの要素のうち、TAとStandardsに該当するものであり、極めて理にかなった定義と捉えています。
当社ではこの情報資本の考え方もとにITガバナンスの活動を定義しています。
さて、経営戦略とIT投資との関係を整理するのが、図-1の情報資本ポートフォリオです。図の左側はバリューチェーンプロセスにかかわる部分、図の右側は、人的資本、組織資本のレディネスの向上にかかわる部分となっています。 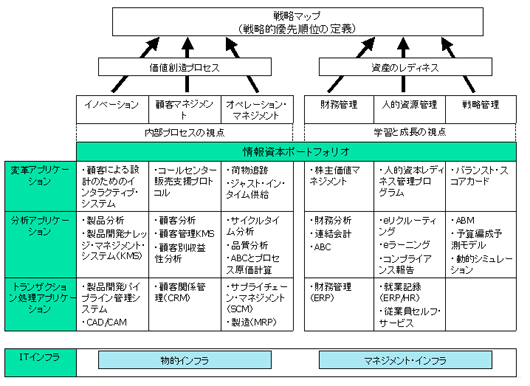
図 1 情報資本ポートフォリオ
情報資本ポートフォリオでは、新しいビジネスプロセス(左側バリューチェーンプロセス、右側バックオフィス)を実現するためにどのようなアプリケーションおよびそれを支えるITインフラが必要かを定義します。
次に図-2に示すように情報資本レディネスの評価を行います。この図の上段には各プロセスクラスターにおける戦略テーマが示されており、下段には各テーマに対する既存情報資本のレディネス評価の結果が示されています。 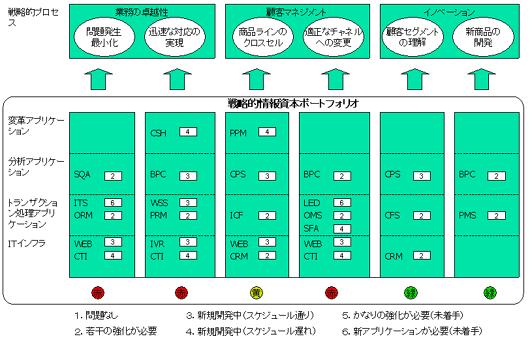
図 2 情報資本レディネスの例
一般に企業では多くのシステムが既に稼働しているわけですから、新しい業務プロセスを実施するにあたって、既存のシステムの変更で対応できるのか、新しく構築するのが必要なのかなどを判断することは、極めて理にかなっていると考えることができます。 さて、新しい業務プロセスは情報資本への投資によってのみ実現できるものではありません。戦略人材の確保も同時に必要となります。図-3はその検討のフレームワークを示したものです。この図では、顧客管理プロセスに関して「商品ラインのクロスセル」という戦略テーマが設定されており、その実現にあたって「フィナンシャル・プランナー」という戦略人材が必要であると定義され、人的資本にはその人材に求められる属性が示されています。 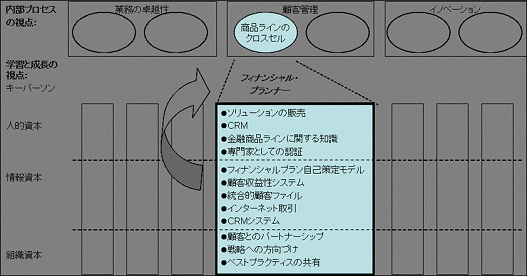
図 3 戦略人材の検討
以上ご紹介したように、第3世代のBSCでは、合理的に戦略をアクションプランに展開することができます。
以前に櫻井教授らとともにキャプラン教授と対談した際に、「自分はもともとMITの出身なのでで、システマティックに整理することが好きなのだ」というようなことをおっしゃっておられました。確かに、BSCだけでなくABCも非常によく構造化され、実行しやすいものになっています。
さて、BSCの紹介はいったん今回で終了しますが、実はまだまだご紹介しないといけない本が2冊残っています。 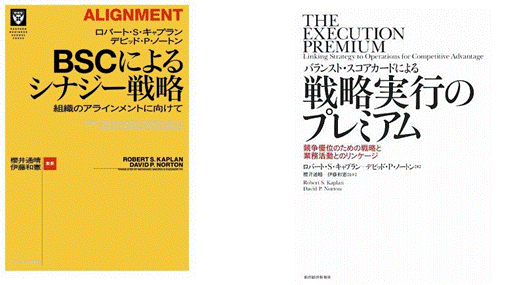
図 4 BSC 上級編の本
左側の本ではBSCが個別最適にならないためにOSM(Office for Strategy Management)を中核として各組織のBSCの整合をとるための方法論が述べられています。右側はBSCの集大成というべきもので、理論の理解を超えてBSCを使って戦略を実行するための様々なプラクティスが書かれています。
いずれ機会をみて、連載させて頂きたいと思います。 「戦略マップ」:本文中の図は全てこの本からの引用
ロバート S・キャプラン、デビット P・ノートン著、櫻井通晴・伊藤和憲・長谷川惠一監訳(ランダムハウス講談社,2005年) *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |