WEBマガジン
「“ファシリテーション”と“場の論理”と“パターンランゲージ”と」
2016.07.27 株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部 安松 健
場をつくり、つなげる
日本ファシリテーション協会によれば、ファシリテーションのスキルとして、
- 場のデザインのスキル ~場をつくり、つなげる~
- 対人関係のスキル ~受け止め、引き出す~
- 構造化のスキル ~かみ合わせ、整理する~
- 合意形成のスキル ~まとめて、分かち合う~
場づくりを4つに大別して考える
さて、この「場づくり」ですが、4つに大別して理解することが有用だと考えています。ファシリテーションは、1対1ではなく1対n(1対多)と説明されますが、どのような1対nかが場の全体設計において大きな影響を及ぼします。下図をご覧ください。
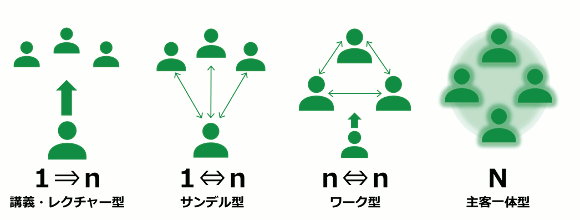
図1 場づくりの4つの型
「1⇒n型」は、特定の人が一方向に情報を発信するいわゆる講義・レクチャー型で、ファシリテーターというより講師・講演者になります。より多くの人に向けて情報を短時間に大量に発信できますが、話し手と聞き手がはっきりと分かれ、聞き手が受け身になりやすい型になります。
「1⇔n型」は、双方向でインタラクティブなやりとりがなされます。ただ、そのほとんどはファシリテーターを経由して行われ、やりとりの中心にファシリテーターがいる型になります。NHKハーバード白熱教室のマイケル・サンデル[2]が代表例でしょうか。この型は、場のやりとりを(大人数であっても)参加者全員に共有できますが、発言できる人は限られるという特徴があります。
「n⇔n型」は、全員がそれぞれに双方向のやりとりを行っている、いわゆるグループワークが主となる場などになります。ファシリテーターがやりとりの中心にいるというよりは、全参加者間の相互のやりとりが活性化するようにサポートします。この型は、より多くの参加者が発言できますが、全体の状況(やりとり)を把握することは困難になります。
共創に必要な主客一体の「N型」
| "普通は、まず『私』というものが存在していて、『私』が何かしてやろう、などと考えるわけです。しかし、実はそんなふうに思っていては、大したことはできない。『私』から離れて、自分も相手も含んだ全体を飲み込んだ見方でものを見るということをしなければ、自分自身の最高の働きを発揮することなどできない"[3] |
もしファシリテーションの現場で、下記のような課題があるのであれば、
- グループワークを実施しているが、既存の枠内で収まってしまい新しい発想が出てこない
- 良いアイデアは出ていると思うがアクションにつながらない
また「異質の」という点も見逃してはなりません。
「私と他者」ではなく「私たち」となったとしても、同質・均質的な私たちとなる閉鎖的な「群れ合いの場」となっては、創造的にはなりえません。この群れ合いの場というのは、"互いに依存し合うことによって見せかけの安心感を得ている"場で、"場に束縛されると同時にその枠を守ろう"とし、"自己防御のために、創造につながるような異論を許さない"、そのため"その内部では創造的な活動力は生まれない"場になります。[4]
創造のためにはこのような群れ合いの場ではなく、異質の個と個、"両者のあいだに新しい関係が生まれて個の活きが統合され、両者が開かれる"「出会いの場」でなければならないこと[4]も忘れてはいけません。
パターンランゲージ3.0
重要な示唆を与えてくれるものとして、パターンランゲージ3.0があります。パターンランゲージは、"ある領域に潜む《デザインの知》を記述した言語"で、その対象は、1.0は建築などの「物質的なもの」、2.0ではソフトウェアなどの「非物質的なもの」でしたが、3.0では学びや教育、変革行動などの「人間行為」がデザインの対象になります。また、使い方としては、1.0は「デザインする人と使う人」の間を、2.0は「熟達者と非熟達者」の間を埋めるためのものでしたが、3.0では異なる経験を持つ「多様な人たちをつなぐ」ために用いられます。[5]
このパターンランゲージ3.0の中でも、共創の場づくりのためには、"Pedagogical Patterns for Creative Learning[6]"と"Educational Patterns for Generative participants[7]"がおすすめです。すべては紹介できませんので、この中から2つほどパターンを紹介すると、my discovery, your discovery, our discoveryとひろげていく 「Discovery-Driven Expanding(発見の拡がり)」や、リーダーでもファシリテーターでもなく参加者と表現されている「Generative Participant(生成的な参加者)」などがあり、主客一体に直結することが確認できます。
なお、これらのパターンは創造的学習の現場よりマイニングされたものですが、ビジネス現場においても有用です。このことは、コラボレイティブ学習と知識経営の研究の関係[8]を考慮すれば当然のことにはなりますが、ビジネス界に限らず異業界の実践知も活用していくことは効果的です。
参加者が決めるということ
そして、参加者が決めるということを肝に銘じて、意図した場づくりができているか、十分に注意して確認し続けることが必要になります。
最後に
(参考文献)
| [1] | "ファシリテーションとは" 特定非営利法人日本ファシリテーション協会Webサイト |
| [2] | "NHKハーバード白熱教室" NHKオンライン |
| [3] | 『生命知としての場の論理―柳生新陰流に見る共創の理』 清水博 中公新書1996年 |
| [4] | 『場の思想』 清水博 東京大学出版会2003年 |
| [5] | 「パターンランゲージ3.0」 井庭崇 情報処理Vol.52 No.9 2011年 |
| [6] | "Pedagogical Patterns for Creative Learning," Takashi Iba / Chikara Ichikawa / Mami Sakamoto / Tomohito Yamazaki, 18th Conference on Pattern Languages of Programs (PLoP11), 2011. |
| [7] | "Educational patterns for generative participants: designing for creative learning", Shibuya Takafumi, et al. Proceedings of the 20th Conference on Pattern Languages of Programs. The Hillside Group, 2013. |
| [8] | 『コミュニティ・オブ・プラクティス―ナレッジ社会の新たな知識形態の実践』 エティエンヌ・ウェンガー/リチャード・マクダーモット/ウィリアム・M・スナイダー(著)野中郁次郎(解説) 翔泳社2002年 |
| [9] | 『ロジカルリスニング「論理思考」と「聞く技術」の統合スキル』 船川淳志 ダイヤモンド社2006年 |
| [10] | 『茶の本 The Book of Tea【日英対訳】』 岡倉天心 IBCパブリッシング2008年 |
*本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。
『WEBマガジン』に関しては下記よりお気軽にお問い合わせください。
同一テーマ 記事一覧
 「行動観察とIT~後篇:事実の現場力をどう仕組みにつなげるか~」
「行動観察とIT~後篇:事実の現場力をどう仕組みにつなげるか~」
2018.07.19 共通 株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部 矢島 彩子
 「行動観察とIT~前篇:顧客意図を把握するということ~」
「行動観察とIT~前篇:顧客意図を把握するということ~」
2018.02.20 共通 株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部 矢島 彩子
 「現代に求められる「もう一方の力」と「対話型組織開発」」
「現代に求められる「もう一方の力」と「対話型組織開発」」
2017.12.15 共通 株式会社オージス総研 行動観察リフレーム本部 松本加奈子
 「行動観察とビッグデータ」
「行動観察とビッグデータ」
2013.09.18 ITガバナンス 株式会社オージス総研 鈴村 一美
 「IT分野における行動観察の適用 ~その2~」
「IT分野における行動観察の適用 ~その2~」
2013.04.17 ITガバナンス 株式会社オージス総研 鈴村 一美
 「IT分野における行動観察の適用 ~その1~」
「IT分野における行動観察の適用 ~その1~」
2013.02.12 ITガバナンス 株式会社オージス総研 鈴村 一美
