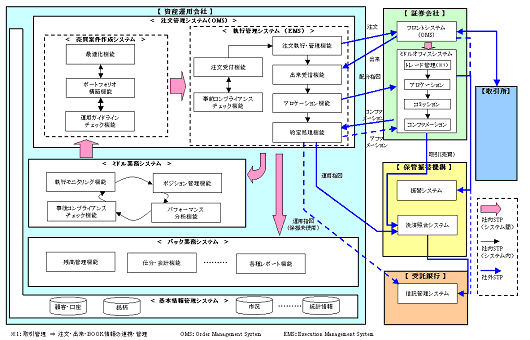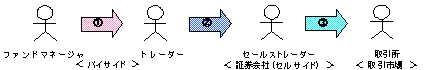昨年は、「証券STPの進展」と題して、証券取引・決済の自動化・効率化について、記載させて頂きました。
今回からは、それに関連する事項として、「トレーディング業務」について、基本的な事柄を中心に記載して行きたいと思います。
トレーディング業務は、バイサイド(資産運用会社:投信投資顧問、信託銀行、生損保など)における業務、セルサイド(証券会社など)における業務がありますが、まず今回は、バイサイドのトレーディング業務について記載します。
尚、本文中、意見にわたる部分は、筆者の私見であることを予めお断りしておきます。 1.バイサイドから見た証券取引の概要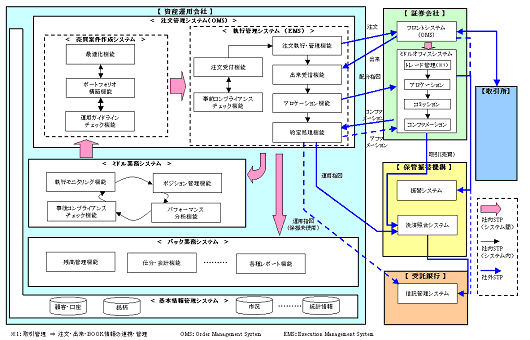
図1 バイサイドから見た国内証券取引とシステムの例
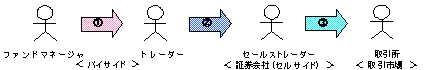
図2 登場人物と注文執行の流れ
| (1) | ファンドマネージャは、運用戦略・運用方針に基づき担当するファンドについて個別の銘柄の売り買いを決定します。OMSの売買案件作成機能を使用して、売買案件を作成し、それを、トレーダーに回送します。 | | (2) | トレーダーは、OMSの執行管理機能を用いて、複数のファンドマネージャから来た売買案件を取り纏め、資産運用会社の顧客(※1)にとって最良となるように、執行方針を決定し、証券会社の担当トレーダーに注文を執行します。
この際、必要に応じてIOI(※2)を出します。 | | (3) | 証券会社のトレーダーも、バイサイドトレーダーとの取り決めの基づき、顧客に最良となる様に、取引市場に注文を執行します。 |
- バイサイドのトレーディング業務は、主として前述の図1の「執行管理」の
注文受付 → 事前コンプライアンスチェック → 注文執行・管理 → 出来管理
の部分に当たります。 - ※1顧客:年金基金やファンドなど、ファンドについては、実際は投資家。
※2 IOI :Indication of Interest 資産運用会社が取引の意図を提示し取引相手を探す事。
2.トレーディング業務の目的・役割 私が証券会社に入社した1980年代、バイサイドのトレーディング業務は、まだきちんと確立されていませんでした。バイサイドでは、ファンドのマネージメント業務に非常に大きなウェイトがおかれ、トレーディング業務は、まだまだ、等閑にされていることが多く、専任のトレーダーを配置している資産運用会社は大手でも殆どありませんでした。でも、近年は違います、1998年の日本版ビックバン以降の手数料の自由化、取引所集中義務の撤廃によるプリンパル取引解禁などにより、バイサイドおいても、トレーディング業務の重要性が認識され、人材、システム、制度など其々の面で充実してきています。 - ■目的・役割
- 最良執行を実現する事です。
- 最良執行とは、顧客にとって最良の取引の条件で注文を執行するための方針及び方法を定めたものです。最良執行義務とは、価格のみならず、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務のことです。
- 【前提】低リスクで効率化した事務の取廻しが出来る事。
価格 :出来るだけ安く買って、出来るだけ高く売る。
コスト:取引にかかわるコスト(売買委託手数料など)を可能な限り低く抑える。
スピード:取引の執行開始から完了までを出来るだけ短時間にする。
執行の確実性:買うべき銘柄を確実に買いきり、売るべき銘柄を確実に売り切る。 - と単純に書くと、「最良執行」は簡単そうですが、一筋縄には行きません。
市場は常に流動している事、取引の種類が多様化している事、従来の取引所に加えPTS市場の登場で市場が多岐に亘っている事、確実な執行を含め市場が多岐に渡っている事、執行の確実性をどの様に評価するかなど検討・考慮すべき点は沢山あります。
- ■役割分担
近年、トレーディング業務の重要性の増加からファンドマネージメント業務とトレーディング業務を分業して行う資産運用会社が大半を占めています。
ファンドマネージャとトレーダーを役割分担する事で、以下の効果があります。| (1) | 専門性の高める事で効率化・パフォーマンス向上を実現できる
前述の様に、トレーディング業務は高度化、複雑化しています。又、ファンドマネージメント業務もアセットの多様化や、運用手法の高度化、アクティブ運用の深耕化など年月を重ねる毎に高度化、複雑化しています。この様な状況の中で、一人の人間で、相異なる、両方の業務をハイパフォーマンスで実現するのは非常に困難になっています。トレーダーは「取引」に集中し、ファンドマネージャは「運用」に集中する形態が一般的になっています。 | | (2) | コンプライアンス遵守の強化ができる
最良執行を行うためにはコンプライアンスを遵守した取引を行う事は当然の事です。
資産運用会社は、「ファンド間売買の禁止」や「特定証券会社への発注の偏り」、「運用ポリシーとの事前の整合性チェック(例:株式運用比率上限への抵触確認)」など、金融商品取引法はじめとする各種の法令のみならず業界や社内の規制について違法な取引、誤った取引を行わない様にコンプライアンスチェックを行っています。
ファンドマネージャ、トレーダーの相互間でチェックを行うことで、コンプライアンス遵守の強化に繋がります。 |
- 役割分担をする際の問題点としては、案件情報や発注方針の共有化などがありますが、情報共有化を促進するシステムを整備し、コミュニケーションを十分に取れる体制・組織を作る事が肝要でると考えます。
次回は、「執行コスト」や「取引の種類」を中心に、バイサイドのトレーディング業務について記載して行きたいと思います。 *本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |  「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第六回)」
「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第六回)」
 「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第五回)」
「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第五回)」
 「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第四回)」
「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第四回)」
 「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第三回)」
「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第三回)」
 「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第二回)」
「トレーディング業務基礎(バイサイド編 第二回)」
 「証券STPの進展 第四回」
「証券STPの進展 第四回」
 「証券STPの進展 第三回」
「証券STPの進展 第三回」
 「忠臣蔵と元祖デリバティブ取引所 」
「忠臣蔵と元祖デリバティブ取引所 」
 「証券STPの進展 第二回」
「証券STPの進展 第二回」
 「証券STPの進展 第一回」
「証券STPの進展 第一回」