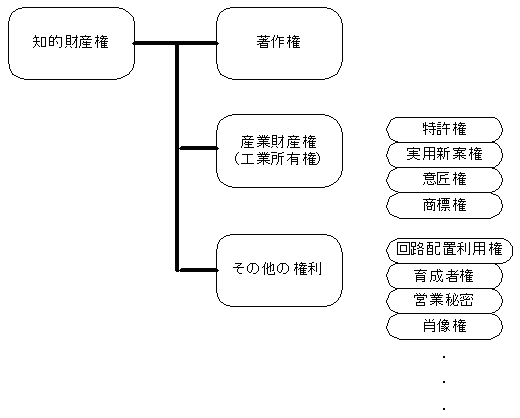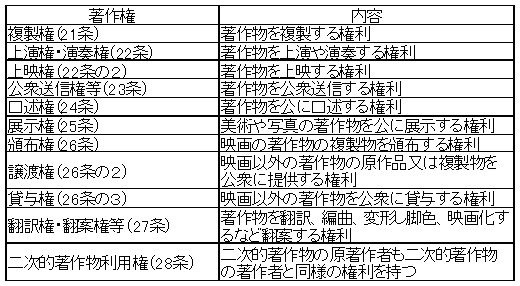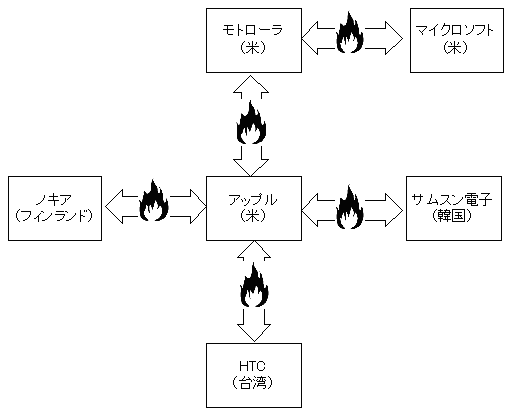※ 本稿は、財団法人経済産業調査会発行 「特許ニュース」No.13226(2012 年5月11日発行)への寄稿記事です。 1. はじめに 第4回では『ソーシャルメディアを利用する企業の動向と事例』と題して、企業におけるTwitter、Facebook、YouTube、mixiなどの利用動向と実際の活用事例を紹介した。TwitterやFacebookの利用率は非常に高く、また複数のソーシャルメディアを組み合わせて有効に利用していることが分かった。そして、ソーシャルメディアを利用する上で必要になってくるポリシーやガイドラインについても解説した。これらのポリシーやガイドラインは炎上を予防する上で有効である。本稿では、ときに炎上の原因の1つとなる権利侵害について、ソーシャルメディアと著作権や特許権などの知的財産権、プライバシー権との関係を中心に解説していく。 2. 知的財産権 知的財産権は、著作権そして特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの産業財産権(工業所有権とも呼ばれる)に分れる。それ以外にも、回路配置利用権(半導体回路配置保護法)、育成者権(種苗法)、営業秘密(不正競争防止法)、肖像権などがある。 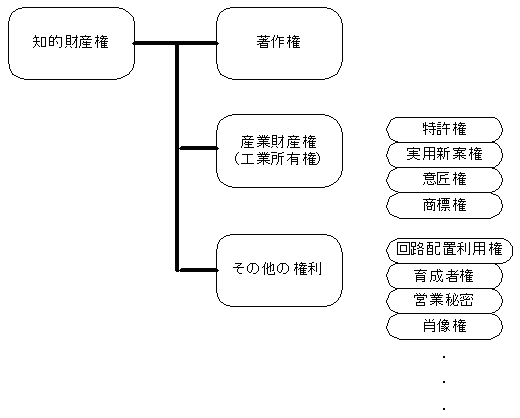
著作権は登録の手続きを必要とせず、著作物ができた段階で権利が発生する。それに対して、産業財産権は、登録をしないと権利が発生しない。
この点を踏まえ、まず最初に知的財産権の1つである著作権とソーシャルメディアとの関係を見ていく。 3. 著作権 著作権は、著作者がその著作物に対して持つ権利である。そのため、親告罪(告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪)となっている。
著作権は「著作権法2条1項1号」において、次のように定義されている。 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 |
「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とあるので、ソーシャルメディアを使って表現した文章、写真、動画、絵なども著作権法上の著作物に該当しうる。
ソーシャルメディアを使うときに、不用意に他人の著作物を利用すると著作権法違反として訴えられる可能性があるということだ。
著作物についてもう少し具体的に見ていく。
「著作権法10条(著作物の例示)」では、次のように著作物の例示がされている。 (著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
|
このうちいくつかを、ソーシャルメディアでの利用という点で見ていく。
「一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 」に関しては、TwitterやFacebookなどで中心的に利用される文章が当てはまる。しかし文章でも、単なる事実だけではなく、「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要がある。たとえば、「富士山は3,776メートルである」というのは単なる事実にすぎないので、著作物にはならない。
「二 音楽の著作物」、「三 舞踊又は無言劇の著作物」、「七 映画の著作物」 に関しては、 YouTubeをはじめとした動画投稿サイトで勝手に音楽、ダンスの振り付け、映画、アニメーションなどの音声、映像を流したりすると著作権法違反になる。楽曲の歌詞などを文字として流す場合も同様である。
「四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」は、絵画、版画、彫刻以外にもマンガ、イラストなども入る。そのため人気があるアニメキャラクターはインターネット上にも多く存在しているが、勝手に使用するのは問題がある。著作権者は誰なのかについてあらかじめ調べておく必要がある。
「八 写真の著作物」に関しては、写真を使用するソーシャルメディアで気を付ける必要がある。 例えばFacebookに写真を掲載することがよくあるが、そのときに自分で撮った写真や、写真を撮った人の許可を得ているものならば問題はない。しかし著作権者が不明の場合には、掲載を見送った方が良いだろう。
これら以外にも「六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」や「九 プログラムの著作物 」も、ソーシャルメディアで使われる可能性があると思われる。
○著作権法の権利
著作権法は権利の束と言われ、大きく「著作権」、「著作者人格権」、「著作隣接権」の3つに分類できる。その中の著作権については、以下のような権利で構成される。 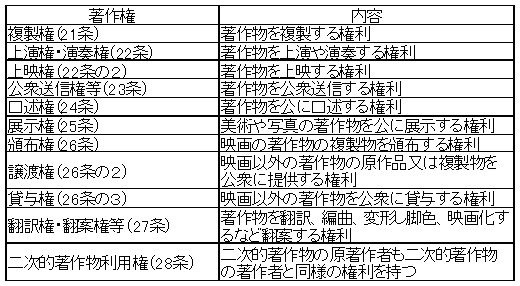
特にソーシャルメディアと関係が深い権利としては、複製権、公衆送信権等、翻訳権・翻案権等、二次的著作物利用権がある。
○著作権法違反の例
ソーシャルゲームについて、著作権侵害を認めた例が最近出た。
GREEは、Mobageを運営するDeNAを釣りゲームを真似したとして訴えた。東京地裁(阿部正幸裁判長)は2012年2月23日ソーシャルゲームについて著作権侵害を認め、DeNAに対し釣りゲームの配信差し止めと約2億3千万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
○"tsudaる"と著作権
"tsudaる"という造語がある。これは、ジャーナリストの津田大介氏が始めたとされるもので、Twitterで「社会問題上重要度の高いカンファレンスにオンライン状態で出席し、現場で発表された発言の140字要約postをTwitterのTimeline上に送り続ける行為※1」である。
ここでカンファレンスは著作物にあたるので、この"tsudaる"という行為が著作権法の違反に該当するかという問題がある。
著作権法違反になる要件として、著作物と全く同じであることは必要とされない。例えば、ですます調をである調に変更したとしても、内容、文脈などが変わっていなければ、著作権法違反になってしまう。
"tsudaる"場合、講演者のすべての言葉をTwitter上で流す訳ではなく、適宜内容を要約している。そのため、著作権侵害にはならない場合が多いと思われる。
しかし、パネルディスカッションで、複数の人がやり取りするような場合、それぞれの個々人の発言をほぼそのままの形で、Twitterで流してしまうと、著作権法違反になるという見解もあるようである。
他人の著作物を利用しても著作権法違反にならない例外がある。それが引用である。
引用は、著作権法32条1項に次のように定義されており、著作権者に断る必要はない。(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
この解釈であるが、最高裁判所昭和55年3月28日判決※2によれば、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」とされる。つまり、自分が作成する文章の中で、他人が書いた文章を使用することである。他人の文章だけを独立して使用することはできない。
逆に、イベントによっては、録画録音禁止、などを掲げている場合があるがこのようなときに"tsudaる"のは避けるべきである。有料イベントについても同様である。
また文化庁によれば、適切な「引用」と認められるためには、以下の要件が必要とされる。※3 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) |
(1)では引用には「必然性があること」とあり、自分の著作物において意見などを主張するときに、その引用が、自分の主張の論拠として自然につながっている必要がある。
また、(3)では「主従関係が明確であること」とあるので、引用部分はあくまでも従であり、自分の意見を補完するものである必要がある。また、引用する量も自分の文章の量と比較して、適切であることが求められる。
(2)で、「自分の著作物と引用部分とが区別されていること」とあるので、TwitterやFacebookなどで他人の投稿に対して、自分の意見を加える必要がある場合は、その引用部分を括弧で囲むなどして、自分の意見と明確に区別できるようにしておく必要がある。
また、(4)で「出所の明示がなされていること」とあるので、名前(ID)やリンクが必要ということになる。 4. 著作隣接権 著作権は著作物を作った人が持っているが、その著作物に密接に関連した権利として著作隣接権がある。
著作隣接権は、楽曲を演奏する人(実演家)や、それを録音するレコード製作者、そしてそれを放送する放送事業者や有線放送事業者などが保持している権利である。実演は著作権法2条1項3号に次のように定義されている。
第二条
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 |
実演者はこの条文に定義されている実演をする人である。実演者は必ずしも、プロとは限らず素人の場合もある。従って演奏を行っている人を撮影し、YouTubeなどにアップする場合に、その演奏を行っている人との間に、著作権法上の問題が発生しないように確認が必要になる。
レコード製作者は著作権法2条1項5,6号に次のように定義されており、楽曲などをCDにする人だけではなく、著作権で保護されていない音を録音することも含まれる。
第二条
五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 |
そのため、YouTubeなどへ投稿されている他の人が録音した音をそのまま利用すると、著作隣接権違反となる。
放送事業者は、「複製権」、「再放送権及び有線放送権」、「送信可能化権」、「テレビジョン放送の伝達権」といった権利を持っている。有線放送事業者もほぼ同様に、「複製権」、「放送権及び再有線放送権」、「送信可能化権」、「有線テレビジョン放送の伝達権」などの権利を持つ。そのため、たとえばテレビで録画したものをYouTubeやSNSに投稿したいのならば、その動画の著作隣接権を持っている放送事業者や有線放送事業者などの権利者の許可を得ることが必要になる。 5. 特許権 最近特許戦争という言葉を新聞やテレビでもよく目にするようになった。。
特許戦争はソーシャルメディア企業よりも先にソーシャルメディアのプラットフォームになるスマートフォンなどのモバイル機器企業の間で勃発した。そのため、これらモバイル機器を製造している企業が保持している特許は、FacebookやTwitterなどソーシャルメディア企業が保持している特許より多い。ソーシャルメディア企業も特許絡みの訴訟が増えてきており、その防衛対策として特許申請、取得の数を増やしているようである。
○モバイル機器企業の特許侵害訴訟の例
2011年4月15日、米アップル社はサムスン電子社のスマートフォン「Galaxy S 4G」のデザインが「iPhone」の模倣であり、また「iPad2」を模倣するため、故意にタブレット「Galaxy Tab」の発売を遅らせたとして、特許権及び商標権侵害で米・カリフォルニア州地方裁判所に提訴した。
それに対して、2011年4月22日サムスン電子社はアップル製品がデータ分析転送や電力制御、無線データ通信など10件の特許侵害しているとして、ソウル中央地方裁判所、独マンハイム裁判所、東京地裁に提訴した。さらに同年4月27日には、サムスン電子社はアメリカでも米アップル社を提訴した。
その後、互いに訴訟を行っており、日本、アメリカ、韓国、オランダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、イギリスなど30以上の国で特許訴訟を行っているようである。
特許侵害に関しては、米アップル社とサムスン電子社以外にも、図1のように、複数の企業が互いにそれぞれを訴えている。 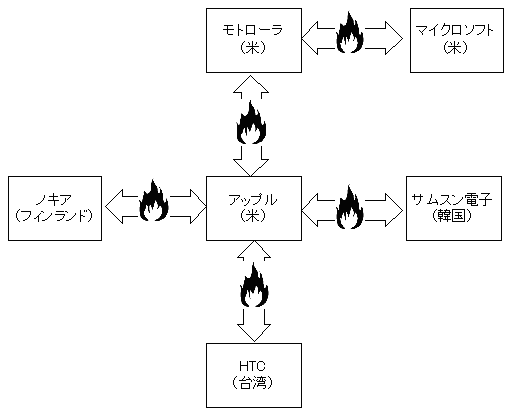
図 1 モバイル機器企業特許戦争関係図
ガイドラインは、社員の就業規則にのっとっているものが多い。その上に、炎上を避けるためのソーシャルメディア上の注意点などを追加している。 ○ソーシャルメディア企業の特許の例
SNSを運営する米Friendster社は2006年7月7日、SNSに関する米国特許を取得した。「ソーシャルネットワーク内でのユーザーの関係に基づいたオンラインコンピュータシステムで、ユーザーを接続するシステム、方法、装置」(特許番号7069308)である。これ以外にも米Friendster社は、ソーシャルネットワーク関係の特許をいくつも取得している。これらの特許は、米Friendster社が、SNSの黎明期に取得したもので、非常に広範囲で、一般的なものと言える。 2010年の4月にFacebook社は、Friendster社の18件の特許を、約4,000万ドルで買い取っている。
Facebook社は、自分でも特許を取得している。たとえば、New Feedに関する特許を2010年2月23日に米国で取得した。(特許番号7669123)Facebook社はこの特許を日本においても、「ソーシャルネットワークのユーザについてのニュース配信を動的に提供するシステムおよび方法」(特許番号4866463)として、2011年11月18日に取得した。
New Feedとは、自分の"友達"が「いいね!を押した」、「プロフィールを更新した」、「写真を投稿した」、「誰かと"友達"になった」などの情報を時系列で表示する仕組みのことである。
このNew Feedの技術に関しても、Twitter、mixi、LinkedInなどで一般的に使用されている。New Feedの特許取得はFacebook社が他社を訴えるというよりも、自社を訴えられないための防衛手段としての側面が強いと思われる。
そのFacebook社であるが、2012年3月12日に、米Yahoo!社からカリフォルニア州サンノゼの米連邦地方裁判所に特許侵害で提訴された。米Yahoo!社はFacebookの基本機能の実現に、広告モデル、プライバシー設定、カスタマイゼーション、メッセージング、ソーシャル機能に関連する10件の特許技術が含まれている、と主張している。米Yahoo!社はFacebook社に対してロイヤリティの支払のみならず損害賠償の支払も請求している。
一般的に、特許侵害の訴訟に対する対抗策として、自社が保持している特許により反訴する方法がある。しかし、Facebook社は、米Yahoo!社と比較して保有している特許の数が少なかった。米Yahoo!社の3,300以上に対して、2011年12月31日の時点で56件の特許ならびに503件の特許出願を持っているにすぎなかった。
そこで、Facebook社は、対策としてIBM社の特許750件を買収した。750件には特許以外の権利も含まれており、純粋な特許の数はそれより少ないようである。特許の内容についても、詳細は公開されていないが、ソーシャルメディアに限らず、広範な技術領域を包含しているということである。
これによりFacebook社は2012年4月3日米Yahoo!社を米カリフォルニア州北地区連邦地方裁判所に提訴した。Facebook社は、ホームページ、コンテンツ最適化、写真共有機能、広告サービスなどFacebook社が持つ10件の特許を米Yahoo!社が侵害している、と主張した。Facebook社が主張する10件の特許のうち、Facebook社による発明は2件だけで、それ以外はIBM社など他社から買収したものである。
そして、まさにこの原稿を書き終えようとしていた4月23日に、Facebook社が米マイクロソフト社から約650件の特許を総額5億5000万ドル(約450億円)で買い取ることで合意したというニュースが入ってきた。
実は、日本の企業もSNSに関する特許でFacebook社を訴えている。
株式会社メキキ及びメキキ・クリエイツ株式会社は、2001年10月に「 MekikiCity (現サムライフィールドネットワーク)」というSNSを立ち上げ、サービス開始時に、日米で特許を取得していた。
2009 年 10 月 7 日、株式会社メキキ及びメキキ・クリエイツ株式会社はFacebook社を相手取り「既存のコンタクトを通じて"友達"を識別する方法を含めた基本特許」侵害に関して、訴訟を起こした。※4
同様に、日本のベンチャー企業であるイーパーセル社は、米テキサス州で2011年4月に、米Google社、米Yahoo!社、AOL社など13社を特許権侵害で訴えた。必ずしもソーシャルメディアだけに関係する特許ではないが、データの受信を通知画面で表示する機能(ポップアップ)など、インターネット産業には欠かせないものが多い。その為、訴えられた企業のうち数社は既に和解しライセンス契約を結ぶなど、イーパーセル社は事実上の勝利をおさめている。
その他に、ソーシャルメディア絡みの特許で知っておきたいものとして、2010年6月15日に、米Amazon社が取得した特許がある。(特許番号7739139)※5これにもSNSで一般的に利用されている内容が含まれており、その影響が注目されている。 6. プライバシー権、肖像権、パブリシティ権 プライバシー権とは、私生活上の事柄を公開されない権利のことである。サミュエル・D・ウォーレン氏とルイス・ブランダイス氏がHervard Law Reviewの論文にて提唱し、法的に独立した権利だと考えられるようになった。
その後、プライバシー権は、自分の情報をコントロールする権利という積極的な面もあると考えられるようになった。
日本でもプライバシー権は法律で明確に定義されたものではないが、「宴のあと」裁判※6において、憲法13条で保障されている人格権としてプライバシー権を認めている。
個人情報の保護に関する法律※7は、私生活上の事柄を公開されない権利を規定すると共に、個人情報のコントロール(第三者への提供制限、訂正請求、開示請求など)について規定している。
肖像権はプライバシー権の一部と考えられている。自分の姿を他人に使用されない権利である。人格権としての側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権的な側面(パブリシティ権)がある。
イベントや飲み会で参加者同士写真を撮り、それをFacebookなどに載せるようなことが良く行われるが、Facebookを利用していない人は写真を撮られてもそれが公開されるとは思っていない。写っている人や場合によっては店の了承を得ないでFacebookに載せることは控えたほうが良いだろう。
また風景を撮ろうとして人が入り込む場合は、遠くから顔が分からないように写したり、足元だけを写すなどの工夫が必要になる。
Google ストリートビューはGoogle社が提供しているWebサービスの1つで、道路沿いの風景がパノラマ写真で表示されるものである。住宅地も写るのでプライバシーの侵害だという声が多く上がった。
これに対してのGoogle社の主張は「全て公道から見ることができるものであり問題ない」というものである。しかし人物の撮影(肖像権)に関しては、自動認識プログラムでぼかしを入れるなどの対応をすることになっている。
肖像権は人物を対象としており、建造物は対象としていない。著作権法でも、建造物に関しては複製の禁止(46条)しか規定していない。従って、著作権法においても、建造物の撮影は許されることになる。しかし、敷地の中に入って無断で撮影することはもちろん、建造物内部に写真撮影禁止が謳われている場合は、違法行為となる可能性がある。
パブリシティ権とは有名人の氏名や肖像が持つ、経済的な価値を保護する権利をいう。
2012年2月2日、ピンク・レディーが、週刊誌「女性自身」に写真を無断掲載され、パブリシティ権を侵害されたとして、損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)※8は、
「肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」という。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由来する権利の一内容を構成するものということができる。」とパブリシティ権の存在を認めている。しかし、著名人に関しては受忍すべき場合もあるとした上で、次の様に、具体的にパブリシティ権を列挙している。
「肖像等を無断で使用する行為は,①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,③肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」
このように、著名人の顧客吸引力を商品の宣伝などに直接利用するとパブリシティ権を侵害することになる。従って、USTREAMなどの動画や、FacebookPageなどの投稿の写真において、著名人の肖像や氏名を無断で宣伝に利用すると、損害賠償を請求される可能性がある。
7. おわりに ソーシャルメディアと著作権や特許権などの知的財産権、プライバシー権などの権利について、解説をおこなった。著作権についてはまだ世間では、その理解が十分ではなく、厳密に見ると著作権法違反のケースが多数見受けられる。しかし大多数が行っているから大丈夫であろうと判断するのは非常に危険である。
ソーシャルメディアに関する特許件数に関しては、現状はまだそれほど多いとは言えない。しかし、特許に関する訴訟も増えてきており、ソーシャルメディア企業による、特許の取得や特許の買収などが今後増加することが予想される。そのためソーシャルメディア企業の今後の動向が注目される。 | 参考文献(リンク) | | | | ※1 | trickenさんの投稿 | | | http://ascii.jp/elem/000/000/428/428621/index-2.html | | ※2 | 最高裁判所第三小法廷昭和55年3月28日判決 裁判所公式 パロディ裁判 | | | | | ※3 | 文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項 | | | | | ※4 | Facebook,Incに対する米国訴訟提起について | | | | | ※5 | http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7,739,139.PN.&OS=PN/7,739,139&RS=PN/7,739,139 | | | | ※6 | 「宴のあと」裁判とは元外務大臣・東京都知事候補の有田八郎が、三島由紀夫の『宴のあと』という小説がプライバシーを侵すものであるとして、東京地裁に訴えたものである。判決は三島側に損害賠償を命じた。 | | | | ※7 | 個人情報の保護に関する法律は2003年5月に成立した。「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」(第一条より)ものである | | | | ※8 | http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120202111145.pdf | | |
*本Webマガジンの内容は執筆者個人の見解に基づいており、株式会社オージス総研およびさくら情報システム株式会社、株式会社宇部情報システムのいずれの見解を示すものでもありません。 |  「Googleの「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」の改訂について」
「Googleの「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」の改訂について」
 「ユーザーの行動や体験を意識したSEOへ」
「ユーザーの行動や体験を意識したSEOへ」
 「「サービス・イノベーションによるブランディング」と「おもてなしマインド」の関係について」
「「サービス・イノベーションによるブランディング」と「おもてなしマインド」の関係について」
 「昨今の商業施設をとりまく状況」
「昨今の商業施設をとりまく状況」
 「ソーシャルメディアの立ち位置」
「ソーシャルメディアの立ち位置」
 「ソーシャルメディアのエンタープライズ利用における注意点 第6回」
「ソーシャルメディアのエンタープライズ利用における注意点 第6回」
 「ソーシャルメディアを利用する企業の動向と事例 第4回」
「ソーシャルメディアを利用する企業の動向と事例 第4回」
 「業務プロセスにおけるソーシャルメディアを利用したサービス 第3回」
「業務プロセスにおけるソーシャルメディアを利用したサービス 第3回」
 「ソーシャルメディアの課題と形成する技術(ハードとソフト) 第2回」
「ソーシャルメディアの課題と形成する技術(ハードとソフト) 第2回」
 「ソーシャルメディアの位置づけと課題 第1回」
「ソーシャルメディアの位置づけと課題 第1回」