行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~
属人化や非効率がなぜ解消されないのか――。現場改善やDX推進の取り組みが頭打ちになっている企業では、これまでのアンケート調査やIoTデータでは見えにくい"行動の背景"に目を向ける必要があります。近年、工場などの製造現場を中心に、行動観察を通じて無意識の判断や作業手順を捉える動きが見られています。行動観察が適用できる領域は多岐にわたりますが、本記事では、属人化や技能伝承の課題を抱える企業に向けて、長期視点での行動観察調査の価値と導入方法、現場での活用事例を紹介します。
20年以上にわたる行動観察実績
 業務改善支援の資料ダウンロードはこちら
業務改善支援の資料ダウンロードはこちら
なぜ、現場改善は頭打ちになるのか?
製造現場では、IoTやセンサーデータ、作業標準書などを活用して業務の平準化が進められています。しかし、これらの取り組みだけでは行動の実態を十分に把握しきれず、改善が頭打ちになる原因となっています。
現場では、作業者が無意識にとっている些細な動作や判断が日常的に発生しています。たとえば、わずかに身体をひねる動き、迷ってから工具を選ぶ動作などは、センサーデータでは測りにくい"意味のある行動"です。加えてこういった行動の背景には、経験や習慣、環境要因など複数の要素が絡み合っており、表面的なデータだけでは理解が困難です。
さらに、作業標準書と実態との間にギャップがあることも珍しくありません。標準書通りに動いているように見えても、実際には各人が独自のやり方で補っている場合があります。そのような場合、より適切に進めるための行動なのか、標準から逸脱した行動なのかを見極める必要があります。
このような行動を見極めるには、行動観察が適しています。
長期視点の行動観察調査とは?――IoTでは見えない"現場の理由"をつかむ技法
行動観察調査は現場に入り込み、作業者や対象者の行動やコミュニケーション、周囲の環境を観察して、その背景や理由、潜在的な考えを捉える調査手法です。実際の行動に加え、現場での非言語的なコミュニケーションや、無意識の行動、そして作業環境が与える影響を把握するのに最適です。近年は製造業の現場改革をはじめ、UXリサーチや生活者行動を分析するマーケティング領域でも用いられています。作業者や対象者の言葉では説明しづらい行動などの特徴を明らかにすることで、現場特有の課題やニーズを発見するのに役立ちます。
行動観察は長期視点をもったうえで実施することが大切です。
「長期視点の行動観察調査」と聞くと、長期間にわたり現場に張り付き、継続的に観察を行うイメージをもたれるかもしれません。しかし実際には、調査自体は1〜2日など短期間で行われるケースがほとんどです。ポイントは、一度きりの調査で終わらせず、得られた"気づき"を長期的な改善や施策にどう活用していくかという点にあります。
たとえば、行動観察によって明らかになった現場の理由――なぜその手順になっているのか、なぜマニュアル通りに動けないのかなど――といった気づきは、単なる瞬間的なデータではなく、現場の構造的な課題や習慣に根ざしたものであることが多いのです。これらの気づきを起点に、業務改善や教育設計、マニュアル見直しと実施を行い、さらに2回目の行動観察調査を行います。
このように短いサイクルで、「調査・洗い出し・実施・再調査」のサイクルを長期間にわたり繰り返すことで、より本質的な成果が得られます。
IoTやログ分析では把握できない「なぜそうしているのか」という文脈や意味づけは、行動観察調査ならではの強みです。だからこそ、"長期にわたる実践的な改善"を支える基盤として、行動観察は高く評価されているのです。
さらに、行動観察にはリアルな現場での視点だけでなく、デジタル上の行動を分析する手法も含まれます。たとえば、顧客のWebアプリなどのオンライン上の動きやUI上の反応を分析するUXリサーチの場面でも使われており、「リアル+デジタル」の双方に適用できる柔軟性が行動観察の強みです。
行動観察調査で解決できる課題
行動観察調査をすることで、これまで見えなかった現場の課題が浮かび上がってきます。中でも特に注目すべきは、"隠れた無駄"の発見です。
たとえば、非効率な動線や不要な確認動作、手順の繰り返しなど、当事者は気づかないけれど、第三者には明確に映る改善ポイントが数多くあります。こうした気づきは、現場に可能な限り入り込んで馴染み、数時間から1日程度の観察を通じて得ることができます。
また、作業手順の属人化解消にも有効です。たとえば近年ではベテランと若手の技能の格差が課題となっていますが、観察によって、ベテラン特有の"勘"や"手さばき"を記録し、若手にも伝えられる形に落とし込むことで、技能伝承の断絶を防ぐ手助けとなります。作業者それぞれのスキルを明確にし、単なる作業標準書では表現しきれない"実践的な知恵"を再現可能な形に変えることで、標準化と柔軟性のバランスがとれた現場運営が可能になります。
このように、行動観察は定量的なデータでは把握できない"現場のリアル"を可視化し、現場改善や業務改革の出発点をつくる強力な武器となります。
現場導入の進め方――課題特定から改善提案までのステップ
行動観察を導入する際には、まず調査の目的を明確にし、対象業務を選定することが重要です。たとえば、属人化が進んでいる工程や、改善効果が頭打ちになっている業務など、課題が顕在化している領域を選ぶことで、観察の価値が高まります。
次に、調査対象者を設定し、観察の同意を得たうえで実施に移ります。信頼関係を築きながら、詳細な行動記録を収集していくことが重要です。また、記録の仕方にも工夫が必要です。デジタル機器の使用とアナログな記録方法を併用することで、より多角的なデータが得られます。紙とペンだけでなく、ビデオや録音、スケッチなど複数の手法を組み合わせて、現場の空気感や対象者の自然な動きを捉えることが求められます。記録をもとに分析を行い、行動の背景にある意図を抽出したうえで、具体的な改善提案や教育施策に落とし込むプロセスが続きます。
この一連のプロセスは、単なる観察ではなく「気づきと再構築」を行うことに意味があります。
現場での多様な気づきが、その後の分析に大きく影響し、結果改善策にも影響を与えることになります。
導入事例:
実際の現場では、行動観察によって大きな成果を得た例が複数あります。ある現場ではメンバー間で作業品質に対しての意識が「前向きに取り組んでいる」や、「元請の指示があったから取り組んでいる」などばらついていました。観察を実施すると、それが実際の行動にもあらわれていることがわかりました。たとえば、KY(危険予知活動)が形骸化しているグループと、KYを朝だけではなく昼も行う工夫をしているグループがあるなど、行動の違いが見られました。観察の結果をメンバー間で共有し、目標設定とアクション・振り返りを実施することで意識が高くないグループが「この問題は大切なので考えましょう」など、自ら課題解決をしようとするような発言があらわれるなど意識の向上が見られるようになりました。
また、別の現場では、作業の効率をさらにあげたいという課題がありました。行動観察では実際の作業の様子を観察し、アナログで、かつ手順が多い作業や、微調整を繰り返すために同じ場所を往復するような作業が含まれていることがわかりました。たとえば、「部材を作り出すために、その部材を使う場所で寸法を測っては、加工する場所へ行き切り出しや微修正を何度も行う」といった作業です。これらの作業に対し、改善のためのアイデアを出せたのは行動観察の大きな価値です。
行動観察調査の注意点と対応策
行動観察は非常に有効な手法である一方で、3つの注意点があります。
注意点①: 普段通りの行動が観察しにくい可能性
調査対象者が"観察されている"ことを意識しすぎると、普段通りの行動をとれなくなる可能性もあります。
対応策: 対象者の緊張を解き、観察者が存在を意識されないポジションをとるなどの工夫が必要です。現場への影響を最小限に抑えながら、最大限の情報を引き出すためのスキルと配慮が求められます。
注意②: バイアスが観察や分析を阻害する
観察時や分析時には「こうあるはず」「こうに違いない」などの思い込みや無意識に都合のよい行動だけをとり上げたり、都合よく解釈をしてしまうことがあります。
対応策: 観察時や分析時に起きるバイアスなどの心理的特性を理解したうえで、そこに陥らないように注意をしながら実施することが大切です。
注意③: 明確な答えが得にくい
定量的な手法と比べて、明確な答えを得にくいことが挙げられます。また、観察結果の解釈には主観が入りやすいため注意が必要です。
対応策: 行動観察分析には客観的に捉え、事実に基づいて分析することが重要です。そうすることで、よりよい業務改善や技能伝承へとつながります。また、分析には経験やチームでの議論が欠かせません。
このように行動観察の専門的な知識やスキルをもって実施することで、より本質的な成果につながります。
まとめ: 現場を"見に行く"ことで、改革は再び動き出す
行動観察調査は、従来の数値データでは見えなかった"現場の真実"をしる有効な手段です。属人化や非効率、技能伝承といった複雑な課題に直面している現場ほど、その価値は大きくなります。机上の改善案ではなく、現場で本当に機能する仕組みをつくるためには、まず"目で見る"ことから始めるべきです。デジタルで現場が見えにくくなっている時代だからこそ、行動観察というアナログな技法が現場改革の突破口になる時代が、いま来ています。自社にとって最適な調査方法を選ぶことが、継続的な運用と成果の鍵となります。
行動観察調査を長期にわたって行うことは、現場での問題点や改善のヒントを見つけるために非常に有効です。日々のルーチンや職場の文化に根付いた課題を明らかにすることができます。これにより、現場の効率化や安全性の向上につながり、最終的には全体の生産性向上を実現するでしょう。
行動観察で現場改善したい方へ
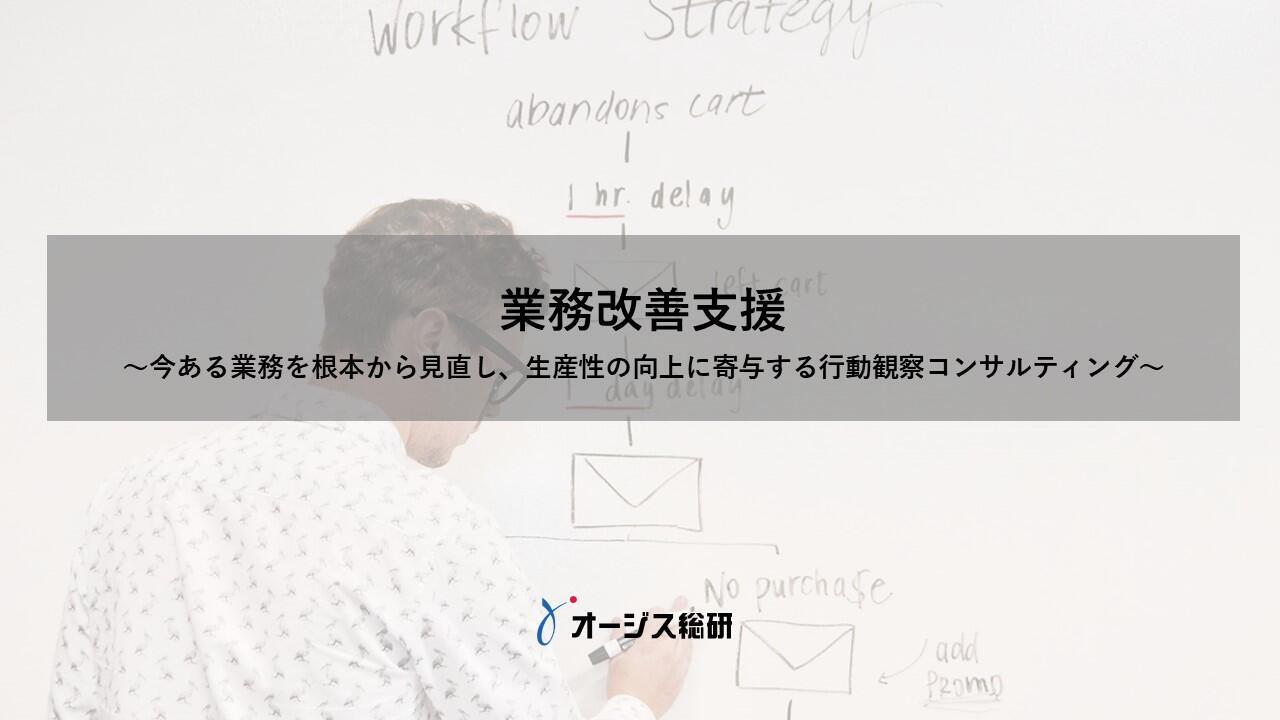
業務改善支援の資料でわかること
・行動観察が必要な理由
・行動観察が適している理由
・オージス総研の行動観察の特徴
・事例
など
2025年7月10日公開
※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連サービス
関連記事一覧
 「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する
「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する 新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説
新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説 "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践
"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 安全を優先する組織文化を作るために
安全を優先する組織文化を作るために 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解
新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解
~顧客理解=人間理解のススメ~ 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~
「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方
良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  現場の安全性向上を目的とした行動観察
現場の安全性向上を目的とした行動観察 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント
業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣
新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説
成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 ウェアラブル端末導入による仮説生成
ウェアラブル端末導入による仮説生成 プロが解く観察力の鍛え方 第3回
プロが解く観察力の鍛え方 第3回
あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? プロが解く観察力の鍛え方 第2回
プロが解く観察力の鍛え方 第2回
気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~
Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回
プロが解く観察力の鍛え方 第1回
「気づき力」を高めるために必要な2つのこと
ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性
 安全性診断サービス
安全性診断サービス 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」
新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 360度カメラ映像による行動観察
360度カメラ映像による行動観察 DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~
DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ 行動観察×AI
行動観察×AI 「気づき」について考える【前編】
「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】
「気づき」について考える【後編】 デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ
デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ リスクマネジメントと現場の気づきの重要性
リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ
ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ カスタマージャーニーマップ作成のポイント
カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性
「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること
成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること
潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上
 ワークショップによる本質的なソリューションの創造
ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造
デザイン思考と新価値創造 新たな価値創造のための3つのヒント
新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント
安全品質の向上のための3つのヒント 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター
鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -
"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット
鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」
自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 コミュニケーションについての定性調査のデータを公開
コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く
日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 70代を迎える団塊世代の兆しを探る
70代を迎える団塊世代の兆しを探る リフレームに必要な3つの「マインドセット」
リフレームに必要な3つの「マインドセット」 アナログは今後どうなるのか
アナログは今後どうなるのか 「わからない」に触れる価値
「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える
「リフレーム」について考える
会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」
 「インサイト」について考える【後編】
「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】
「インサイト」について考える【前編】 「返報性」のキャッチボール
「返報性」のキャッチボール 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?
赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性
グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 ブランディングとしての組織づくり
ブランディングとしての組織づくり パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?
パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮
京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私
ジムとモチベーションと私 「ゆるくつながる」
「ゆるくつながる」 ロボットのいる社会から人の社会を見る
ロボットのいる社会から人の社会を見る
