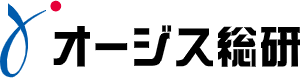第80回 自国中心主義の行きつく果て:「意図せざる結果」としての共貧
2017.03.21 山口 裕幸 先生
世界的には、自国第一主義が声高に叫ばれ、支持を集める傾向が強まっているといえるだろう。イギリスのEU離脱を決めた国民投票の結果、アメリカ大統領戦でのトランプ氏の勝利は、それを象徴する出来事といえる。オランダ下院選挙においても極右政党の自由党が第一党に躍進するのではないかと注目されていたが、こちらはそれほどの勢いを示す結果にはならなかった。とはいえ、今後もフランス大統領選やドイツ連邦議会選挙が控えており、自国第一主義を標榜する政治家や政党にどれほどの支持が集まるのか気になるところである。
 自国第一主義のどこが問題なのか?という疑問を感じる人もいることだろう。どの国も自国民が納付する血税によって営まれているのであって、自国の利益を最優先に考えることは至極まっとうなことだといえるだろう。しかしながら、トランプ大統領の主張にしばしば登場する「アメリカ人の雇用を守るために、日本の自動車会社はアメリカに工場を造るべきだ」という意見を聞くと、なんとなく「なぜ日本の企業がアメリカ人のために工場を造る必要があるのだろうか?」と感じてしまう。そして、「そっちがアメリカ第一主義なら、こっちも日本第一主義に徹するまでだ!」といった感情の方が先走ってしまうことさえあるだろう。
自国第一主義のどこが問題なのか?という疑問を感じる人もいることだろう。どの国も自国民が納付する血税によって営まれているのであって、自国の利益を最優先に考えることは至極まっとうなことだといえるだろう。しかしながら、トランプ大統領の主張にしばしば登場する「アメリカ人の雇用を守るために、日本の自動車会社はアメリカに工場を造るべきだ」という意見を聞くと、なんとなく「なぜ日本の企業がアメリカ人のために工場を造る必要があるのだろうか?」と感じてしまう。そして、「そっちがアメリカ第一主義なら、こっちも日本第一主義に徹するまでだ!」といった感情の方が先走ってしまうことさえあるだろう。
「自分のためにあなたが協力(貢献)すべきだ」と、お互いが言い始めると、なんともどぎついやりとりになってしまう。単に雰囲気がどぎついものになるだけでなく、お互いが損をして、最後には「共貧」という「意図せざる結果」に行きつく可能性が非常に高いのである。このことは本コラム第43回で紹介した「囚人のディレンマ」の論理を、個人対個人から国家対国家に置き換えて考えてみることで理解できるだろう。
「囚人のディレンマ」は、1対1の個人どうしが、競争(利己的行動選択)と協同(相互の利益を考慮した行動選択)のどちらを選択するのかを検討するのにすぐれたゲーム・シミュレーションである。よほどの信頼関係がないと、どうしても人間は自己利益を優先する行動、すなわち競争を選択してしまいがちなのだが、お互いが競争を選択すると、結局のところ、お互いに協力し合うよりも互いが損をしてしまう状況に陥るのである。
しかし、それはゲーム理論的にそのように設定されているからであって、設定はいくらでも多様に存在しうるはずだという意見もあるかもしれない。そこでもうひとつ「共有地(コモンズ)の悲劇」の例も紹介しておこう。これはアメリカの生物学者ハーディン(Hardin, 1968)が指摘した現象で、この指摘は社会学や経済学にも大きな影響を及ぼしている。
牧草地の周辺に複数の酪農家が羊を飼っていたとしよう。この牧草地はオープンアクセスの共有地であって、どの酪農家も自分の羊を連れていって、その牧草を食べさせることができる。酪農家としては、自分の飼う羊を増やしたいので、共有地の牧草をどんどん食べさせることになる。遠慮していると他の酪農家がその羊たちに共有地の牧草を食べさせてしまうため、どの酪農家も競って共有地の牧草を自分の羊に食べさせることになる。その結果、牧草は根こそぎ羊たちに食べ尽くされてしまい、共有地は草ひとつ生えない荒れ地に変わってしまう。それまで共有地の牧草を食べさせることで羊を飼っていた酪農家たちは、自前で牧草を育て、食べさせていかねばならず、結果的に全ての酪農家は被害を受けることになってしまう。
 天然資源の枯渇、地球温暖化などの現象も、根底には互いが自己利益を追求し、競争する心理が重要な役割を果たしている。「国富論」の中でアダム・スミスが論じたように、個々人の競争は、それが市場経済という枠組みの中では、「見えざる手」によって社会全体の利益となる望ましい状況を生み出すこともあるだろう。しかし、なんらの手だてもないままに互いが自己利益の主張と追求に走れば、「共有地の悲劇」につながる可能性があることは常に気にかけておきたい。
天然資源の枯渇、地球温暖化などの現象も、根底には互いが自己利益を追求し、競争する心理が重要な役割を果たしている。「国富論」の中でアダム・スミスが論じたように、個々人の競争は、それが市場経済という枠組みの中では、「見えざる手」によって社会全体の利益となる望ましい状況を生み出すこともあるだろう。しかし、なんらの手だてもないままに互いが自己利益の主張と追求に走れば、「共有地の悲劇」につながる可能性があることは常に気にかけておきたい。
我々の祖先は、互いが利己的に振る舞うことで生じる「損」には敏感に気づいていたのだろうと考えられる。「情けは人のためならず」ということばが継承されてきた背景には、情けをかけて人助けをすること、自分には得はなくてもみんなに協力することは、そのときだけ考えれば損なのかもしれないが、巡りめぐって将来には自分が助けて貰う「得」にもつながる、という先人たちの現実的な智恵が込められているように思う。自国の利益のためにも、他の国々との協力関係を大切に育んでいく協同の心がけは不可欠なものだといえるだろう。
引用文献
Hardin, G. (2009). The Tragedy of the Commons*. Journal of Natural Resources Policy Research, 1(3), 243-253.
※先生のご所属は執筆当時のものです。
-
 第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか?
前の記事へ
第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか?
前の記事へ
-
第81回 自国第一主義は自国民を守るか-集団主義に関する社会心理学的研究をふまえて-
次の記事へ

関連記事一覧
 第182回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(3)〜 メンバーによるリーダーシップ評価の良し悪しは、行動よりも結果次第? 〜
第182回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(3)〜 メンバーによるリーダーシップ評価の良し悪しは、行動よりも結果次第? 〜 第181回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(2)〜 皆で情報交換したのにそれが活かされない!『隠されたプロフィール』現象 〜
第181回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(2)〜 皆で情報交換したのにそれが活かされない!『隠されたプロフィール』現象 〜 第180回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(1)〜 自分自身をごまかしてしまう認知的不協和解消への動機づけ 〜
第180回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(1)〜 自分自身をごまかしてしまう認知的不協和解消への動機づけ 〜 第179回 優れたパフォーマンスを達成するチームづくりの要について考える
第179回 優れたパフォーマンスを達成するチームづくりの要について考える 第178回 社会問題への不満の高まりは攻撃と排斥によって解消されるか
第178回 社会問題への不満の高まりは攻撃と排斥によって解消されるか
 第177回 世代による考え方の違いから生まれる組織内葛藤を克服するマネジメントを考える ~ 社会的アイデンティティ研究を参考に ~
第177回 世代による考え方の違いから生まれる組織内葛藤を克服するマネジメントを考える ~ 社会的アイデンティティ研究を参考に ~
 第176回 葛藤を乗り越える交渉のあり方について ~ 日米間の関税をめぐる交渉の経緯を社会心理学の視点から振り返りつつ ~
第176回 葛藤を乗り越える交渉のあり方について ~ 日米間の関税をめぐる交渉の経緯を社会心理学の視点から振り返りつつ ~  第175回 ストレスに悩む管理職の気構え転換戦略 ~ 問題解決型のストレス対処から情動焦点型のそれへ ~
第175回 ストレスに悩む管理職の気構え転換戦略 ~ 問題解決型のストレス対処から情動焦点型のそれへ ~ 第174回 コンプライアンス時代における管理職の行動戦略~叱咤激励か、慰労し承認するか、それが問題だ~
第174回 コンプライアンス時代における管理職の行動戦略~叱咤激励か、慰労し承認するか、それが問題だ~ 第173回 生成AIによる人事評価はメンバーのモチベーション向上につながるか~対人認知に関する社会心理学的研究の視点から~
第173回 生成AIによる人事評価はメンバーのモチベーション向上につながるか~対人認知に関する社会心理学的研究の視点から~ 第172回 合従連衡による多数派形成は紛争を解決に導くか~パワーダイナミクスに関する社会心理学的研究の視点から~
第172回 合従連衡による多数派形成は紛争を解決に導くか~パワーダイナミクスに関する社会心理学的研究の視点から~ 第171回 強さを背景に利己的に振る舞う相手には、どのように対応すれば良いのだろうか~紛争に関する社会心理学的研究の視点から~
第171回 強さを背景に利己的に振る舞う相手には、どのように対応すれば良いのだろうか~紛争に関する社会心理学的研究の視点から~ 第170回 日本の組織で仕事の効率が上がらない理由を考える~社会心理学的視点から~
第170回 日本の組織で仕事の効率が上がらない理由を考える~社会心理学的視点から~ 第169回 時代を超えて効果的リーダーシップの中核にあるもの~変革型リーダーシップ論を踏まえて~
第169回 時代を超えて効果的リーダーシップの中核にあるもの~変革型リーダーシップ論を踏まえて~ 第168回 混沌とした状況におけるリーダー行動について考える~ライフサイクル理論の視点から~
第168回 混沌とした状況におけるリーダー行動について考える~ライフサイクル理論の視点から~ 第167回 挑戦心の源について考える~やる気を見せない従業員や部下の挑戦心に火をつけるには~
第167回 挑戦心の源について考える~やる気を見せない従業員や部下の挑戦心に火をつけるには~ 第166回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(3)~部下が抱く管理職への「暗黙の期待」との向き合い方~
第166回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(3)~部下が抱く管理職への「暗黙の期待」との向き合い方~ 第165回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(2)~対話と調整に基軸を置くリーダー行動と組織の混沌~
第165回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(2)~対話と調整に基軸を置くリーダー行動と組織の混沌~ 第164回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(1)~「もの言う」動機づけにブレーキをかける職場の権威勾配~
第164回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(1)~「もの言う」動機づけにブレーキをかける職場の権威勾配~ 第163回 国際化が進む日本社会における人々の心理について考える
第163回 国際化が進む日本社会における人々の心理について考える 第162回 組織の中の世代間意識ギャップについて考える
第162回 組織の中の世代間意識ギャップについて考える 第161回 人手不足解消への道筋を考える(4)~女性を積極的に雇用するアプローチ~
第161回 人手不足解消への道筋を考える(4)~女性を積極的に雇用するアプローチ~ 第160回 人手不足解消への道筋を考える(3)~海外からの労働者を積極的に雇用するアプローチ~
第160回 人手不足解消への道筋を考える(3)~海外からの労働者を積極的に雇用するアプローチ~ 第159回 人手不足解消への道筋を考える(2)~高齢者を積極的に雇用するアプローチ~
第159回 人手不足解消への道筋を考える(2)~高齢者を積極的に雇用するアプローチ~ 第158回 人手不足解消への道筋を考える(1)~不本意な離職を少なくしていくアプローチ~
第158回 人手不足解消への道筋を考える(1)~不本意な離職を少なくしていくアプローチ~ 第157回 組織的不祥事が繰り返し起こる理由を考える~「組織ならでは」の心理学的特性を視野に入れつつ~
第157回 組織的不祥事が繰り返し起こる理由を考える~「組織ならでは」の心理学的特性を視野に入れつつ~ 第156回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか(2)~多様性豊かな組織の強みを引き出す包摂的リーダーシップ~
第156回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか(2)~多様性豊かな組織の強みを引き出す包摂的リーダーシップ~ 第155回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか~ネガティブ・フィードバックの大切さに着目して~
第155回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか~ネガティブ・フィードバックの大切さに着目して~ 第154回 「部下を動かす」力について考える~監督と管理者の違いに注目しながら~
第154回 「部下を動かす」力について考える~監督と管理者の違いに注目しながら~ 第153回 意識や行動を変える「力」について考える ~自律的に変化を作り出す力はどこから来るか~
第153回 意識や行動を変える「力」について考える ~自律的に変化を作り出す力はどこから来るか~ 第152回 心理の世界で働く「慣性の法則」について考える ~変わ「ら」ないのか、変わ「れ」ないのか~
第152回 心理の世界で働く「慣性の法則」について考える ~変わ「ら」ないのか、変わ「れ」ないのか~ 第151回 AI(人工知能)の飛躍的進歩と人間の働き方
第151回 AI(人工知能)の飛躍的進歩と人間の働き方 第150回 管理職に求められるリーダーシップ行動の変容 〜指示・命令から傾聴そして支援へ〜
第150回 管理職に求められるリーダーシップ行動の変容 〜指示・命令から傾聴そして支援へ〜 第149回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(8) 〜「集団主義」的傾向のダークサイド、ブライトサイド〜
第149回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(8) 〜「集団主義」的傾向のダークサイド、ブライトサイド〜 第148回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(7) 〜自己卑下的に発言し、振る舞うことの影響〜
第148回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(7) 〜自己卑下的に発言し、振る舞うことの影響〜 第147回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(6) 〜ランキングに一喜一憂?〜
第147回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(6) 〜ランキングに一喜一憂?〜 第146回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(5) 〜リスク・コミュニケーションの難しさ〜
第146回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(5) 〜リスク・コミュニケーションの難しさ〜 第145回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(4) 〜リスクをできるだけ回避しようとする傾向〜
第145回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(4) 〜リスクをできるだけ回避しようとする傾向〜 第144回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(3) 〜資産形成は投資よりも貯金を優先する傾向〜
第144回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(3) 〜資産形成は投資よりも貯金を優先する傾向〜 第143回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(2) 〜“ガラパゴス化”について〜
第143回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(2) 〜“ガラパゴス化”について〜 第142回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(1) 〜長時間労働問題について〜
第142回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(1) 〜長時間労働問題について〜 第141回 リーダーシップの社会心理学(5) 〜リーダーシップ観の変遷とこれから〜
第141回 リーダーシップの社会心理学(5) 〜リーダーシップ観の変遷とこれから〜 第140回 リーダーシップの社会心理学(4) 〜リーダーの影響力と「人脈」〜
第140回 リーダーシップの社会心理学(4) 〜リーダーの影響力と「人脈」〜 第139回 リーダーシップの社会心理学(3) 〜リーダーの影響力を育み強化する基盤について〜
第139回 リーダーシップの社会心理学(3) 〜リーダーの影響力を育み強化する基盤について〜 第138回 リーダーシップの社会心理学(2) 〜再考:どんなリーダーがメンバーから高く評価されるのか〜
第138回 リーダーシップの社会心理学(2) 〜再考:どんなリーダーがメンバーから高く評価されるのか〜 第137回 リーダーシップの社会心理学(1) 〜リーダーシップ幻想論(Romance of Leadership)について〜
第137回 リーダーシップの社会心理学(1) 〜リーダーシップ幻想論(Romance of Leadership)について〜 第136回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 7 ~労働生産性向上の視点から(後半)~
第136回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 7 ~労働生産性向上の視点から(後半)~ 第135回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 6 ~労働生産性向上の視点から(前半)~
第135回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 6 ~労働生産性向上の視点から(前半)~ 第134回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 5 ~日本人のメンタリティーと社会や組織の革新性との関係について~
第134回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 5 ~日本人のメンタリティーと社会や組織の革新性との関係について~ 第133回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 4 ~組織における「常識・当たり前」を考え直してみる~
第133回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 4 ~組織における「常識・当たり前」を考え直してみる~ 第132回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 3 ~どうやって新規な取り組みへの挑戦を動機づけるか~
第132回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 3 ~どうやって新規な取り組みへの挑戦を動機づけるか~ 第131回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 2 ~"奇想天外"を面白がる心のゆとりはどこから来るのか~
第131回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 2 ~"奇想天外"を面白がる心のゆとりはどこから来るのか~ 第130回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える ~"奇想天外"を面白がる"雰囲気""風土"の大切さ~
第130回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える ~"奇想天外"を面白がる"雰囲気""風土"の大切さ~ 第129回 人々の社会への協力行動を引き出す働きかけを考える ~懲罰を伴う強権発動に行き着く前に~
第129回 人々の社会への協力行動を引き出す働きかけを考える ~懲罰を伴う強権発動に行き着く前に~ 第128回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(4) ~「失敗から学ぶ組織」作りを支えるリーダーシップとは~
第128回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(4) ~「失敗から学ぶ組織」作りを支えるリーダーシップとは~ 第127回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(3) ~チーム・コミュニケーションの活性化をはかる管理職のリーダーシップとは~
第127回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(3) ~チーム・コミュニケーションの活性化をはかる管理職のリーダーシップとは~ 第126回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(2)~難局・危機的状況に立ち向かう管理職のリーダーシップ~
第126回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(2)~難局・危機的状況に立ち向かう管理職のリーダーシップ~ 第125回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(1)~オンライン・コミュニケーションのメリットを生かし、デメリットを克服する道筋~
第125回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(1)~オンライン・コミュニケーションのメリットを生かし、デメリットを克服する道筋~ 第124回 デジタル化が進む職場の「心理的安全性」について~批判や攻撃を恐れず自由闊達な意見交換の場にしていくには~
第124回 デジタル化が進む職場の「心理的安全性」について~批判や攻撃を恐れず自由闊達な意見交換の場にしていくには~ 第123回 リモートワーク環境とチームワーク形成 ~集団力学的視点から~
第123回 リモートワーク環境とチームワーク形成 ~集団力学的視点から~ 第122回 リモートワークの普及がワークライフにもたらすもの ~社会的アイデンティティの観点から~
第122回 リモートワークの普及がワークライフにもたらすもの ~社会的アイデンティティの観点から~ 第121回 トレードオフの苦境をいかに乗り越えていくか ~優先順位の付け方を人間の欲求階層説から考える~
第121回 トレードオフの苦境をいかに乗り越えていくか ~優先順位の付け方を人間の欲求階層説から考える~ 第120回 人間の行動選択と社会の心理学的「場」の関係性を考える ~新型コロナウイルス禍における自粛要請と"Go Toキャンペーン"の相剋を題材に~
第120回 人間の行動選択と社会の心理学的「場」の関係性を考える ~新型コロナウイルス禍における自粛要請と"Go Toキャンペーン"の相剋を題材に~ 第119回 認知バイアスをうまく活用して人々を特定の行動に導く方法~「ナッジ」や「仕掛け学」を参考に~
第119回 認知バイアスをうまく活用して人々を特定の行動に導く方法~「ナッジ」や「仕掛け学」を参考に~ 第118回 大切なことだとわかっていても「自分には必要ない」と思ってしまうのはなぜか~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(2)~
第118回 大切なことだとわかっていても「自分には必要ない」と思ってしまうのはなぜか~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(2)~ 第117回 なぜ人々は動かないのか。何が人々を動かすのか。 ~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(1)~
第117回 なぜ人々は動かないのか。何が人々を動かすのか。 ~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(1)~ 第116回 デジタル化が進む職場コミュニケーションとどう向き合うか ~バーチャル・チームの実情に注目しながら~
第116回 デジタル化が進む職場コミュニケーションとどう向き合うか ~バーチャル・チームの実情に注目しながら~ 第115回 職場の雑談やおしゃべりがもたらすメリットとデメリット
第115回 職場の雑談やおしゃべりがもたらすメリットとデメリット 第114回 急な組織コミュニケーションの変容で働く意識はどう変わるか
第114回 急な組織コミュニケーションの変容で働く意識はどう変わるか 第113回 職場を真の「安全基地」とするために-リスクを過剰に恐れず前向きに挑戦する行動を引き出すには-
第113回 職場を真の「安全基地」とするために-リスクを過剰に恐れず前向きに挑戦する行動を引き出すには- 第112回 セキュアベースであるための核心はリスク・テイキングを動機づけること-「安全基地」的組織を目指して(2)-
第112回 セキュアベースであるための核心はリスク・テイキングを動機づけること-「安全基地」的組織を目指して(2)- 第111回 なぜセキュアベース理論が注目されるのか -「安全基地」的組織を目指して(1)-
第111回 なぜセキュアベース理論が注目されるのか -「安全基地」的組織を目指して(1)- 第110回 ワーク・ライフ・バランスの未来図- AI(人工知能)は「働き方」をどのように変えるのだろうか -
第110回 ワーク・ライフ・バランスの未来図- AI(人工知能)は「働き方」をどのように変えるのだろうか - 第109回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(6)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって④ -
第109回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(6)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって④ - 第108回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(5)- リーダーシップ育成をめぐって③ <番外編> -
第108回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(5)- リーダーシップ育成をめぐって③ <番外編> - 第107回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(4)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって② -
第107回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(4)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって② - 第106回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(3)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって① -
第106回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(3)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって① - 第105回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(2) -「やりがい搾取」問題をめぐって-
第105回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(2) -「やりがい搾取」問題をめぐって- 第104回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味 - 終身雇用制廃止を巡る議論を題材に -
第104回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味 - 終身雇用制廃止を巡る議論を題材に - 第103回 「評判」の持つ社会的機能について考えてみる-現代社会において評判はどのくらい大切なものなのか-
第103回 「評判」の持つ社会的機能について考えてみる-現代社会において評判はどのくらい大切なものなのか- 第102回 どうすればギクシャクした対人関係を丸くおさめられるのか-「雨降って地固まる」型の対人葛藤解決方略を求めて-
第102回 どうすればギクシャクした対人関係を丸くおさめられるのか-「雨降って地固まる」型の対人葛藤解決方略を求めて- 第101回 外国語を使う必要がなくなる日は来るか-Society5.0構想と関連づけながら-
第101回 外国語を使う必要がなくなる日は来るか-Society5.0構想と関連づけながら- 第100回 ホンネ(本音)が飛び交う議論の功罪-組織や社会の安定とタテマエの働き-
第100回 ホンネ(本音)が飛び交う議論の功罪-組織や社会の安定とタテマエの働き- 第99回 「ダメ出し」をハラスメントと受け取られないようにするにはどうしたらよいのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑩-
第99回 「ダメ出し」をハラスメントと受け取られないようにするにはどうしたらよいのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑩- 第98回 勤勉は美徳か?なぜそんなに一所懸命に働くのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑨-
第98回 勤勉は美徳か?なぜそんなに一所懸命に働くのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑨- 第97回 年上の部下とのコミュニケーションが難しく感じられるのはなぜか?-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑧-
第97回 年上の部下とのコミュニケーションが難しく感じられるのはなぜか?-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑧- 第96回 「理想のリーダー像」が人によって異なることが生み出す上司と部下のすれ違い-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑦-
第96回 「理想のリーダー像」が人によって異なることが生み出す上司と部下のすれ違い-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑦- 第95回 どうすれば上司-部下間のコミュニケーションはよいものになるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑥-
第95回 どうすれば上司-部下間のコミュニケーションはよいものになるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑥- 第94回 「空気を読む」ことは賢い社会・組織を作り上げるのに有効なのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑤-
第94回 「空気を読む」ことは賢い社会・組織を作り上げるのに有効なのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑤- 第93回 新入社員をひとくくりにして「レッテルを貼る」行為はなぜなくならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う④-
第93回 新入社員をひとくくりにして「レッテルを貼る」行為はなぜなくならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う④- 第92回 懲りたはずなのに、なぜバブル経済現象は繰り返し起こるのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う③-
第92回 懲りたはずなのに、なぜバブル経済現象は繰り返し起こるのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う③- 第91回 エスカレーターで片側をあけて乗る行為は危険なのになぜ無くならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う②-
第91回 エスカレーターで片側をあけて乗る行為は危険なのになぜ無くならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う②- 第90回 応援は選手のパフォーマンスを高めるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う①-
第90回 応援は選手のパフォーマンスを高めるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う①- 第89回 緻密な人間行動観察が明らかにする事実-従業員の幸福感の高さが組織の業績を左右する?-
第89回 緻密な人間行動観察が明らかにする事実-従業員の幸福感の高さが組織の業績を左右する?- 第88回 フレーミング・シフトはどのように進めるとよいか-「職場は学習の場」というフレーミング確立に向けて-
第88回 フレーミング・シフトはどのように進めるとよいか-「職場は学習の場」というフレーミング確立に向けて- 第87回 「職場とは何か」をとらえ直す-働くことのフレーミングをより建設的なものにシフトさせるには-
第87回 「職場とは何か」をとらえ直す-働くことのフレーミングをより建設的なものにシフトさせるには- 第86回 職場を「学習する場」としてフレーミングするには-「作業の場」としてのフレーミングからの脱却-
第86回 職場を「学習する場」としてフレーミングするには-「作業の場」としてのフレーミングからの脱却- 第85回 職場集団をチームとして機能させる取り組み-「やらされ感」からの脱却への道筋-
第85回 職場集団をチームとして機能させる取り組み-「やらされ感」からの脱却への道筋- 第84回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(2)-「心理的安全(psychological safety)」を高める方策-
第84回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(2)-「心理的安全(psychological safety)」を高める方策- 第83回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(1)-「心理的安全(psychological safety)」の研究を参考に-
第83回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(1)-「心理的安全(psychological safety)」の研究を参考に- 第82回 自国第一主義が社会に蔓延するプロセスを考える-集団間関係に関する社会心理学研究をふまえて-
第82回 自国第一主義が社会に蔓延するプロセスを考える-集団間関係に関する社会心理学研究をふまえて- 第81回 自国第一主義は自国民を守るか-集団主義に関する社会心理学的研究をふまえて-
第81回 自国第一主義は自国民を守るか-集団主義に関する社会心理学的研究をふまえて- 第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか?
第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか? 第78回 『振り込め詐欺』の被害はなぜなくならないか
第78回 『振り込め詐欺』の被害はなぜなくならないか 第77回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(6)-集合現象に関する社会心理学研究を参考に-
第77回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(6)-集合現象に関する社会心理学研究を参考に- 第76回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(5)-説得行動に関する社会心理学研究を参考に-
第76回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(5)-説得行動に関する社会心理学研究を参考に- 第75回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(4)-少数者影響過程の実証研究を参考に-
第75回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(4)-少数者影響過程の実証研究を参考に- 第74回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(3)-ラタネたちのシミュレーション実験を参考に-
第74回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(3)-ラタネたちのシミュレーション実験を参考に- 第73回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(2)-サッカー効果に注目して-
第73回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(2)-サッカー効果に注目して- 第72回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(1)-投票行動に注目して-
第72回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(1)-投票行動に注目して- 第71回 信頼性の高い行動観察を行うために(5)-「他人の目」からの解放は人間行動にいかなる影響を及ぼすか-
第71回 信頼性の高い行動観察を行うために(5)-「他人の目」からの解放は人間行動にいかなる影響を及ぼすか- 第70回 信頼性の高い行動観察を行うために(4)-「他人の目」を意識することはどれほど行動に影響するか-
第70回 信頼性の高い行動観察を行うために(4)-「他人の目」を意識することはどれほど行動に影響するか- 第69回 信頼性の高い行動観察を行うために(3)-人々の行動に表れる「社会への信頼」-
第69回 信頼性の高い行動観察を行うために(3)-人々の行動に表れる「社会への信頼」- 第68回 信頼性の高い行動観察を行うために(2)-「攻撃行動」の背後で働いている心理②-
第68回 信頼性の高い行動観察を行うために(2)-「攻撃行動」の背後で働いている心理②- 第67回 信頼性の高い行動観察を行うために(1)-「攻撃行動」の背後で働いている心理①-
第67回 信頼性の高い行動観察を行うために(1)-「攻撃行動」の背後で働いている心理①- 第66回 行動観察を活かすための課題 - 観察した行動からその発生原因を正しく推測できるか -
第66回 行動観察を活かすための課題 - 観察した行動からその発生原因を正しく推測できるか - 第65回 職場のチームワーク再考(2)-職務特性によって異なるチームワーク-
第65回 職場のチームワーク再考(2)-職務特性によって異なるチームワーク- 第64回 職場のチームワーク再考(1)-職場はチームになりうるのか-
第64回 職場のチームワーク再考(1)-職場はチームになりうるのか- 第63回 組織の集合知性を育むには(4)-メンバーの視野を広げる働きかけとは-
第63回 組織の集合知性を育むには(4)-メンバーの視野を広げる働きかけとは- 第62回 組織の集合知性を育むには(3)-視野の狭まりと広がりがもたらす影響-
第62回 組織の集合知性を育むには(3)-視野の狭まりと広がりがもたらす影響- 第61回 組織の集合知性を育むには(2)-組織に潜在する集合知性の創発を阻む障壁-
第61回 組織の集合知性を育むには(2)-組織に潜在する集合知性の創発を阻む障壁- 第60回 組織の集合知性を育むには(1)-集団に宿る知性とは-
第60回 組織の集合知性を育むには(1)-集団に宿る知性とは- 第59回 会議の社会心理学(8)-職場の仲間と情報を共有するための知恵-
第59回 会議の社会心理学(8)-職場の仲間と情報を共有するための知恵- 第58回 会議の社会心理学(7)-話し合えば情報共有できるという幻想の罠-
第58回 会議の社会心理学(7)-話し合えば情報共有できるという幻想の罠- 第57回 会議の社会心理学(6)-「裸の王様」現象による決定の歪み-
第57回 会議の社会心理学(6)-「裸の王様」現象による決定の歪み- 第56回 会議の社会心理学(5)-話し合いは民意を反映するか-
第56回 会議の社会心理学(5)-話し合いは民意を反映するか- 第55回 会議の社会心理学(4)-話し合いは創造的アイディアを生み出すか-
第55回 会議の社会心理学(4)-話し合いは創造的アイディアを生み出すか- 第54回 会議の社会心理学(3)-話し合いが暴走してしまうとき②-
第54回 会議の社会心理学(3)-話し合いが暴走してしまうとき②- 第53回 会議の社会心理学(2)-話し合いが暴走してしまうとき①-
第53回 会議の社会心理学(2)-話し合いが暴走してしまうとき①- 第52回 会議の社会心理学(1)-話し合えば的確な決定を導けるか-
第52回 会議の社会心理学(1)-話し合えば的確な決定を導けるか- 第51回 やるべきことを先送りしてしまう心理的罠から抜け出せるものだろうか-「双曲割引」の意思決定バイアスの克服法をめぐって-
第51回 やるべきことを先送りしてしまう心理的罠から抜け出せるものだろうか-「双曲割引」の意思決定バイアスの克服法をめぐって- 第50回 なぜ、やるべきことを先送りしてしまうのか-「双曲割引」の意思決定バイアス-
第50回 なぜ、やるべきことを先送りしてしまうのか-「双曲割引」の意思決定バイアス- 第49回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(5)-なぜ縁起をかついでしまうのか-
第49回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(5)-なぜ縁起をかついでしまうのか- 第48回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(4)-「メンタルショットガン」の影響-
第48回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(4)-「メンタルショットガン」の影響- 第47回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(3)-「確証バイアス」の影響-
第47回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(3)-「確証バイアス」の影響- 第46回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(2)-「あと知恵バイアス」の影響-
第46回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(2)-「あと知恵バイアス」の影響- 第45回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(1)-「利用可能性」ヒューリスティックの影響-
第45回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(1)-「利用可能性」ヒューリスティックの影響- 第44回 専門家の直感は信用できるか
第44回 専門家の直感は信用できるか 第43回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(6)-交渉場面を題材に④-
第43回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(6)-交渉場面を題材に④- 第42回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(5)-交渉場面を題材に③-
第42回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(5)-交渉場面を題材に③- 第41回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(4)-交渉場面を題材に②-
第41回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(4)-交渉場面を題材に②- 第40回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(3)-交渉場面を題材に①-
第40回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(3)-交渉場面を題材に①- 第39回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(2)-行動経済学と社会心理学③-
第39回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(2)-行動経済学と社会心理学③- 第38回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(1)-行動経済学と社会心理学②-
第38回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(1)-行動経済学と社会心理学②- 第37回 人間の行動は「不合理」なのだろうか-行動経済学と社会心理学①-
第37回 人間の行動は「不合理」なのだろうか-行動経済学と社会心理学①- 第36回 他者の心を正しく読むことができるか
第36回 他者の心を正しく読むことができるか 第35回 他者のしぐさから、その他者の心を読み取れるか
第35回 他者のしぐさから、その他者の心を読み取れるか 第34回 コミュニケーションで伝わるもの
第34回 コミュニケーションで伝わるもの 第33回 チーム力、組織力とは何かについて考える(8)-"急がば回れ"のミッション共有戦略-
第33回 チーム力、組織力とは何かについて考える(8)-"急がば回れ"のミッション共有戦略- 第32回 チーム力、組織力とは何かについて考える(7)-ミッション共有は意外と難しい-
第32回 チーム力、組織力とは何かについて考える(7)-ミッション共有は意外と難しい- 第31回 チーム力、組織力とは何かについて考える(6)-ミッションの共有への取り組み-
第31回 チーム力、組織力とは何かについて考える(6)-ミッションの共有への取り組み- 第30回 チーム力、組織力とは何かについて考える(5)-プロアクティブな実践の基盤-
第30回 チーム力、組織力とは何かについて考える(5)-プロアクティブな実践の基盤- 第29回 チーム力、組織力とは何かについて考える(4)-プロアクティブ行動という視点-
第29回 チーム力、組織力とは何かについて考える(4)-プロアクティブ行動という視点- 第28回 チーム力、組織力とは何かについて考える(3)-レジリエンスを高める組織マネジメント②-
第28回 チーム力、組織力とは何かについて考える(3)-レジリエンスを高める組織マネジメント②- 第27回 チーム力、組織力とは何かについて考える(2)-レジリエンスを高める組織マネジメント①-
第27回 チーム力、組織力とは何かについて考える(2)-レジリエンスを高める組織マネジメント①- 第26回 チーム力、組織力とは何かについて考える(1)-レジリエンス-
第26回 チーム力、組織力とは何かについて考える(1)-レジリエンス- 第25回 相互理解のコミュニケーションを考える-互いに信頼し、困難と向き合うために-
第25回 相互理解のコミュニケーションを考える-互いに信頼し、困難と向き合うために-  第24回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(6)-リスク認知とリスク評価の心理学-
第24回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(6)-リスク認知とリスク評価の心理学- 第23回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(5)-リスク・コミュニケーションとクライシス・コミュニケーション-
第23回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(5)-リスク・コミュニケーションとクライシス・コミュニケーション- 第22回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(4)-アサーティブなコミュニケーションについて-
第22回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(4)-アサーティブなコミュニケーションについて- 第21回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(3)-説得と心理的リアクタンス(反発)の関係に注目して-
第21回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(3)-説得と心理的リアクタンス(反発)の関係に注目して- 第20回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(2)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に②-
第20回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(2)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に②- 第19回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(1)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に①-
第19回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(1)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に①- 第18回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(6)-社会的影響力と説得的コミュニケーションの視点から-
第18回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(6)-社会的影響力と説得的コミュニケーションの視点から- 第17回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(5)-コミュニケーション行動研究の知見から③-
第17回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(5)-コミュニケーション行動研究の知見から③- 第16回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(4)-コミュニケーション行動研究の知見から②-
第16回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(4)-コミュニケーション行動研究の知見から②- 第15回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(3)-コミュニケーション行動研究の知見から①-
第15回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(3)-コミュニケーション行動研究の知見から①- 第14回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(2)-援助行動研究の知見から-
第14回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(2)-援助行動研究の知見から- 第13回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(1)-S. Milgramのロストレター・テクニック-
第13回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(1)-S. Milgramのロストレター・テクニック- 第12回 チームワークの良さは観察すればわかるか?- “百聞は一見にしかず”行動観察の意義の核心をめぐって-
第12回 チームワークの良さは観察すればわかるか?- “百聞は一見にしかず”行動観察の意義の核心をめぐって- 第11回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(2)-チーム・マネジメントの心理学②-
第11回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(2)-チーム・マネジメントの心理学②- 第10回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(1)-チーム・マネジメントの心理学①-
第10回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(1)-チーム・マネジメントの心理学①- 第9回 チームワークと行動観察-"こころがひとつになる"と何が違ってくるのか-
第9回 チームワークと行動観察-"こころがひとつになる"と何が違ってくるのか- 第8回 組織の規範変革と社会心理学-集団に「こころ」を想定することの是非をめぐって-
第8回 組織の規範変革と社会心理学-集団に「こころ」を想定することの是非をめぐって- 第7回 組織の規範とメンバーの職務動機づけ(やる気)の関係-リターン・ポテンシャル・モデルを参考にして-
第7回 組織の規範とメンバーの職務動機づけ(やる気)の関係-リターン・ポテンシャル・モデルを参考にして- 第6回 部下のやる気を引き出す働きかけとは?-コーチングの視点に基づいて-
第6回 部下のやる気を引き出す働きかけとは?-コーチングの視点に基づいて- 第5回 人間のやる気はどのように行動に表れるだろうか-動機づけに関する社会心理学研究の視点から-
第5回 人間のやる気はどのように行動に表れるだろうか-動機づけに関する社会心理学研究の視点から- 第4回 部下のやる気と行動を引き出す管理職の働きかけとは-リーダーシップに関する社会心理学研究の視点から-
第4回 部下のやる気と行動を引き出す管理職の働きかけとは-リーダーシップに関する社会心理学研究の視点から- 第3回 多数者意見の影響力は個人の行動をどのくらい束縛するか-同調行動に関する社会心理学の研究-
第3回 多数者意見の影響力は個人の行動をどのくらい束縛するか-同調行動に関する社会心理学の研究- 第2回 流行や普及の社会現象の発生メカニズムと行動観察-T.C. Schellingの「限界質量」の理論を題材にして-
第2回 流行や普及の社会現象の発生メカニズムと行動観察-T.C. Schellingの「限界質量」の理論を題材にして- 第1回 行動を観察すれば人間心理のどこまでを明らかにすることができるのだろうか-S. Milgramの「空を見上げる人々」実験を題材にして-
第1回 行動を観察すれば人間心理のどこまでを明らかにすることができるのだろうか-S. Milgramの「空を見上げる人々」実験を題材にして-