第57回 制約条件を考える(3)
2015.04.23 山岡 俊樹 先生
制約条件を用いて、効率よく発想する方法を考える。通常、何かを発想する場合、曖昧な条件の下、色々なアイディアを出すのか良いとされている。そうすると面白いアイディアは多く出せるのだが、面白いだけの場合が多く、役に立たない。この面白いアイディアから更に別のアイディアが生まれることもあろう。しかし、発想する作業は無目的に行われるのではなく、様々な目的のために行われるので、効率良く適切なアイディアが生まれなければならない。
制約条件に基づく発想方法は、決めた制約条件の中でアイディアを求めるという効率のよいやり方である。以下に手順を示す。
①制約条件(アイディアの範囲)の範囲を決める。
例えば、斬新で従来にない製品のアイディアを出すのか?あるいは、改善レベルのアイディアなのか?
②設定した制約条件をさらに分解する。分解する基準として空間・時間他の観点から検討する。
例えば、マクロ的な視点から「日常・非日常の世界」で分解する。あるいは、ミクロ的視点では、そのマクロ的視点の日常の世界を更に絞り込んで、「自宅での世界」でも良い。
③分解した世界をさらに絞り込んでゆく。絞り込む基準は空間・時間外である。
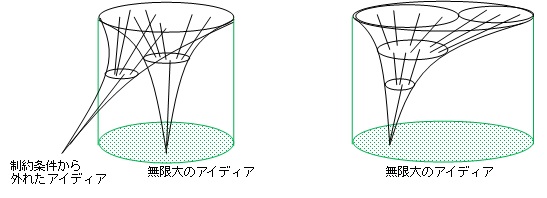
具体的に考えてみよう。例えば、LED(発光ダイオード)の活用先のアイディアを求めたい場合を考える。通常、4-5人のビジネスマンが集まり、ブレーンストーミングなどを行い、かなりの数のアイディアを収集するだろう。この場合、発想者は身の回りの事象を考え、それらに適合するLEDのアイディアを出すのが普通である。この場合、LED(発光ダイオード)の活用先のアイディアなので、制約条件として、幅広く捉え、日常空間と非日常空間からアプローチする。日常空間は家庭空間、オフィス空間、非日常空間として、旅行空間、イベント空間を考える。それぞれの空間に関して、時間軸でLEDの活用の妥当性をチェックしてゆく。この作業は人間工学でいうタスク分析である。このやり方のメリットは、論理的にアイディアが出るので、漏れが少ないのと一人でできることである。この場合、家庭空間を例に検討すると、朝から夜までの時間軸でのタスクで、LEDの活用できるアイディアを抽出する。家庭では以下のようになる。
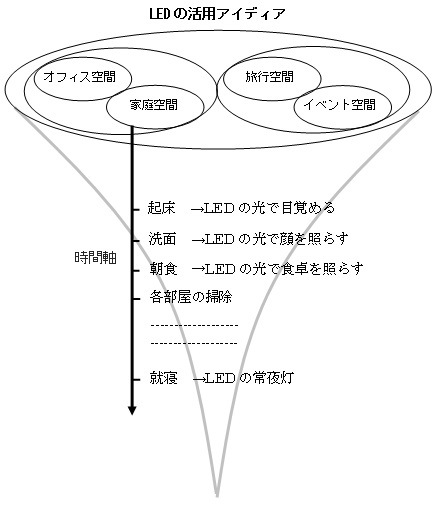
従来のように闇雲にアイディアを出すのは頭のトレーニングには良いが、短時間で効率よく、漏れが少ないようにアイディアを出すには制約条件を活用した発想法が有効である。
以前、講演会でこの方法を紹介したところ、制約条件を考えると良いアイディアが生まれないのではという質問を受けた。一見そのように思えるが、コストが開発のボトルネックとなるので、最初から制約条件を厳密にしたほうが効率的である。制約条件を曖昧にしたままの方が様々なアイディアが出ると思うが、コストや機能面の制約条件からそのアイディアの妥当性を検討するとほとんどアウトの場合も想定できる。そもそも素晴らしいアイディアはすべての制約条件をクリアしているものである。この考え方からすれば、最初から厳密な制約条件を決めて、その中で素晴らしいアイディアを想像するアルゴリズムのほうが効果的であると考える。
※先生のご所属は執筆当時のものです。
関連記事一覧
 第112回 ホリステックな考え方(22)
第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)
第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係
第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法
第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法
第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係
第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について
第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係
第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係
第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係
第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係
第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力
第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考
第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性
第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)
第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)
第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)
第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)
第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)
第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)
第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)
第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方
第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)
第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)
第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)
第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)
第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)
第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)
第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)
第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)
第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)
第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)
第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止
第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感
第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討
第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用
第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用
第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方
第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)
第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)
第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)
第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)
第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)
第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン
第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン
第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン
第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン
第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン
第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン
第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン
第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン
第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン
第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン
第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン
第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン
第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン
第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン
第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)
第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)
第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)
第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)
第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)
第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)
第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)
第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)
第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)
第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)
第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)
第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)
第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)
第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)
第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)
第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)
第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)
第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)
第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)
第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)
第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)
第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)
第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)
第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)
第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)
第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)
第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)
第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)
第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)
第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)
第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)
第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)
第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)
第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)
第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)
第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)
第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)
第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)
第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)
第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)
第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)
第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)
第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)
第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)
第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)
第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法
第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る
第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握
第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)
第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)
第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想
第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点
第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)
第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)
第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル
第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)
第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)
第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)
第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)
第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)
第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)
第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る
第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)
第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)
第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)
第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)
第60回 制約条件を考える(6)
第59回 制約条件を考える(5)
 第58回 制約条件を考える(4)
第58回 制約条件を考える(4) 第56回 制約条件を考える(2)
第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)
第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)
第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)
第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)
第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)
第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)
第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)
第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)
第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)
第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)
第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える
第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える
第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える
第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮
第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-
第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)
第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)
第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)
第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)
第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)
第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する
第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する
第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)
第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)
第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)
第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)
第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)
第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)
第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する
第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)
第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)
第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)
第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う
第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)
第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)
第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)
第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)
第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)
第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)
第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)
第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)
第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)
第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)
第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション
第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)
第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)
第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する
第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する
第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)
第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)
第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-
第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る
第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-
第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-
第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法
第1回 観察の方法
