第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力
2025.2.28 山岡 俊樹 先生
今までホリステックの考え方を述べてきた。今回はそれらを整理したいと思う。図1にあるように構造化してまとめた。
AIの活用が盛んになるにつれ、AIに頼らない仕事が人間に残された領域になるかもしれない。そのためには鋭敏な感覚を持つ必要がある。AIには鋭敏な感覚が無いからだ。我々の現在の生活は、極言すると手袋をして料理を食べたり、文字を書いたりしているのではないかと感じてしまう。箸を持つ感覚、文字を書く感覚が緩くなっているのではないだろうか?これは手だけでなく体全体もそうだ。箸や鉛筆の持ち方が自己流になってしまい、とても美しいとは思えない。偉そうにはいえないが、我が国をリードする政治家や経済人の文字の下手さ加減は残念だ。30年ぐらい前の彼らの先輩達は達筆で驚いた記憶がある。美しい作法により美しい文字が生まれる。このような道具の作法は歴史を通じて洗練されてきたはずであるが、どうなってしまったのだろうか?
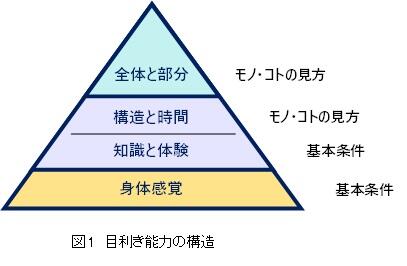
1.身体感覚の復活
このようなことから身体感覚の鋭敏化が必要で、そうでないと頭でっかちの人間になってしまう。目利きになる最低限の条件は身体感覚の鋭敏化である。例えば、道路を歩いていると金木犀(キンモクセイ)の匂いがするとき、ああこの匂いはよいなと感じるだろうか?道端に咲いている雑草に目が行くだろうか?電車内で困った人がいたとき、席を譲るだろうか?このような細やかな感覚を失ってはならない。モノ・コト、人の行動に鈍感な人に目利きになれないというのは当然であろう。これが目利きになるための基本条件である。
2.知識と体験の獲得
知識と体験が無いとモノ・コトづくりはできないし、それらの哲学も生まれない。知識や体験の少ない小学生や中学生に新しい自動車について考えろといっても無理である。しかし、笑い事ではない。実際そのような知識や体験が不足し、哲学の無いモノ・コトづくりに係る人が多いのではないかと疑ってしまう。それを痛感させる製品やソフトウエアが意外と多い。あるメーカの技術出身の企画者は、毎年イタリアで開催される展示会に自腹で参加し、最新情報を得ていると聞き驚いたことがあった。ここまでやる目利きもいるのだなと恐れ入った次第である。
さまざまな体験は知識により意味付けされ、体験が構造化される(図2)。高級ホテルに宿泊すると外部の雑音が入らない、空調が静かで気にならない、スタッフの対応が素晴らしい、などの体験が構造化されて高級ホテルに関する知識が構築されていく。
自社の製品やソフトに関し、ユーザにヒアリングし改良点などを得るのは悪くはないが、前提として開発者が目利きとなり客観的に判断できる能力が必要だ。科学主義が重きを置かれた20世紀では、開発者の主観はできるだけ避け、ユーザに聞くことは客観的で科学的であると信じられていた。ユーザとの協創などの考え方は、主体である開発者の目利き能力を減じることにならないだろうか?阪急の創始者である小林一三は、自分の考えで宝塚、東宝、第一ホテルなどの独自のビジネスを考案し、どう考えても協創などは行っていない。
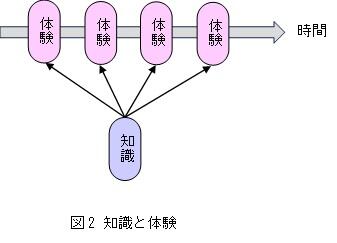
3.構造と時間を考える
我々は時空間の中で生きているので、常に空間と時間の視点から考えるとよい。空間を別の視点から考えれば、構造でもあるのでこの視点から考える。空間にはさまざまな要素が存在するが、それらを目的でまとめると構造化した存在となる。この構造を特定することによりシステム(製品や組織など)の骨格が定まる(図3)。
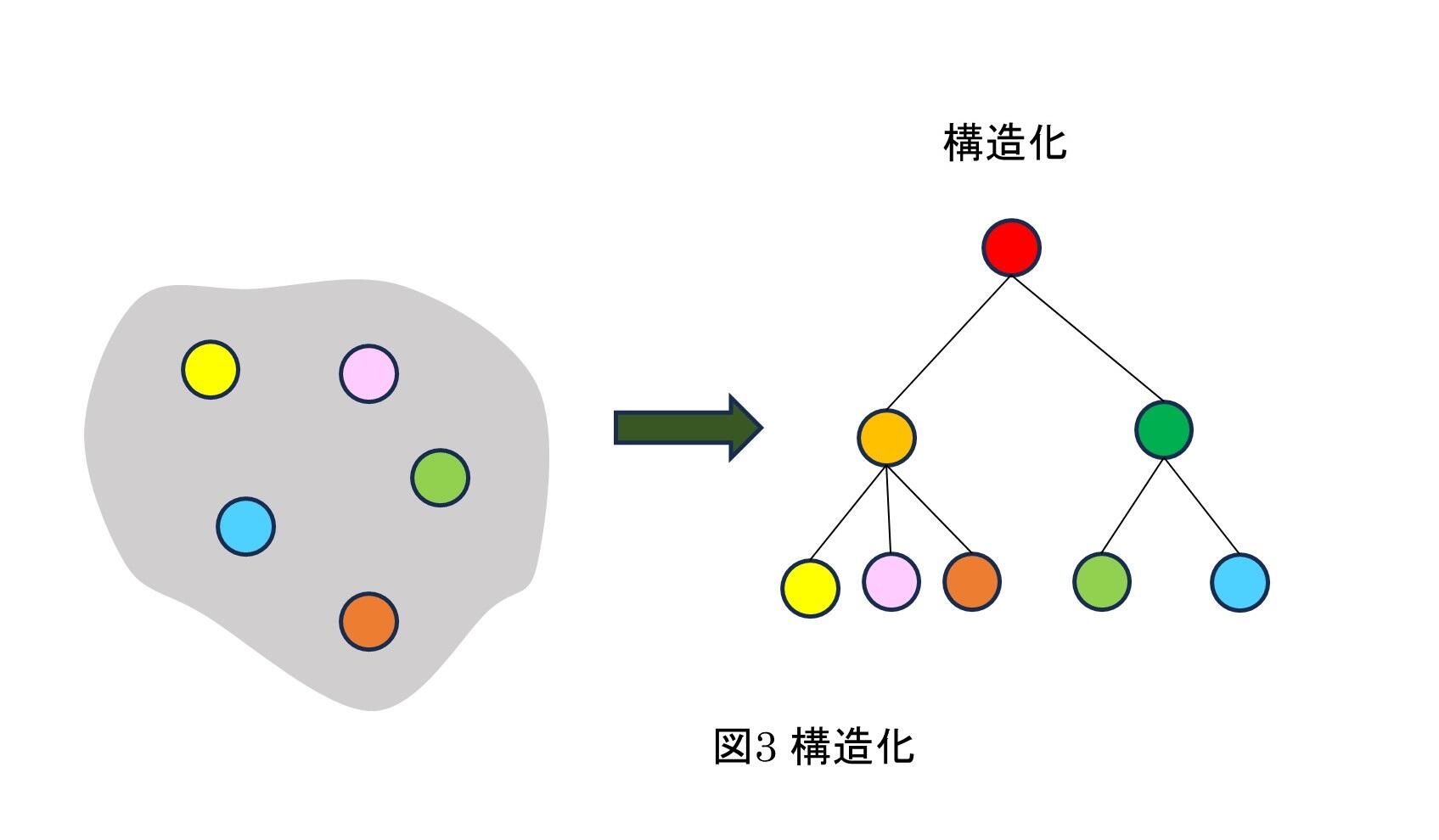
時間に関して、ローマ皇帝、マルクス・アウレリウス(Marcus Aurelius, 121-180)は過去を知れば未来を予言できると述べ、ドラッカーも同様のことをいっている。この過去とは20年前程度のことではなく、500年前ごろから調べていくとベクトルが分かるという。ドラッカーはグーテンベルグの活版印刷の技術から現在までの世の中の流れを概観し、NPOの存在を予測しぴたりと当てている。
4.全体と部分の関係を考える
インドの哲人クリシュナムルティ(Krishnamurti, 1895-1986)は我々が特定のものを全体から切り離すとき、その特定のものがそれ自身の問題を引き起こすという。そのため全領域に気づくというのは、特定のものを見、同時にそれと全体との関係を理解することであると述べている(自己の変容, P. 81, めるくまーる, 1992)(図4)。華厳宗の一即多、多即一の考えも全体と要素の関係の重要性を述べている。
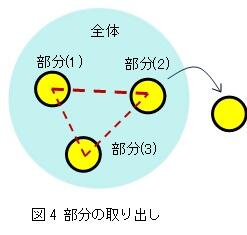
確かにそうで、ある部分を取り出すとき、全体との関係が失われる例を我々は良く知っている。例えば、所持金が無くなった、食べるものが無い、その点に意識が集中し、全体(この場合、社会)との関係が失われ、窃盗などを引き起こすことがある。
この関係はモノ・コトづくりでも同じである。前回紹介した鉄道駅のホームに置かれているイスの件も同様に考えることができる(図5)。ユーザの使用状況を予測すれば、座る時間は短時間で、さまざまなユーザが使うのでできるだけ自由度の高いデザインが望まれるだろう。しかし、このイスはユーザにフィットさせるため背もたれにS字カーブを採用している。イスという全体に対して、イスには人間工学のS字カーブがよいという部分のみに目が行ったのではないだろうか?S字カーブを採用するには、そのための前提条件を検討しなければならない。

※先生のご所属は執筆当時のものです。
関連サービス
関連記事一覧
 第112回 ホリステックな考え方(22)
第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)
第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係
第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法
第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法
第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係
第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について
第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係
第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係
第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係
第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係
第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考
第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性
第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)
第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)
第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)
第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)
第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)
第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)
第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)
第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方
第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)
第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)
第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)
第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)
第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)
第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)
第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)
第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)
第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)
第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)
第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止
第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感
第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討
第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用
第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用
第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方
第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)
第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)
第73回 チェックリストの活用法(4) 第72回 チェックリストの活用法(3)
第72回 チェックリストの活用法(3) 第71回 チェックリストの活用法(2)
第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)
第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン
第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン
第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン
第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン
第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン
第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン
第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン
第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン
第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン
第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン
第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン
第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン
第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン
第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン
第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)
第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)
第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)
第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)
第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)
第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)
第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)
第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)
第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)
第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)
第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)
第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)
第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)
第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)
第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)
第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)
第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)
第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)
第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)
第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)
第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)
第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)
第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)
第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)
第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)
第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)
第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)
第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)
第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)
第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)
第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)
第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)
第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)
第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)
第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)
第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)
第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)
第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)
第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)
第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)
第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)
第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)
第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)
第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)
第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)
第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法
第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る
第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握
第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)
第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)
第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想
第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点
第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)
第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)
第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル
第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)
第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)
第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)
第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)
第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)
第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)
第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る
第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)
第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)
第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)
第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)
第60回 制約条件を考える(6)
第59回 制約条件を考える(5)
 第58回 制約条件を考える(4)
第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)
第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)
第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)
第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)
第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)
第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)
第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)
第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)
第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)
第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)
第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)
第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)
第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える
第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える
第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える
第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮
第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-
第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)
第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)
第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)
第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)
第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)
第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する
第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する
第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)
第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)
第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)
第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)
第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)
第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)
第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する
第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)
第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)
第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)
第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う
第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)
第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)
第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)
第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)
第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)
第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)
第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)
第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)
第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)
第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)
第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション
第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)
第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)
第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する
第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する
第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)
第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)
第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-
第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る
第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-
第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-
第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法
第1回 観察の方法
