第72回 チェックリストの活用法(3)
2022.9.28 山岡 俊樹 先生
自宅の近くに2つの総合スーパーがあり、食品売り場は好調のようであるが、衣服売り場は精彩がない。そこは食品売り場と違い生活上差し迫った商品ではないため、「夢」「わくわく感が無い」と購入されないだろう。
そこで、上記の2つの総合スーパーに行ったとき、衣服売り場を簡単に観察した。わくわく感が無く、機能的に商品ジャンルごと商品が並べられていた。その特徴は以下の通り。
①わくわく感が無い(逆に言えば、情報提示力が弱い)
②機械的に商品ジャンルごとにレイアウトされている(商品ジャンル間の関係が不明)
③どうやって選択していいのか分からない(情報不足)
一方、同じフロアーにある書店では工夫を凝らし、哲学と宗教の本の売り上げトップ10を展示していた。一位は「般若心経」(佐々木閑、NHK出版)であった。哲学や宗教については関心がある方であるが、それらの本のコーナーでは目移りしてしまい、購入まで至らないことがよくある。しかし、このように展示されると、さすが一位になるだけのことがあり、分かりやすく、しかも詳しく書かれてあり、思わず購入してしまった。つまり、購入するための情報提供をしてくれているのである。
この書店のように顧客に本の持つ価値を従来と異なる方法で提示することにより、上記③の顧客に対して効果がありそうだ。何事も商品やシステムの本質を考えると何をすべきか明確になる。その本質に近づく方法の一つがマクロ的視点(思考)である。衣服売り場ならば、30年前のそこそこの機能性・デザインで価格が安ければいいという時代は終わり、顧客の価値を反映した場所にしなくてはならない。流行をあおり、毎年モデルチェンジをして、売り上げを伸ばすといったベクトルはSDGsの時代にはそぐわない。お気に入りの衣服を購入して、長く使うという潮流が我々の意識下で起こりつつあるだろう。しかし、その潜在意識は意識下にないので、顧客への刺激により覚醒してもらう必要がある。その覚醒させる手段がファッションデザインであり、ファッション売り場である。衣服が顧客の体形にフィットした、デザインが気に入ったではなく、この衣服売り場が顧客にどのような価値提案をするかがポイントである。体形へのフィット性やデザインは重要な価値であるが、それらを包含したマクロ的な価値を創造し示さなければいけない。顧客がこの衣服を着用することにより、このような世界が広がるという提案が必要である。更には、この売り場に行くことが目的化すれば成功であろう。現にホテル業界はそのような動きがみられる。
我々の思考の習いとして、ミクロ的視点が多く、要素の積み上げ式の発想が多い。要素の積み上げ式の方が考えることが容易だからである。例えば、自宅を新築する際、ここを和室にして、隣に台所にしたいなどと考えるが、そもそも本質として家族としてどのような生活をするのかというマクロ的な議論が欠けている場合が多いだろう。勿論、間取りを考えているときに生活像をある程度イメージしているが、明確にしているわけではないと思う。生活像を明確にしないと効率という近代主義の考え方で全く面白みのない住宅になってしまう。この積み上げ方式の思考は、企業のモノづくりでも同様の傾向がある。急にマクロの発想はできないので、最初は様々な情報を収集し構想を練り熟成すると、あるときこうしたいというマクロの発想ができる。
定かではないが、世の中の一流と言われる人々の思考は、ミクロだけではなく、マクロ的思考を行っているようだ。本田宗一郎氏、稲盛和夫氏などの言説からそのように感じる(図1)。本田宗一郎は、会社は社会のものなので、社名にホンダの名前を入れたことに後悔していた。積み上げの思考をしたらこのような発想は出てこない。
ミクロ的視点のチェックリストは多く提案されているが、マクロ的視点のチェックリストを作りたいと考えている。マクロ的チェックリストについては、次回に説明したい。
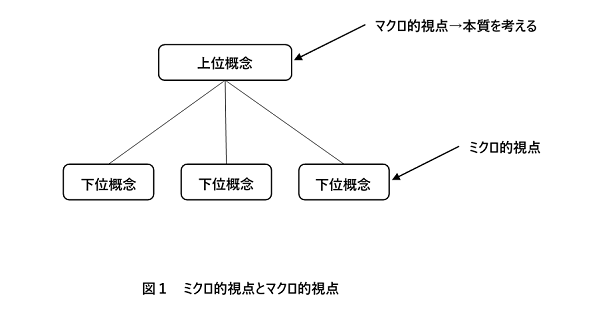
※先生のご所属は執筆当時のものです。
関連サービス
関連記事一覧
 第112回 ホリステックな考え方(22)
第112回 ホリステックな考え方(22) 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)
第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係
第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法
第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法
第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係
第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について
第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係
第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係
第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係
第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係
第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力
第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考
第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性
第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 第98回 ホリステックな考え方(8)
第98回 ホリステックな考え方(8) 第97回 ホリステックな考え方(7)
第97回 ホリステックな考え方(7) 第96回 ホリステックな考え方(6)
第96回 ホリステックな考え方(6) 第95回 ホリステックな考え方(5)
第95回 ホリステックな考え方(5) 第94回 ホリステックな考え方(4)
第94回 ホリステックな考え方(4) 第93回 ホリステックな考え方(3)
第93回 ホリステックな考え方(3) 第92回 ホリステックな考え方(2)
第92回 ホリステックな考え方(2) 第91回 ホリステックな考え方
第91回 ホリステックな考え方 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)
第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)
第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)
第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)
第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)
第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)
第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 第84回 思考の硬直・停止(その5)
第84回 思考の硬直・停止(その5) 第83回 思考の硬直・停止(その4)
第83回 思考の硬直・停止(その4) 第82回 思考の硬直・停止(その3)
第82回 思考の硬直・停止(その3) 第81回 思考の硬直・停止(その2)
第81回 思考の硬直・停止(その2) 第80回 思考の硬直・停止
第80回 思考の硬直・停止 第79回 ボリューム感
第79回 ボリューム感 第78回 構成の検討
第78回 構成の検討 第77回 アクセントの効用
第77回 アクセントの効用 第76回 活動理論の活用
第76回 活動理論の活用 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方
第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第74回 チェックリストの活用法(5)
第74回 チェックリストの活用法(5) 第73回 チェックリストの活用法(4)
第73回 チェックリストの活用法(4) 第71回 チェックリストの活用法(2)
第71回 チェックリストの活用法(2) 第70回 チェックリストの活用法(1)
第70回 チェックリストの活用法(1) 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン
第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン
第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン
第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン
第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン
第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン
第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン
第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン
第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン
第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン
第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン
第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン
第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン
第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン
第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン 第55回 温かいデザイン(31)
第55回 温かいデザイン(31) 第54回 温かいデザイン(30)
第54回 温かいデザイン(30) 第53回 温かいデザイン(29)
第53回 温かいデザイン(29) 第52回 温かいデザイン(28)
第52回 温かいデザイン(28) 第51回 温かいデザイン(27)
第51回 温かいデザイン(27) 第50回 温かいデザイン(26)
第50回 温かいデザイン(26) 第49回 温かいデザイン(25)
第49回 温かいデザイン(25) 第48回 温かいデザイン(24)
第48回 温かいデザイン(24) 第47回 温かいデザイン(23)
第47回 温かいデザイン(23) 第46回 温かいデザイン(22)
第46回 温かいデザイン(22) 第45回 温かいデザイン(21)
第45回 温かいデザイン(21) 第44回 温かいデザイン(20)
第44回 温かいデザイン(20) 第43回 温かいデザイン(19)
第43回 温かいデザイン(19) 第42回 温かいデザイン(18)
第42回 温かいデザイン(18) 第41回 温かいデザイン(17)
第41回 温かいデザイン(17) 第40回 温かいデザイン(16)
第40回 温かいデザイン(16) 第39回 温かいデザイン(15)
第39回 温かいデザイン(15) 第38回 温かいデザイン(14)
第38回 温かいデザイン(14) 第37回 温かいデザイン(13)
第37回 温かいデザイン(13) 第36回 温かいデザイン(12)
第36回 温かいデザイン(12) 第35回 温かいデザイン(11)
第35回 温かいデザイン(11) 第34回 温かいデザイン(10)
第34回 温かいデザイン(10) 第33回 温かいデザイン(9)
第33回 温かいデザイン(9)  第32回 温かいデザイン(8)
第32回 温かいデザイン(8) 第31回 温かいデザイン(7)
第31回 温かいデザイン(7) 第30回 温かいデザイン(6)
第30回 温かいデザイン(6) 第29回 温かいデザイン(5)
第29回 温かいデザイン(5) 第28回 温かいデザイン(4)
第28回 温かいデザイン(4) 第27回 温かいデザイン(3)
第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)
第26回 温かいデザイン(2) 第25回 温かいデザイン(1)
第25回 温かいデザイン(1) 第24回 人間を把握する(6)
第24回 人間を把握する(6) 第23回 人間を把握する(5)
第23回 人間を把握する(5) 第22回 人間を把握する(4)
第22回 人間を把握する(4) 第21回 人間を把握する(3)
第21回 人間を把握する(3) 第20回 人間を把握する(2)
第20回 人間を把握する(2) 第19回 人間を把握する(1)
第19回 人間を把握する(1) 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)
第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)
第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)
第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)
第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)
第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)
第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)
第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)
第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) 第10回 3つの思考方法
第10回 3つの思考方法 第9回 潮流を探る
第9回 潮流を探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握
第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第7回 構造の把握(2)
第7回 構造の把握(2) 第6回 構造の把握(1)
第6回 構造の把握(1) 第5回 システム的見方による発想
第5回 システム的見方による発想 第4回 時間軸の視点
第4回 時間軸の視点 第3回 メンタルモデル(2)
第3回 メンタルモデル(2) 第2回 メンタルモデル(1)
第2回 メンタルモデル(1) 第1回 身体モデル
第1回 身体モデル 第70回 UXを考える(6)
第70回 UXを考える(6) 第69回 UXを考える(5)
第69回 UXを考える(5) 第68回 UXを考える(4)
第68回 UXを考える(4) 第67回 UXを考える(3)
第67回 UXを考える(3) 第66回 UXを考える(2)
第66回 UXを考える(2) 第65回 UXを考える(1)
第65回 UXを考える(1) 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る
第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る 第63回 制約条件を考える(9)
第63回 制約条件を考える(9) 第62回 制約条件を考える(8)
第62回 制約条件を考える(8) 第61回 制約条件を考える(7)
第61回 制約条件を考える(7) 第60回 制約条件を考える(6)
第60回 制約条件を考える(6)
第59回 制約条件を考える(5)
 第58回 制約条件を考える(4)
第58回 制約条件を考える(4) 第57回 制約条件を考える(3)
第57回 制約条件を考える(3) 第56回 制約条件を考える(2)
第56回 制約条件を考える(2) 第55回 制約条件を考える(1)
第55回 制約条件を考える(1) 第54回 物語性について考える(9)
第54回 物語性について考える(9) 第53回 物語性について考える(8)
第53回 物語性について考える(8) 第52回 物語性について考える(7)
第52回 物語性について考える(7) 第51回 物語性について考える(6)
第51回 物語性について考える(6) 第50回 物語性について考える(5)
第50回 物語性について考える(5) 第49回 物語性について考える(4)
第49回 物語性について考える(4) 第48回 物語性について考える(3)
第48回 物語性について考える(3) 第47回 物語性について考える(2)
第47回 物語性について考える(2) 第46回 物語性について考える(1)
第46回 物語性について考える(1) 第45回 適合性について考える
第45回 適合性について考える 第44回 制約条件について考える
第44回 制約条件について考える 第43回 サインについて考える
第43回 サインについて考える 第42回 さまざまな配慮
第42回 さまざまな配慮 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-
第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第40回 表示を観察する(1)
第40回 表示を観察する(1) 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)
第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)
第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)
第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)
第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する
第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する
第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)
第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)
第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)
第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)
第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)
第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)
第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する
第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第26回 サービスを構造的に観察する(3)
第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)
第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第24回 サービスを構造的に観察する(1)
第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う
第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)
第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)
第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)
第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)
第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)
第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)
第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)
第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)
第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)
第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)
第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 70デザイン項目とアブダクション
第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)
第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)
第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する
第9回 俯瞰してHMIを観察する 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する
第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)
第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)
第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-
第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る
第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-
第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-
第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第1回 観察の方法
第1回 観察の方法
