DtoD手法に基づくアジャイル要求
「Discover to Deliver(DtoD)」は3つの時間軸とプロダクトの7側面の観点を用いてプロダクトに対するニーズとその実現スケジュールを利害関係者で話し合い、合意するためのフレームワークです。
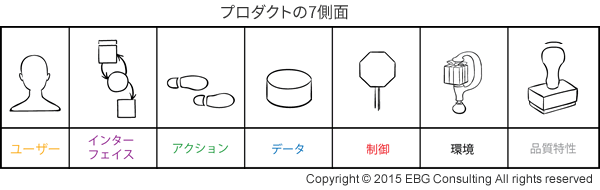
出典: エレン・ゴッテスディーナー、メアリー・ゴーマン 著, 『発見から納品へ:アジャイルなプロダクトの計画策定と分析』, BookWay, 2014. 55
また、DtoDは顧客を喜ばせるために不可欠である「正しいプロダクト」を納品するための強力なフレームワークでもあります。
DtoDが生まれた背景
スクラム※の普及
2001年にアジャイル開発宣言が起草されて以来13年が経過し、欧米ではアジャイル開発が当たり前になりつつあります。そのようなアジャイル開発の普及に大きく貢献したのが「アジャイル開発のミニマムセット」と呼ばれるスクラムというコンパクトなアジャイル開発フレームワークです。
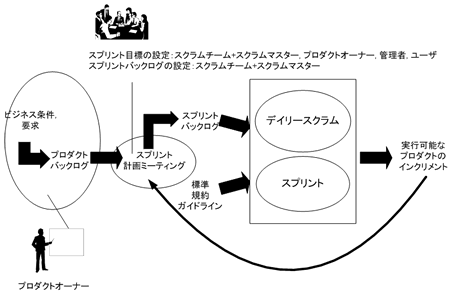
スクラムは、単純化すると以下の4つの特徴を持ちます。
- スプリントという一定の期間毎に動くソフトウェアを作る
- 要求はプロダクトバックログという優先順位付けされた一覧表に保管される
- 各スプリントにおいてその時点での優先順位の高いバックログ項目を基本に、開発チームがスプリント内で開発できる目標を設定する
- スプリント毎にバックログへの項目の追加や優先順位付け、動くソフトウェアの評価はプロダクトオーナーという役割の人が行う
1.のように一定期間毎に動くソフトウェアを作ることを時間枠(タイムボックス)納品とここでは呼びます。
スクラムは、優先順位付けされたバックログ項目の優先順位順に動くソフトウェアを作り、作成されたソフトウェアを評価することで開発依頼者や市場のニーズに即したソフトウェア(プロダクト)をすばやく開発することを可能にしました。これがスクラムの普及の大きな原動力となったのです。
プロダクトバックログ項目を表現するユーザーストーリー
その一方で、スクラムはコンパクトなアジャイル開発フレームワークとして誕生したために以下のようなことの具体的な実行方法が当初規定されていませんでした。
(ア)プロダクトバックログ項目の表現形式
(イ)プロダクトバックログ項目の定義プロセス
スクラムが発展する過程で、XPというアジャイル手法の考え方を取り入れて(ア)としてユーザーの声形式の「ユーザーストーリー」を用い、(イ)としてRon Jefferiesの3C(カード、会話、確認)の3段階でユーザーストーリーを発展させる方法が提案されました。さらに、ユーザーストーリーマッピングという手法が登場し、ユーザーストーリーをリリースや要求種別を軸に並べて各リリースの内容を考えることが提案されました。これらの方法により、開発者ではないプロダクトオーナーが自分の理解できる言葉で要求を表現したり、それらについて開発者と会話したり、リリース計画の計画策定に参加したりすることが可能になったのです。
スクラムとユーザーストーリーの組み合わせにおける課題
ただ、これらはユーザーストーリーの表現形式やそれを検討する過程を3段階で発展させ、さらに計画と結びつけた方がよいということについて優れたアドバイスではあるものの、ユーザーストーリーをどのように考案するのかという具体的な方法を示すものではありません。また、具体的な方法が示されてもその方法によりプロダクトオーナーが単独でユーザーストーリーの考案や優先順位付けを実際に行えるのかという問題もあります。
また、ユーザーストーリーはソフトウェアの機能的な要求しか表現しておらず、データや品質特性、環境などプロダクト開発に関係するニーズをより多面的に理解し、表現し、開発内容を検討し、合意を形成することには役不足です。言いかえれば、従来開発の分析に相当する作業が入りこむ余地があまりないのです。確かに従来開発の分析作業はある程度の専門性が求められ、時間もかかるし、文章を中心とした成果物を作るという点でもアジャイル開発とは相いれないものと思われるかもしれません。しかし、業務システムのように多数の利害関係者が関与するプロダクトに対するニーズをより多面的に理解し、表現し、開発内容を検討し、合意を形成することが求められる場合も多いのです。
DtoDは分析者が関与してそれらの課題を解決します
DtoDはファシリテーション、要求/分析の分野で長年に渡り活躍してきた米国EBG Consulting社のエレン・ゴッテスディーナーさんとメアリー・ゴーマンさんが考案したフレームワークであり、従来開発の分析作業を以下のように変えてアジャイル開発とうまく組み合わせられるように発展させたものです。
- ワークショップの活用
専門家単独で行うのではなく、顧客、業務、技術という異なる視点の人々が参加するワークショップを開催して、迅速にニーズをより多面的に理解し、表現し、開発内容を検討し、合意を形成する。
- 多様なモデルの活用
ワークショップで、ニーズや開発内容を軽量でとっつきやすいさまざまなモデル(短文記述を含む)により多面的に表現し、理解する。これらは、「プロダクトの7側面」という形でまとめられる。
- 分析者の役割の変更
分析者がワークショップのファシリテーターやモデラーの役割を担うことで、プロダクトオーナーの役割を分担する。
ここでプロダクトと言っているのは、開発の結果として作成されるものであり、一般消費者が使うソフトウェアやハードウェア製品やクラウドサービスだけではなく、業務システムのように特定の企業の業務を支援するシステムも含みます。
DtoDでは、要求定義、分析、計画策定を行うワークショップを計画/分析セッションと呼びます。DtoDの計画/分析セッションは、複数のリリース(全体ビュー)、次のリリース(事前ビュー)、次の反復(現在ビュー)という3つの計画策期間に対して開催します。先の説明ではスクラムを補うものとしてDtoDを説明してきましたが、DtoDはこれらのセッションの開催のタイミングを調整することで、カンバン(フロー納品)や従来開発(従来納品)の中でも活用することができるのです。
DtoD関連資料
・DtoDに基づくアジャイル要求入門
「DtoDに基づくアジャイル要求入門(PDF)」
「DtoDに基づくアジャイル要求入門」のWeb版は「オブジェクトの広場」に連載しています。
・書籍
DtoDに関するさらに詳しい内容をお知りになりたい方は、DtoDの考案者であるゴッテスディーナーさんとゴーマンさんの著書である『発見から納品へ:アジャイルなプロダクトの計画策定と分析(BookWay, 2014)』というDtoDの解説書をお薦めします。
当書籍ではDtoDおよび、それらを支援するテクニック群を解説しています。さらに、通常の業務アプリ開発に近い例として、ガラス清掃業のためのシステム開発を題材とした事例を掲載しています。
書籍詳細はこちら
アジャイル開発関連のトレーニング
オージス総研は1990年代から、反復開発やアジャイル開発に取り組み、大規模アジャイル開発の経験等を通じてノウハウを蓄積してまいりました。昨今は、上記、DtoDの紹介はもとより、下記取り組みを通じて、お客様のアジャイル開発、企業としてのアジャイルな取り組みを支援し続けています。
- ・アジャイル開発に取り組み始めた方向けのトレーニングコースの提供:
体験!アジャイル超入門
スクラム入門研修 - ・企業や事業部レベルでリーン、アジャイル、DevOpsのプラクティスを実践するためのナレッジベース「SAFe®」の導入支援やトレーニングコースの提供:
大規模アジャイルフレームワークSAFe®導入支援
SAFe®研修
アジャイル開発の導入、推進等に関して、お気軽に、お問い合わせください。
※この記事に掲載されている内容、および製品仕様、所属情報(会社名・部署名)は公開当時のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連記事一覧
 第182回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(3)〜 メンバーによるリーダーシップ評価の良し悪しは、行動よりも結果次第? 〜
第182回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(3)〜 メンバーによるリーダーシップ評価の良し悪しは、行動よりも結果次第? 〜 第112回 ホリステックな考え方(22)
第112回 ホリステックな考え方(22) 第181回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(2)〜 皆で情報交換したのにそれが活かされない!『隠されたプロフィール』現象 〜
第181回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(2)〜 皆で情報交換したのにそれが活かされない!『隠されたプロフィール』現象 〜 【初学者向け】研修で得られるものとは【セキュリティー】
【初学者向け】研修で得られるものとは【セキュリティー】 第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2)
第111回 ホリステックな考え方(21) 全体・部分・時間の関係(その2) 物流業務におけるEDIとは?仕組み・メリット・導入のポイントをわかりやすく解説
物流業務におけるEDIとは?仕組み・メリット・導入のポイントをわかりやすく解説 Black Hat発表から学ぶ!フィッシング詐欺とアカウント復旧の新たな課題
Black Hat発表から学ぶ!フィッシング詐欺とアカウント復旧の新たな課題 MBSEとは?ドキュメントベースの開発の違いやメリット、期待される効果について解説
MBSEとは?ドキュメントベースの開発の違いやメリット、期待される効果について解説 第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係
第110回 ホリステックな考え方(20) 全体・部分・時間の関係 第180回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(1)〜 自分自身をごまかしてしまう認知的不協和解消への動機づけ 〜
第180回 "意外な"人間心理や行動を明らかにした社会心理学の研究結果(1)〜 自分自身をごまかしてしまう認知的不協和解消への動機づけ 〜 工場の制御システムを守るためのセキュリティ対策ガイド
工場の制御システムを守るためのセキュリティ対策ガイド 【脅威分析・TVRA】効果的なセキュリティリスク評価のステップ
【脅威分析・TVRA】効果的なセキュリティリスク評価のステップ 第179回 優れたパフォーマンスを達成するチームづくりの要について考える
第179回 優れたパフォーマンスを達成するチームづくりの要について考える 第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法
第109回 ホリステックな考え方(19) ホリステックな視点での思考法・発想法 NewRelicとは?オブザーバビリティプラットフォームの全貌とメリット
NewRelicとは?オブザーバビリティプラットフォームの全貌とメリット AIデータ分析とは?メリットや分析手法、実施する際のポイントを解説
AIデータ分析とは?メリットや分析手法、実施する際のポイントを解説 テキスト生成AIとは?注目されている理由や活用事例、注意点を解説
テキスト生成AIとは?注目されている理由や活用事例、注意点を解説 IoTセキュリティガイドラインとは?目的や概略、推奨されるセキュリティ対策を解説
IoTセキュリティガイドラインとは?目的や概略、推奨されるセキュリティ対策を解説 セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)とは?概要や評価基準を解説
セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度(JC-STAR)とは?概要や評価基準を解説 第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法
第108回 ホリステックな考え方(18) ホリステックな視点での思考法・発想法 第178回 社会問題への不満の高まりは攻撃と排斥によって解消されるか
第178回 社会問題への不満の高まりは攻撃と排斥によって解消されるか
 「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する
「行動観察」「レジリエンス工学」で安全意識の高い現場へ変革する クラウド型EDIシステムとは?オンプレミス型との違いや導入メリットを解説!
クラウド型EDIシステムとは?オンプレミス型との違いや導入メリットを解説! 第177回 世代による考え方の違いから生まれる組織内葛藤を克服するマネジメントを考える ~ 社会的アイデンティティ研究を参考に ~
第177回 世代による考え方の違いから生まれる組織内葛藤を克服するマネジメントを考える ~ 社会的アイデンティティ研究を参考に ~
 新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説
新人・若手社員を早期育成・戦力化するには? 指導の質を向上させる方法を解説 業務フロー図とは?わかりやすい書き方やルールについて解説
業務フロー図とは?わかりやすい書き方やルールについて解説 【セミナー開催レポート】「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり~誰もが実践できるようにするための生成AI活用法~」
【セミナー開催レポート】「顧客理解とアイデア発想の有機的なつながりが産む新しい価値づくり~誰もが実践できるようにするための生成AI活用法~」 第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係
第107回 ホリステックな考え方(17) 5W1H1F1Eの方法および全体と部分の関係 業務可視化ツールとは?業務フロー図で見える化するメリットと導入のコツ
業務可視化ツールとは?業務フロー図で見える化するメリットと導入のコツ 製造業がMBSEを導入する前に知るべき課題と対策
製造業がMBSEを導入する前に知るべき課題と対策 第176回 葛藤を乗り越える交渉のあり方について ~ 日米間の関税をめぐる交渉の経緯を社会心理学の視点から振り返りつつ ~
第176回 葛藤を乗り越える交渉のあり方について ~ 日米間の関税をめぐる交渉の経緯を社会心理学の視点から振り返りつつ ~  初公開!価値づくり実践プログラム「GMC」開催リポート
初公開!価値づくり実践プログラム「GMC」開催リポート 第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について
第106回 ホリステックな考え方(16) メンタルモデルの拡大について テンプレートに頼らずに業務フロー図の作成ができるツールとは
テンプレートに頼らずに業務フロー図の作成ができるツールとは EDIとAIの融合 : データ連携の新時代
EDIとAIの融合 : データ連携の新時代 システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介
システムのブラックボックス化をルールベース開発(BRMS)で解消。活用事例ご紹介 複雑化する開発にMBSEを。いまこそ導入すべき3つの理由
複雑化する開発にMBSEを。いまこそ導入すべき3つの理由 行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~
行動観察による長期的・継続的な業務改善 ~隠れた課題を見つけ出す方法とは?~ 第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係
第105回 ホリステックな考え方(15) 全体と部分の関係 IoTシステムに最適なMQTTネットワーク設計
IoTシステムに最適なMQTTネットワーク設計 VANTIQによるスマートビルの構築 第5回 ~スマホアプリによる社員現在位置の見える化~
VANTIQによるスマートビルの構築 第5回 ~スマホアプリによる社員現在位置の見える化~ コード開発に最適な生成AIとは。コーディング特化型と汎用型を徹底比較
コード開発に最適な生成AIとは。コーディング特化型と汎用型を徹底比較 メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢
メインフレームとは?撤退か進化か、現状の課題と今後の選択肢 第175回 ストレスに悩む管理職の気構え転換戦略 ~ 問題解決型のストレス対処から情動焦点型のそれへ ~
第175回 ストレスに悩む管理職の気構え転換戦略 ~ 問題解決型のストレス対処から情動焦点型のそれへ ~ "画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践
"画面UIの使いやすさ"が業務効率を変える理由 -システムにユーザビリティを取り入れる意味と実践 ISDNサービス終了にともない見えてきたEDI運用課題とアウトソーシングという解決策 ~「全銀TCP/IP・広域IP網」を具体例としてご紹介 ~
ISDNサービス終了にともない見えてきたEDI運用課題とアウトソーシングという解決策 ~「全銀TCP/IP・広域IP網」を具体例としてご紹介 ~ 第174回 コンプライアンス時代における管理職の行動戦略~叱咤激励か、慰労し承認するか、それが問題だ~
第174回 コンプライアンス時代における管理職の行動戦略~叱咤激励か、慰労し承認するか、それが問題だ~ MQTTで強化するセキュリティ対策を分かりやすく解説
MQTTで強化するセキュリティ対策を分かりやすく解説 第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係
第104回 ホリステックな考え方(14) 全体と部分の関係 第173回 生成AIによる人事評価はメンバーのモチベーション向上につながるか~対人認知に関する社会心理学的研究の視点から~
第173回 生成AIによる人事評価はメンバーのモチベーション向上につながるか~対人認知に関する社会心理学的研究の視点から~ 複数のスクラムチーム間の品質のばらつきを解消!
複数のスクラムチーム間の品質のばらつきを解消! 第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係
第103回 ホリステックな考え方(13) 全体と部分の関係 TinyMLとは?基本概念や実装方法を解説
TinyMLとは?基本概念や実装方法を解説 オージス総研「OGIS Group Forum 2024」開催レポート 後編
オージス総研「OGIS Group Forum 2024」開催レポート 後編 オージス総研「OGIS Group Forum 2024」開催レポート 前編
オージス総研「OGIS Group Forum 2024」開催レポート 前編 第172回 合従連衡による多数派形成は紛争を解決に導くか~パワーダイナミクスに関する社会心理学的研究の視点から~
第172回 合従連衡による多数派形成は紛争を解決に導くか~パワーダイナミクスに関する社会心理学的研究の視点から~ 生成AIで業務効率化。メリットの解説とユーザーの活用事例を紹介
生成AIで業務効率化。メリットの解説とユーザーの活用事例を紹介 第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係
第102回 ホリステックな考え方(12) 全体と部分の関係 【アジャイル開発】スクラムのチームビルディングとは?成功するポイントと方法を解説
【アジャイル開発】スクラムのチームビルディングとは?成功するポイントと方法を解説 VANTIQによるスマートビルの構築 第4回 ~AIカメラによる社員の見える化の実現~
VANTIQによるスマートビルの構築 第4回 ~AIカメラによる社員の見える化の実現~ 第171回 強さを背景に利己的に振る舞う相手には、どのように対応すれば良いのだろうか~紛争に関する社会心理学的研究の視点から~
第171回 強さを背景に利己的に振る舞う相手には、どのように対応すれば良いのだろうか~紛争に関する社会心理学的研究の視点から~ スキーマ駆動開発 : 現代のシステム開発を加速させるパラダイムシフト
スキーマ駆動開発 : 現代のシステム開発を加速させるパラダイムシフト EDIとは?種類や導入効果、活用分野について解説
EDIとは?種類や導入効果、活用分野について解説 EDIと電子契約の違いとは?業務効率化に向けた最適な選択について
EDIと電子契約の違いとは?業務効率化に向けた最適な選択について MQTTとHTTPの違い。IoT開発に使用するプロトコルはどのように選ぶべきか?
MQTTとHTTPの違い。IoT開発に使用するプロトコルはどのように選ぶべきか? 第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力
第101回 ホリステックな考え方(11) 目利きの能力 生成AIを使いこなすプロンプトとは?作成例とコツを紹介
生成AIを使いこなすプロンプトとは?作成例とコツを紹介 ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説
ITOM(IT運用管理)とは?ITSMやITAMとの違いやツールの機能・概要を解説 EDI取引の効率化と安定運用を実現するポイント | アウトソーシングで課題解決
EDI取引の効率化と安定運用を実現するポイント | アウトソーシングで課題解決 第170回 日本の組織で仕事の効率が上がらない理由を考える~社会心理学的視点から~
第170回 日本の組織で仕事の効率が上がらない理由を考える~社会心理学的視点から~ 第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考
第100回 ホリステックな考え方(10) 絞込み思考 EDIシステム導入のメリットと失敗しないためのヒント
EDIシステム導入のメリットと失敗しないためのヒント 第169回 時代を超えて効果的リーダーシップの中核にあるもの~変革型リーダーシップ論を踏まえて~
第169回 時代を超えて効果的リーダーシップの中核にあるもの~変革型リーダーシップ論を踏まえて~ 第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性
第99回 ホリステックな考え方(9) 目利きの重要性 EDIによる発注業務の最適化とは?仕組み・メリット・導入手順を解説
EDIによる発注業務の最適化とは?仕組み・メリット・導入手順を解説 生成AIを活用したFAQ自動生成とは?問い合わせ対応やマニュアル探しを効率化
生成AIを活用したFAQ自動生成とは?問い合わせ対応やマニュアル探しを効率化 EDI連携とは?種類や導入のメリット、システムの選び方を解説
EDI連携とは?種類や導入のメリット、システムの選び方を解説 MQTTがIoTに最適な理由とは?知っておくべきMQTTの基本と導入メリット
MQTTがIoTに最適な理由とは?知っておくべきMQTTの基本と導入メリット 【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説
【AWS】Amazon CloudWatch Logsとは?ログ収集・監視など何ができるのかや他のツールとの違いを解説 第168回 混沌とした状況におけるリーダー行動について考える~ライフサイクル理論の視点から~
第168回 混沌とした状況におけるリーダー行動について考える~ライフサイクル理論の視点から~ 外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説
外形監視とは?目的や仕組み、メリット・デメリットを解説 第98回 ホリステックな考え方(8)
第98回 ホリステックな考え方(8) オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説
オブザーバビリティとは?意味や監視との違い、IT運用における必要性を解説 外国送金における新フォーマットISO20022とは?
外国送金における新フォーマットISO20022とは? 【ルールエンジン コラム】
【ルールエンジン コラム】
日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦
~ITテクノロジーとデジタルの活用~
第3章 10年後存続するためのIT利活用戦略 第167回 挑戦心の源について考える~やる気を見せない従業員や部下の挑戦心に火をつけるには~
第167回 挑戦心の源について考える~やる気を見せない従業員や部下の挑戦心に火をつけるには~ VANTIQによるスマートビルの構築 第3回 ~カメラによる顔認証結果を受け、セキュリティゲートやエレベータをリアルタイムに制御する機能を追加~
VANTIQによるスマートビルの構築 第3回 ~カメラによる顔認証結果を受け、セキュリティゲートやエレベータをリアルタイムに制御する機能を追加~ 第97回 ホリステックな考え方(7)
第97回 ホリステックな考え方(7) 安全を優先する組織文化を作るために
安全を優先する組織文化を作るために 第166回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(3)~部下が抱く管理職への「暗黙の期待」との向き合い方~
第166回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(3)~部下が抱く管理職への「暗黙の期待」との向き合い方~ 第96回 ホリステックな考え方(6)
第96回 ホリステックな考え方(6) ウイルスをシャットアウト
ウイルスをシャットアウト
安全にファイルを送信・受信できるクラウドサービス 新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解
新規事業成功のための行動観察を用いた顧客理解
~顧客理解=人間理解のススメ~ 第165回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(2)~対話と調整に基軸を置くリーダー行動と組織の混沌~
第165回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(2)~対話と調整に基軸を置くリーダー行動と組織の混沌~ エッジAIとTinyMLが切り開く可能性
エッジAIとTinyMLが切り開く可能性 【イベント開催レポート】生成AIとエスノする!行動観察リサーチャーが今語りたいGPT-PJシェア会
【イベント開催レポート】生成AIとエスノする!行動観察リサーチャーが今語りたいGPT-PJシェア会 第95回 ホリステックな考え方(5)
第95回 ホリステックな考え方(5) ランサムウェアの対策とは
ランサムウェアの対策とは 可視化とAI・データ分析(後半)
可視化とAI・データ分析(後半) Web-EDIとは?移行後の課題と対応策をわかりやすく解説
Web-EDIとは?移行後の課題と対応策をわかりやすく解説 第164回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(1)~「もの言う」動機づけにブレーキをかける職場の権威勾配~
第164回 組織に心理的安全性を醸成しようとするときの心理的ハードル(1)~「もの言う」動機づけにブレーキをかける職場の権威勾配~ 【ルールエンジン コラム】
【ルールエンジン コラム】
日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦
~ITテクノロジーとデジタルの活用~
第2章 グローバルな市場経済を意識して10年後存続可能な企業が進むべき展望 【ルールエンジン コラム】
【ルールエンジン コラム】
日本企業のグローバルビジネスにむけた挑戦
~ITテクノロジーとデジタルの活用~
第1章 同時多発的に起きるグローバル経済の不確実性の増大 【ルールエンジン コラム】
【ルールエンジン コラム】
ビジネスルール可視化のメリット2 デシジョンテーブルの活用 第94回 ホリステックな考え方(4)
第94回 ホリステックな考え方(4) 【ルールエンジン コラム】
【ルールエンジン コラム】
ビジネスルール可視化のメリット1 DMNの活用 オフィス宅ふぁいる便によるウイルス&ランサムウェアからのデータ保護
オフィス宅ふぁいる便によるウイルス&ランサムウェアからのデータ保護 受信者に直接パスワードを送信したい
受信者に直接パスワードを送信したい 相手からファイルを送ってもらいたい
相手からファイルを送ってもらいたい 第163回 国際化が進む日本社会における人々の心理について考える
第163回 国際化が進む日本社会における人々の心理について考える 第93回 ホリステックな考え方(3)
第93回 ホリステックな考え方(3) ファイル送信APIの活用で手間とミスを削減
ファイル送信APIの活用で手間とミスを削減 オフィス宅ふぁいる便 Outlook上での使用方法
オフィス宅ふぁいる便 Outlook上での使用方法 第162回 組織の中の世代間意識ギャップについて考える
第162回 組織の中の世代間意識ギャップについて考える 第92回 ホリステックな考え方(2)
第92回 ホリステックな考え方(2) VANTIQによるスマートビルの構築 第2回 ~ビルOSが、どのエレベータを呼び出したかディスプレイ表示する機能の追加~
VANTIQによるスマートビルの構築 第2回 ~ビルOSが、どのエレベータを呼び出したかディスプレイ表示する機能の追加~ ChatGPTとは?安全にビジネス利用するために知っておきたいメリットや課題を解説
ChatGPTとは?安全にビジネス利用するために知っておきたいメリットや課題を解説 第161回 人手不足解消への道筋を考える(4)~女性を積極的に雇用するアプローチ~
第161回 人手不足解消への道筋を考える(4)~女性を積極的に雇用するアプローチ~ 第91回 ホリステックな考え方
第91回 ホリステックな考え方 VANTIQによるスマートビルの構築 第1回 ~セキュリティゲート通過時にエレベータを自動的に呼び出す~
VANTIQによるスマートビルの構築 第1回 ~セキュリティゲート通過時にエレベータを自動的に呼び出す~ 第160回 人手不足解消への道筋を考える(3)~海外からの労働者を積極的に雇用するアプローチ~
第160回 人手不足解消への道筋を考える(3)~海外からの労働者を積極的に雇用するアプローチ~ 第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念)
第90回 思考の硬直・停止(その11)思い込み(固定概念) キッティングとは? 作業内容やアウトソーシングするメリットなどをご紹介
キッティングとは? 作業内容やアウトソーシングするメリットなどをご紹介 第159回 人手不足解消への道筋を考える(2)~高齢者を積極的に雇用するアプローチ~
第159回 人手不足解消への道筋を考える(2)~高齢者を積極的に雇用するアプローチ~ 第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念)
第89回 思考の硬直・停止(その10)思い込み(固定概念) 【セミナー開催レポート】<三菱電機株式会社講演>勘・コツ・ノウハウを次世代へ!行動観察による技能伝承
【セミナー開催レポート】<三菱電機株式会社講演>勘・コツ・ノウハウを次世代へ!行動観察による技能伝承 大容量ファイル転送のセキュリティ向上と効率化 : オフィス宅ふぁいる便の管理機能で実現するビジネス環境
大容量ファイル転送のセキュリティ向上と効率化 : オフィス宅ふぁいる便の管理機能で実現するビジネス環境 法人向けパソコン(PC)を調達するならリース、レンタル、購入のどれがいい?それぞれのメリットや注意点を解説
法人向けパソコン(PC)を調達するならリース、レンタル、購入のどれがいい?それぞれのメリットや注意点を解説 第158回 人手不足解消への道筋を考える(1)~不本意な離職を少なくしていくアプローチ~
第158回 人手不足解消への道筋を考える(1)~不本意な離職を少なくしていくアプローチ~ Microsoft Outlookだけで大容量ファイルを安全に送る : オフィス宅ふぁいる便アドイン機能で業務効率をアップ
Microsoft Outlookだけで大容量ファイルを安全に送る : オフィス宅ふぁいる便アドイン機能で業務効率をアップ 可視化とAI・データ分析(前半)
可視化とAI・データ分析(前半) 時系列分析について実際のデータを例にモデルや活用事例をご紹介
時系列分析について実際のデータを例にモデルや活用事例をご紹介 第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念)
第88回 思考の硬直・停止(その9)思い込み(固定概念) 第157回 組織的不祥事が繰り返し起こる理由を考える~「組織ならでは」の心理学的特性を視野に入れつつ~
第157回 組織的不祥事が繰り返し起こる理由を考える~「組織ならでは」の心理学的特性を視野に入れつつ~ 「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~
「デザインリサーチ」で人の本質的なニーズを捉える~考え方・手法・注意点~  第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念)
第87回 思考の硬直・停止(その8)思い込み(固定概念) 第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念)
第86回 思考の硬直・停止(その7)思い込み(固定概念) 第156回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか(2)~多様性豊かな組織の強みを引き出す包摂的リーダーシップ~
第156回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか(2)~多様性豊かな組織の強みを引き出す包摂的リーダーシップ~ 良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方
良いUXを考えるための土台となる、「UXリサーチ」の考え方  「レンゴー株式会社登壇|シェアNo.1企業が挑む、パッケージの新たな価値の創出」セミナー開催レポート
「レンゴー株式会社登壇|シェアNo.1企業が挑む、パッケージの新たな価値の創出」セミナー開催レポート 企業や法人のパソコンを処分する方法とは?パソコン内のデータ消去や廃棄方法まで解説
企業や法人のパソコンを処分する方法とは?パソコン内のデータ消去や廃棄方法まで解説 現場の安全性向上を目的とした行動観察
現場の安全性向上を目的とした行動観察 第155回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか~ネガティブ・フィードバックの大切さに着目して~
第155回 どんなリーダーシップがチームを真のチームとして機能させるのか~ネガティブ・フィードバックの大切さに着目して~ 第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念)
第85回 思考の硬直・停止(その6)思い込み(固定概念) 業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント
業務可視化を成功させノウハウや技術の伝承を実現する重要なポイント 仮想スマートシティ構築 第3回(後編)「自動音声電話によるバス乗車支援サービス」~スマートシティにおける高速開発アプローチ~
仮想スマートシティ構築 第3回(後編)「自動音声電話によるバス乗車支援サービス」~スマートシティにおける高速開発アプローチ~ 仮想スマートシティ構築 第3回(前編)「自動音声電話によるバス乗車支援サービス」~スマートシティにおける高速開発アプローチ~
仮想スマートシティ構築 第3回(前編)「自動音声電話によるバス乗車支援サービス」~スマートシティにおける高速開発アプローチ~ 第84回 思考の硬直・停止(その5)
第84回 思考の硬直・停止(その5) 第154回 「部下を動かす」力について考える~監督と管理者の違いに注目しながら~
第154回 「部下を動かす」力について考える~監督と管理者の違いに注目しながら~ エッジAIとは?活用事例や導入方法、メリット・デメリットを解説
エッジAIとは?活用事例や導入方法、メリット・デメリットを解説 新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣
新規事業立ち上げの成功ガイド:押さえておくべきポイントと秘訣 成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説
成功する商品開発のプロセスとは?6ステップで解説 メールによるランサムウェアの感染手口や対策をわかりやすく解説
メールによるランサムウェアの感染手口や対策をわかりやすく解説 「日本マクドナルド登壇 行動観察によりヒトを知り尽くせ!現場イノベーションセミナー」セミナー開催レポート
「日本マクドナルド登壇 行動観察によりヒトを知り尽くせ!現場イノベーションセミナー」セミナー開催レポート 第153回 意識や行動を変える「力」について考える ~自律的に変化を作り出す力はどこから来るか~
第153回 意識や行動を変える「力」について考える ~自律的に変化を作り出す力はどこから来るか~ DX(デジタルトランスフォーメーション)とは|意味や成功ポイント、進め方、事例を解説
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは|意味や成功ポイント、進め方、事例を解説 第83回 思考の硬直・停止(その4)
第83回 思考の硬直・停止(その4) 「島津製作所に学ぶDX時代における製造現場の品質維持の取り組み」
「島津製作所に学ぶDX時代における製造現場の品質維持の取り組み」
セミナー開催レポート(株式会社島津製作所様) 第152回 心理の世界で働く「慣性の法則」について考える ~変わ「ら」ないのか、変わ「れ」ないのか~
第152回 心理の世界で働く「慣性の法則」について考える ~変わ「ら」ないのか、変わ「れ」ないのか~ 業務組み込みとAI・データ分析(後半)
業務組み込みとAI・データ分析(後半) 第82回 思考の硬直・停止(その3)
第82回 思考の硬直・停止(その3) Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】
Splunkとは?ログ監視や分析、セキュリティ強化などを解説【スプランク入門】 第151回 AI(人工知能)の飛躍的進歩と人間の働き方
第151回 AI(人工知能)の飛躍的進歩と人間の働き方 第81回 思考の硬直・停止(その2)
第81回 思考の硬直・停止(その2) 業務組み込みとAI・データ分析(前半)
業務組み込みとAI・データ分析(前半) 第150回 管理職に求められるリーダーシップ行動の変容 〜指示・命令から傾聴そして支援へ〜
第150回 管理職に求められるリーダーシップ行動の変容 〜指示・命令から傾聴そして支援へ〜 第80回 思考の硬直・停止
第80回 思考の硬直・停止 APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方
APM(アプリケーション性能管理)とは?意味や性能監視の重要性、APMツールの選び方 AIOpsを始めるために必要なことを解説
AIOpsを始めるために必要なことを解説 IT業務の内製化を実現するための効果的なIT人材育成とは
IT業務の内製化を実現するための効果的なIT人材育成とは 第149回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(8) 〜「集団主義」的傾向のダークサイド、ブライトサイド〜
第149回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(8) 〜「集団主義」的傾向のダークサイド、ブライトサイド〜 第79回 ボリューム感
第79回 ボリューム感 AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説
AIOpsとは?AIOpsの運用事例や機能、メリットを解説 MQTTとMessagePub+ :ラベル(MessagePub+ )
MQTTとMessagePub+ :ラベル(MessagePub+ ) MQTTとMessagePub+ :トピックの名前と階層化
MQTTとMessagePub+ :トピックの名前と階層化 MQTTとMessagePub+ :トピック分類のまとめ
MQTTとMessagePub+ :トピック分類のまとめ MQTTとMessagePub+ :応答系トピック
MQTTとMessagePub+ :応答系トピック MQTTとMessagePub+ :要求系トピック
MQTTとMessagePub+ :要求系トピック MQTTとMessagePub+ :通知系トピック
MQTTとMessagePub+ :通知系トピック MQTTとMessagePub+ :トピックの分類
MQTTとMessagePub+ :トピックの分類 MQTTとMessagePub+ :MQTTを用いたIoTサービスにおけるトピック設計
MQTTとMessagePub+ :MQTTを用いたIoTサービスにおけるトピック設計 MQTTとMessagePub+ :MessagePub+ におけるセッション管理
MQTTとMessagePub+ :MessagePub+ におけるセッション管理 第148回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(7) 〜自己卑下的に発言し、振る舞うことの影響〜
第148回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(7) 〜自己卑下的に発言し、振る舞うことの影響〜 第78回 構成の検討
第78回 構成の検討 MQTTとMessagePub+ :MQTT活用のコツ
MQTTとMessagePub+ :MQTT活用のコツ ウェアラブル端末導入による仮説生成
ウェアラブル端末導入による仮説生成 課題粒度とAI・データ分析
課題粒度とAI・データ分析 第147回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(6) 〜ランキングに一喜一憂?〜
第147回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(6) 〜ランキングに一喜一憂?〜 第77回 アクセントの効用
第77回 アクセントの効用 データ活用の成功プロセス|ポイントや事例も徹底解説
データ活用の成功プロセス|ポイントや事例も徹底解説 第146回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(5) 〜リスク・コミュニケーションの難しさ〜
第146回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(5) 〜リスク・コミュニケーションの難しさ〜 「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー
「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー
開催レポート(2)(ハウス食品株式会社様) 「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー
「生活者インサイトリサーチにおける新たな挑戦」セミナー
開催レポート(1)(花王株式会社様) 第76回 活動理論の活用
第76回 活動理論の活用 第145回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(4) 〜リスクをできるだけ回避しようとする傾向〜
第145回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(4) 〜リスクをできるだけ回避しようとする傾向〜 第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方
第75回 観察におけるエティックとイーミックの考え方 第144回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(3) 〜資産形成は投資よりも貯金を優先する傾向〜
第144回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(3) 〜資産形成は投資よりも貯金を優先する傾向〜 第74回 チェックリストの活用法(5)
第74回 チェックリストの活用法(5) 仮想スマートシティ構築 第2回 仮想スマートシティ「NooS City」アプリのご紹介
仮想スマートシティ構築 第2回 仮想スマートシティ「NooS City」アプリのご紹介 第143回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(2) 〜“ガラパゴス化”について〜
第143回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(2) 〜“ガラパゴス化”について〜 第73回 チェックリストの活用法(4)
第73回 チェックリストの活用法(4) 第142回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(1) 〜長時間労働問題について〜
第142回 「日本的」な社会・集合現象について社会心理学的視点から考える(1) 〜長時間労働問題について〜 仮想スマートシティ構築 第1回 VANTIQによるFIWAREを利用した仮想スマートシティ「NooS City」
仮想スマートシティ構築 第1回 VANTIQによるFIWAREを利用した仮想スマートシティ「NooS City」 IdP(IDプロバイダー)とは?SP(サービスプロバイダー)との役割と違いやメリットについて解説
IdP(IDプロバイダー)とは?SP(サービスプロバイダー)との役割と違いやメリットについて解説 第72回 チェックリストの活用法(3)
第72回 チェックリストの活用法(3) 地図を使った顧客管理とは?メリットとポイントについて解説
地図を使った顧客管理とは?メリットとポイントについて解説 第141回 リーダーシップの社会心理学(5) 〜リーダーシップ観の変遷とこれから〜
第141回 リーダーシップの社会心理学(5) 〜リーダーシップ観の変遷とこれから〜 プロが解く観察力の鍛え方 第3回
プロが解く観察力の鍛え方 第3回
あなたのユーザーインサイトはユーザーが見えるか? IT資産管理「必要性と、ツールの機能や選び方を徹底解説」
IT資産管理「必要性と、ツールの機能や選び方を徹底解説」 パスワードレス認証とは?認証の種類と仕組み、メリットと注意点について解説
パスワードレス認証とは?認証の種類と仕組み、メリットと注意点について解説 第71回 チェックリストの活用法(2)
第71回 チェックリストの活用法(2) 電子インボイスとは?概要と導入による影響を解説
電子インボイスとは?概要と導入による影響を解説 第140回 リーダーシップの社会心理学(4) 〜リーダーの影響力と「人脈」〜
第140回 リーダーシップの社会心理学(4) 〜リーダーの影響力と「人脈」〜 ID管理とは? 重要性やメリット、ID管理システム導入のポイントについて解説
ID管理とは? 重要性やメリット、ID管理システム導入のポイントについて解説 第70回 チェックリストの活用法(1)
第70回 チェックリストの活用法(1) 第139回 リーダーシップの社会心理学(3) 〜リーダーの影響力を育み強化する基盤について〜
第139回 リーダーシップの社会心理学(3) 〜リーダーの影響力を育み強化する基盤について〜 第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン
第69回 温かいデザイン(45) サービスデザイン ID管理の業務負荷を軽減する「認証基盤」とは?4つの機能と導入時の課題について解説
ID管理の業務負荷を軽減する「認証基盤」とは?4つの機能と導入時の課題について解説 AI-OCRとは?業務に組み込むメリットと課題、活用シーン
AI-OCRとは?業務に組み込むメリットと課題、活用シーン イノハブ開催レポート
イノハブ開催レポート プロが解く観察力の鍛え方 第2回
プロが解く観察力の鍛え方 第2回
気づきだけではまだ足りない~インサイトが刺さらない理由~ サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説
サーバーダウンの原因と対策とは?システム障害を防ぐサーバー運用について解説 第138回 リーダーシップの社会心理学(2) 〜再考:どんなリーダーがメンバーから高く評価されるのか〜
第138回 リーダーシップの社会心理学(2) 〜再考:どんなリーダーがメンバーから高く評価されるのか〜 電子帳簿保存法とは?対象書類や保存方法、2022年の改正内容を解説
電子帳簿保存法とは?対象書類や保存方法、2022年の改正内容を解説 第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン
第68回 温かいデザイン(44) サービスデザイン BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説
BRMS導入にデメリットはあるのか?10年以上のBRMS導入支援実績をもとに解説 Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~
Safety-Ⅱを用いた安全性向上支援 ~レジリエンス工学に基づく安全の取り組み~ 第137回 リーダーシップの社会心理学(1) 〜リーダーシップ幻想論(Romance of Leadership)について〜
第137回 リーダーシップの社会心理学(1) 〜リーダーシップ幻想論(Romance of Leadership)について〜 多要素認証(MFA)とは?セキュリティ向上に貢献できる理由や認証方式の種類について解説
多要素認証(MFA)とは?セキュリティ向上に貢献できる理由や認証方式の種類について解説 システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント
システム・サーバー運用業務の自動化が進まない理由と運用自動化を成功に導くポイント 第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン
第67回 温かいデザイン(43) サービスデザイン 大容量ファイル送信サービスを選ぶポイント | 重要性やメリットも解説
大容量ファイル送信サービスを選ぶポイント | 重要性やメリットも解説 シングルサインオン(SSO)認証とは?仕組み、認証方式の種類、メリットや認証連携のパターン
シングルサインオン(SSO)認証とは?仕組み、認証方式の種類、メリットや認証連携のパターン 第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン
第66回 温かいデザイン(42) サービスデザイン 第136回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 7 ~労働生産性向上の視点から(後半)~
第136回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 7 ~労働生産性向上の視点から(後半)~ パスワードレス認証を実現するFIDO2認証<不正ログインの脅威と対策(第4回)>
パスワードレス認証を実現するFIDO2認証<不正ログインの脅威と対策(第4回)> 第135回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 6 ~労働生産性向上の視点から(前半)~
第135回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 6 ~労働生産性向上の視点から(前半)~ 運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について
運用自動化プラットフォームKompiraとは?特長と導入メリット、事例について 第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン
第65回 温かいデザイン(41) サービスデザイン PPAP対策。問題点や代替案とその比較
PPAP対策。問題点や代替案とその比較 多要素認証に用いられる認証方式<不正ログインの脅威と対策(第3回)>
多要素認証に用いられる認証方式<不正ログインの脅威と対策(第3回)> 第134回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 5 ~日本人のメンタリティーと社会や組織の革新性との関係について~
第134回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 5 ~日本人のメンタリティーと社会や組織の革新性との関係について~ ファイル転送サービスの選び方と比較方法とは?導入メリットや手順、大容量以外の比較ポイント
ファイル転送サービスの選び方と比較方法とは?導入メリットや手順、大容量以外の比較ポイント 第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン
第64回 温かいデザイン(40) サービスデザイン サーバー監視とは?目的やツールの選び方、自動化について解説
サーバー監視とは?目的やツールの選び方、自動化について解説 第133回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 4 ~組織における「常識・当たり前」を考え直してみる~
第133回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 4 ~組織における「常識・当たり前」を考え直してみる~ 第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン
第63回 温かいデザイン(39) サービスデザイン 今、求められている不正ログイン対策とは<不正ログインの脅威と対策(第2回)>
今、求められている不正ログイン対策とは<不正ログインの脅威と対策(第2回)> BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~
BRMSとは?~ビジネスルールを切り出すことによる4つの特長~ 運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには?
運用自動化の事例紹介-システム運用をラクにする運用自動化を実現するには? Webサービスに潜む不正ログインの脅威<不正ログインの脅威と対策(第1回)>
Webサービスに潜む不正ログインの脅威<不正ログインの脅威と対策(第1回)> 情報漏えいとは?事例やセキュリティ対策、発生する理由を解説
情報漏えいとは?事例やセキュリティ対策、発生する理由を解説 第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン
第62回 温かいデザイン(38) サービスデザイン 第132回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 3 ~どうやって新規な取り組みへの挑戦を動機づけるか~
第132回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 3 ~どうやって新規な取り組みへの挑戦を動機づけるか~ プロが解く観察力の鍛え方 第1回
プロが解く観察力の鍛え方 第1回
「気づき力」を高めるために必要な2つのこと 運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説
運用自動化とは?自動化のメリットと方法、効率の良い進め方を解説
ミステリーショッパーのメリットと「現場の気づき」の重要性
 IoTのセキュリティ対策とは?3つのセキュリティリスクとその対応策
IoTのセキュリティ対策とは?3つのセキュリティリスクとその対応策 第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン
第61回 温かいデザイン(37) サービスデザイン 第131回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 2 ~"奇想天外"を面白がる心のゆとりはどこから来るのか~
第131回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える 2 ~"奇想天外"を面白がる心のゆとりはどこから来るのか~ 「リードタイム短縮」を容易に実現 時流に即したEDI環境の構築法
「リードタイム短縮」を容易に実現 時流に即したEDI環境の構築法 ISDNサービス終了で転換点を迎えるEDI
ISDNサービス終了で転換点を迎えるEDI
さらにその先も見据えた、あるべき姿とは? システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説
システム運用とは?運用管理と保守の違いや仕事内容、業務効率化の方法を解説 ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策
ビジネスルールとは?概要とルール変更の課題、ルール管理による解決策 第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン
第60回 温かいデザイン(36) サービスデザイン 安全性診断サービス
安全性診断サービス 第130回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える ~"奇想天外"を面白がる"雰囲気""風土"の大切さ~
第130回 社会心理学的視点で社会と組織の活力の源泉を考える ~"奇想天外"を面白がる"雰囲気""風土"の大切さ~ 新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」
新規事業開発の成功プロセス「アイデア出しの3つの手順」 古いEDIが「足を引っ張る」? データ活用時代にサービスとしてのEDIが求められるワケ
古いEDIが「足を引っ張る」? データ活用時代にサービスとしてのEDIが求められるワケ 【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】保険業
【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】保険業 第129回 人々の社会への協力行動を引き出す働きかけを考える ~懲罰を伴う強権発動に行き着く前に~
第129回 人々の社会への協力行動を引き出す働きかけを考える ~懲罰を伴う強権発動に行き着く前に~ 第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン
第59回 温かいデザイン(35) サービスデザイン Azure AD導入環境におけるクラウドとオンプレミスのアカウント管理の実現と課題 <テレワーク時代のアカウント管理(第4回)>
Azure AD導入環境におけるクラウドとオンプレミスのアカウント管理の実現と課題 <テレワーク時代のアカウント管理(第4回)> 【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】広告業
【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】広告業 第128回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(4) ~「失敗から学ぶ組織」作りを支えるリーダーシップとは~
第128回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(4) ~「失敗から学ぶ組織」作りを支えるリーダーシップとは~ 第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン
第58回 温かいデザイン(34)サービスデザイン クラウド利用を見据えたアカウント管理システムの役割と重要機能 <テレワーク時代のアカウント管理(第3回)>
クラウド利用を見据えたアカウント管理システムの役割と重要機能 <テレワーク時代のアカウント管理(第3回)> 【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】商社
【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】商社 【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】製薬業
【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】製薬業 【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】建設業
【オフィス宅ふぁいる便 利用シーン】建設業 ホワイトリストで安全なファイル送信を実現
ホワイトリストで安全なファイル送信を実現 個人情報漏洩対策 Pマーク取得企業サービスを選ぶべき理由
個人情報漏洩対策 Pマーク取得企業サービスを選ぶべき理由 360度カメラ映像による行動観察
360度カメラ映像による行動観察 【オフィス宅ふぁいる便 導入事例】SMART MANUFACTURING TECHNOLOGY JAPAN株式会社様
【オフィス宅ふぁいる便 導入事例】SMART MANUFACTURING TECHNOLOGY JAPAN株式会社様 【オフィス宅ふぁいる便 導入事例】リード・エレクトロニクス株式会社様
【オフィス宅ふぁいる便 導入事例】リード・エレクトロニクス株式会社様 第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン
第57回 温かいデザイン(33)サービスデザイン 第127回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(3) ~チーム・コミュニケーションの活性化をはかる管理職のリーダーシップとは~
第127回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(3) ~チーム・コミュニケーションの活性化をはかる管理職のリーダーシップとは~ アカウント管理システムの導入事例と将来的に果たすべき役割 <テレワーク時代のアカウント管理(第2回)>
アカウント管理システムの導入事例と将来的に果たすべき役割 <テレワーク時代のアカウント管理(第2回)> DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~
DXによる事業課題解決に向けたプロセス ~「デザイン思考」と「アジャイル開発」~ パスワード付きzipファイルをメールで送るのはもうダメ!?危険性を徹底解説!
パスワード付きzipファイルをメールで送るのはもうダメ!?危険性を徹底解説! 【セミナーレポート】AI活用セミナー(2020年8月21日、10月15日)
【セミナーレポート】AI活用セミナー(2020年8月21日、10月15日) 第126回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(2)~難局・危機的状況に立ち向かう管理職のリーダーシップ~
第126回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(2)~難局・危機的状況に立ち向かう管理職のリーダーシップ~ 急拡大するテレワーク時代に不可欠なアカウント管理 <テレワーク時代のアカウント管理(第1回)>
急拡大するテレワーク時代に不可欠なアカウント管理 <テレワーク時代のアカウント管理(第1回)> 第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン
第56回 温かいデザイン(32)サービスデザイン メール誤送信の対処法と防止対策|リスクや誤送信のパターンも解説
メール誤送信の対処法と防止対策|リスクや誤送信のパターンも解説 第125回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(1)~オンライン・コミュニケーションのメリットを生かし、デメリットを克服する道筋~
第125回 リモートワーク時代の職場のチームワークを考える(1)~オンライン・コミュニケーションのメリットを生かし、デメリットを克服する道筋~ 2024年1月 ISDN(INS)終了。企業への影響と代替サービスについて解説
2024年1月 ISDN(INS)終了。企業への影響と代替サービスについて解説 第55回 温かいデザイン(31)
第55回 温かいデザイン(31) 行動観察×AI
行動観察×AI 第124回 デジタル化が進む職場の「心理的安全性」について~批判や攻撃を恐れず自由闊達な意見交換の場にしていくには~
第124回 デジタル化が進む職場の「心理的安全性」について~批判や攻撃を恐れず自由闊達な意見交換の場にしていくには~ 第54回 温かいデザイン(30)
第54回 温かいデザイン(30) 第123回 リモートワーク環境とチームワーク形成 ~集団力学的視点から~
第123回 リモートワーク環境とチームワーク形成 ~集団力学的視点から~ 第53回 温かいデザイン(29)
第53回 温かいデザイン(29) DataRobotとは?製品概要・機能一覧・解決できる課題・活用目的や使い方例を徹底解説
DataRobotとは?製品概要・機能一覧・解決できる課題・活用目的や使い方例を徹底解説 第122回 リモートワークの普及がワークライフにもたらすもの ~社会的アイデンティティの観点から~
第122回 リモートワークの普及がワークライフにもたらすもの ~社会的アイデンティティの観点から~ 第52回 温かいデザイン(28)
第52回 温かいデザイン(28) 工場の設備点検・設備監視とは?その業務内容や課題、アナログメーター可視化による効率化方法を解説
工場の設備点検・設備監視とは?その業務内容や課題、アナログメーター可視化による効率化方法を解説 IoTサービスもルールベースAIで解決
IoTサービスもルールベースAIで解決
~複雑なサービス料金プラン作成や料金計算に最適~ 第121回 トレードオフの苦境をいかに乗り越えていくか ~優先順位の付け方を人間の欲求階層説から考える~
第121回 トレードオフの苦境をいかに乗り越えていくか ~優先順位の付け方を人間の欲求階層説から考える~ 第51回 温かいデザイン(27)
第51回 温かいデザイン(27) ルールベースAIでDX時代を生き抜く
ルールベースAIでDX時代を生き抜く
~ビジネス源泉の強みとなるビジネスルールの帰属~ 第50回 温かいデザイン(26)
第50回 温かいデザイン(26) 第120回 人間の行動選択と社会の心理学的「場」の関係性を考える ~新型コロナウイルス禍における自粛要請と"Go Toキャンペーン"の相剋を題材に~
第120回 人間の行動選択と社会の心理学的「場」の関係性を考える ~新型コロナウイルス禍における自粛要請と"Go Toキャンペーン"の相剋を題材に~ 【セミナーレポート】8/26-27開催、ITmediaエンタープライズ主催、「『形なき資産』をいかに守り、管理するか ~データガバナンスが切り開く企業の未来~」にて講演
【セミナーレポート】8/26-27開催、ITmediaエンタープライズ主催、「『形なき資産』をいかに守り、管理するか ~データガバナンスが切り開く企業の未来~」にて講演 【セミナーレポート】9/24開催「DX時代のデータ活用とは? DataOpsを知り、メタデータ管理をはじめよう!」(マジセミオンラインセミナー)を開催
【セミナーレポート】9/24開催「DX時代のデータ活用とは? DataOpsを知り、メタデータ管理をはじめよう!」(マジセミオンラインセミナー)を開催 第119回 認知バイアスをうまく活用して人々を特定の行動に導く方法~「ナッジ」や「仕掛け学」を参考に~
第119回 認知バイアスをうまく活用して人々を特定の行動に導く方法~「ナッジ」や「仕掛け学」を参考に~ 第49回 温かいデザイン(25)
第49回 温かいデザイン(25) SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~
SAP×ルールベースAIでアドオン課題を解決 ~アドオン再配置によるDXの実現~ 第48回 温かいデザイン(24)
第48回 温かいデザイン(24) 第118回 大切なことだとわかっていても「自分には必要ない」と思ってしまうのはなぜか~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(2)~
第118回 大切なことだとわかっていても「自分には必要ない」と思ってしまうのはなぜか~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(2)~ エンタープライズ向けOpenAMパッケージ「ThemiStruct-WAM」 <OpenAMによるシングルサインオン(第4回)>
エンタープライズ向けOpenAMパッケージ「ThemiStruct-WAM」 <OpenAMによるシングルサインオン(第4回)> OpenAMの注目機能「多要素/リスクベースの認証」と「OpenID Connect」 <OpenAMによるシングルサインオン(第3回)>
OpenAMの注目機能「多要素/リスクベースの認証」と「OpenID Connect」 <OpenAMによるシングルサインオン(第3回)> 第47回 温かいデザイン(23)
第47回 温かいデザイン(23) 第117回 なぜ人々は動かないのか。何が人々を動かすのか。 ~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(1)~
第117回 なぜ人々は動かないのか。何が人々を動かすのか。 ~接触確認アプリ(COCOA)の普及が進まない理由を社会心理学的視点で考える(1)~ 「気づき」について考える【前編】
「気づき」について考える【前編】 「気づき」について考える【後編】
「気づき」について考える【後編】 第116回 デジタル化が進む職場コミュニケーションとどう向き合うか ~バーチャル・チームの実情に注目しながら~
第116回 デジタル化が進む職場コミュニケーションとどう向き合うか ~バーチャル・チームの実情に注目しながら~ 第46回 温かいデザイン(22)
第46回 温かいデザイン(22) DX実現にむけて、 エンタープライズ企業に必要な3つの転換とは
DX実現にむけて、 エンタープライズ企業に必要な3つの転換とは 第115回 職場の雑談やおしゃべりがもたらすメリットとデメリット
第115回 職場の雑談やおしゃべりがもたらすメリットとデメリット 第45回 温かいデザイン(21)
第45回 温かいデザイン(21) コンテナプラットフォーム(kubernetes)環境におけるセキュリティ対策について
コンテナプラットフォーム(kubernetes)環境におけるセキュリティ対策について 停止が許されないDX時代のITシステムを監視・運用するKubernetes
停止が許されないDX時代のITシステムを監視・運用するKubernetes DXレポート「2025年の崖」を克服するクラウドネイティブなIT基盤とは
DXレポート「2025年の崖」を克服するクラウドネイティブなIT基盤とは コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~
コロナ感染症支援の鍵はルールベース開発にあり~DX時代にむけた現実的なIT化アプローチ~ 第44回 温かいデザイン(20)
第44回 温かいデザイン(20) 第114回 急な組織コミュニケーションの変容で働く意識はどう変わるか
第114回 急な組織コミュニケーションの変容で働く意識はどう変わるか 第43回 温かいデザイン(19)
第43回 温かいデザイン(19) 第113回 職場を真の「安全基地」とするために-リスクを過剰に恐れず前向きに挑戦する行動を引き出すには-
第113回 職場を真の「安全基地」とするために-リスクを過剰に恐れず前向きに挑戦する行動を引き出すには- センサー・デバイス
センサー・デバイス 第112回 セキュアベースであるための核心はリスク・テイキングを動機づけること-「安全基地」的組織を目指して(2)-
第112回 セキュアベースであるための核心はリスク・テイキングを動機づけること-「安全基地」的組織を目指して(2)- 第42回 温かいデザイン(18)
第42回 温かいデザイン(18) OpenAMのコア機能「ポリシーベースのアクセス管理」と「SAMLフェデレーション」 <OpenAMによるシングルサインオン(第2回)>
OpenAMのコア機能「ポリシーベースのアクセス管理」と「SAMLフェデレーション」 <OpenAMによるシングルサインオン(第2回)> OpenAMを使ったシングルサインオン(SSO)の仕組み <OpenAMによるシングルサインオン(第1回)>
OpenAMを使ったシングルサインオン(SSO)の仕組み <OpenAMによるシングルサインオン(第1回)> 「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第5章)
「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第5章) 第111回 なぜセキュアベース理論が注目されるのか -「安全基地」的組織を目指して(1)-
第111回 なぜセキュアベース理論が注目されるのか -「安全基地」的組織を目指して(1)- 第41回 温かいデザイン(17)
第41回 温かいデザイン(17) ~オフィスビル改修における省エネ推進のための~ 省エネ・環境行動に関する行動観察プロジェクト
~オフィスビル改修における省エネ推進のための~ 省エネ・環境行動に関する行動観察プロジェクト 顧客情報の記憶に関する優秀者および一般スタッフの比較観察
顧客情報の記憶に関する優秀者および一般スタッフの比較観察 シニアをターゲットとした新業態ビジネス策定のご支援 - 企業視点からユーザー視点への変換による新たな”コミュニティの場”の実現 -
シニアをターゲットとした新業態ビジネス策定のご支援 - 企業視点からユーザー視点への変換による新たな”コミュニティの場”の実現 - キッチンの商品開発に関するエスノグラフィ調査
キッチンの商品開発に関するエスノグラフィ調査 工事現場の観察
工事現場の観察 市役所における来庁者環境および業務の最適化検討支援
市役所における来庁者環境および業務の最適化検討支援 駅構内での利用客の「迷い」行動の実態観察
駅構内での利用客の「迷い」行動の実態観察 行動観察を用いた実践的サービス・スタンダードの構築
行動観察を用いた実践的サービス・スタンダードの構築 オフィスでの従業員の働き方観察
オフィスでの従業員の働き方観察 はじまるくん
はじまるくん 第110回 ワーク・ライフ・バランスの未来図- AI(人工知能)は「働き方」をどのように変えるのだろうか -
第110回 ワーク・ライフ・バランスの未来図- AI(人工知能)は「働き方」をどのように変えるのだろうか - 第40回 温かいデザイン(16)
第40回 温かいデザイン(16) オージス総研のIoTパートナー一覧
オージス総研のIoTパートナー一覧 アジャイル導入の移行シナリオ
アジャイル導入の移行シナリオ アジャイル書籍紹介
アジャイル書籍紹介 「一気に導入」シナリオを実現するOSAM2.0
「一気に導入」シナリオを実現するOSAM2.0 「一歩ずつ導入」シナリオを実現するOSAM1.0
「一歩ずつ導入」シナリオを実現するOSAM1.0 アジャイル開発フレームワークOGIS Scalable Agile Method(OSAM)
アジャイル開発フレームワークOGIS Scalable Agile Method(OSAM) RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~
RPAの苦手を克服 ~作業の自動化から業務の自動化へ~ BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」
BRMSの課題を解決する具体策「yonobi(ヨウノビ)」 金融業務ソリューション
金融業務ソリューション データセンター見学会
データセンター見学会  IP網とは|移行の影響、INS補完策、EDIに関するQ&A
IP網とは|移行の影響、INS補完策、EDIに関するQ&A テミストラクトサポートサービスについて
テミストラクトサポートサービスについて 認証関連技術の解説
認証関連技術の解説 パートナー
パートナー MessagePub+
MessagePub+ アジャイル開発とは
アジャイル開発とは スクラムとは~要求の不確実さに対応するためのフレームワーク
スクラムとは~要求の不確実さに対応するためのフレームワーク アジャイルモデリングへの道5 XP とウォーターフォール開発の設計作業
アジャイルモデリングへの道5 XP とウォーターフォール開発の設計作業 アジャイルモデリングへの道4 アジャイル開発におけるモデリング
アジャイルモデリングへの道4 アジャイル開発におけるモデリング アジャイルモデリングへの道3 マイルドなアジャイル開発手法 AMOP
アジャイルモデリングへの道3 マイルドなアジャイル開発手法 AMOP アジャイルモデリングへの道2 スクラム組んで開発しよう!
アジャイルモデリングへの道2 スクラム組んで開発しよう! アジャイルモデリングへの道1 アジャイルなソフトウェア開発とは
アジャイルモデリングへの道1 アジャイルなソフトウェア開発とは 「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第4章)
「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第4章) 「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第3章)
「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第3章) 「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第2章)
「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第2章) 「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第1章)
「今すぐAPIを公開したい」と言われたシステム担当者が取り組むべき3つのこと(第1章) アプリケーションネットワークがデジタルトランスフォーメーションの課題に対する答えとなる
アプリケーションネットワークがデジタルトランスフォーメーションの課題に対する答えとなる APIがテクノロジー企業だけのものではない理由(後編)
APIがテクノロジー企業だけのものではない理由(後編) APIがテクノロジー企業だけのものではない理由(前編)
APIがテクノロジー企業だけのものではない理由(前編) ビジネスのあり方を変える変化のスピード
ビジネスのあり方を変える変化のスピード API-led Connectivityとは何か?(後編)
API-led Connectivityとは何か?(後編) API-led Connectivityとは何か?(前編)
API-led Connectivityとは何か?(前編) EDI対談 #04 両社の今後の展望について
EDI対談 #04 両社の今後の展望について EDI対談 #03 EDIの今後について
EDI対談 #03 EDIの今後について EDI対談 #02 2024年問題。レガシーEDIからインターネットEDIへ
EDI対談 #02 2024年問題。レガシーEDIからインターネットEDIへ EDI対談 #01 各企業、業界間の業務の違いを吸収できるサービス「EDI」
EDI対談 #01 各企業、業界間の業務の違いを吸収できるサービス「EDI」 第109回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(6)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって④ -
第109回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(6)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって④ - 第39回 温かいデザイン(15)
第39回 温かいデザイン(15) デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ
デジタルトランスフォーメーションの課題と実現に向けたアプローチ 第108回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(5)- リーダーシップ育成をめぐって③ <番外編> -
第108回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(5)- リーダーシップ育成をめぐって③ <番外編> - 第38回 温かいデザイン(14)
第38回 温かいデザイン(14) 第107回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(4)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって② -
第107回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(4)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって② - 第37回 温かいデザイン(13)
第37回 温かいデザイン(13) ビジネスぐる地図をv8.6.0にバージョンアップしました
ビジネスぐる地図をv8.6.0にバージョンアップしました 第106回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(3)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって① -
第106回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(3)- 管理者のリーダーシップ育成をめぐって① - 第36回 温かいデザイン(12)
第36回 温かいデザイン(12) ご好評いただいている機能
ご好評いただいている機能 第105回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(2) -「やりがい搾取」問題をめぐって-
第105回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味(2) -「やりがい搾取」問題をめぐって- 第35回 温かいデザイン(11)
第35回 温かいデザイン(11) リスクマネジメントと現場の気づきの重要性
リスクマネジメントと現場の気づきの重要性 ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ
ビジネスにおける行動変容のためのアプローチ 第104回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味 - 終身雇用制廃止を巡る議論を題材に -
第104回 人的資源管理に「心」の要素を考慮することの意味 - 終身雇用制廃止を巡る議論を題材に - 第34回 温かいデザイン(10)
第34回 温かいデザイン(10) カスタマージャーニーマップ作成のポイント
カスタマージャーニーマップ作成のポイント 「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性
「働き方改革」の実現に向けた現場・現物・現実の重要性 成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること
成功するファシリテーションとは?ファシリテーターに求められること 第33回 温かいデザイン(9)
第33回 温かいデザイン(9)  第103回 「評判」の持つ社会的機能について考えてみる-現代社会において評判はどのくらい大切なものなのか-
第103回 「評判」の持つ社会的機能について考えてみる-現代社会において評判はどのくらい大切なものなのか-
潜在的なヒヤリハットの把握による安全性向上
 ワークショップによる本質的なソリューションの創造
ワークショップによる本質的なソリューションの創造 デザイン思考と新価値創造
デザイン思考と新価値創造 第102回 どうすればギクシャクした対人関係を丸くおさめられるのか-「雨降って地固まる」型の対人葛藤解決方略を求めて-
第102回 どうすればギクシャクした対人関係を丸くおさめられるのか-「雨降って地固まる」型の対人葛藤解決方略を求めて- 第32回 温かいデザイン(8)
第32回 温かいデザイン(8) ビジネスぐる地図が弊社HP"オブジェクトの広場"で取り上げられました。
ビジネスぐる地図が弊社HP"オブジェクトの広場"で取り上げられました。 第31回 温かいデザイン(7)
第31回 温かいデザイン(7) 無料トライアル リニューアルのお知らせ
無料トライアル リニューアルのお知らせ 第101回 外国語を使う必要がなくなる日は来るか-Society5.0構想と関連づけながら-
第101回 外国語を使う必要がなくなる日は来るか-Society5.0構想と関連づけながら- 新たな価値創造のための3つのヒント
新たな価値創造のための3つのヒント 安全品質の向上のための3つのヒント
安全品質の向上のための3つのヒント 第30回 温かいデザイン(6)
第30回 温かいデザイン(6) 第100回 ホンネ(本音)が飛び交う議論の功罪-組織や社会の安定とタテマエの働き-
第100回 ホンネ(本音)が飛び交う議論の功罪-組織や社会の安定とタテマエの働き- 地図を見てあなたが担当しているお客様が一目で分かりますか?
地図を見てあなたが担当しているお客様が一目で分かりますか? 第29回 温かいデザイン(5)
第29回 温かいデザイン(5) 第99回 「ダメ出し」をハラスメントと受け取られないようにするにはどうしたらよいのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑩-
第99回 「ダメ出し」をハラスメントと受け取られないようにするにはどうしたらよいのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑩- ビジネスぐる地図バージョンv8.1.0をリリースしました
ビジネスぐる地図バージョンv8.1.0をリリースしました 第98回 勤勉は美徳か?なぜそんなに一所懸命に働くのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑨-
第98回 勤勉は美徳か?なぜそんなに一所懸命に働くのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑨- 第28回 温かいデザイン(4)
第28回 温かいデザイン(4) ご契約後のユーザーデータの作成方法
ご契約後のユーザーデータの作成方法 自動車保険ロードサービス業者様向けの活用方法
自動車保険ロードサービス業者様向けの活用方法 IoTデータを地図で活用しましょう!
IoTデータを地図で活用しましょう! 第97回 年上の部下とのコミュニケーションが難しく感じられるのはなぜか?-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑧-
第97回 年上の部下とのコミュニケーションが難しく感じられるのはなぜか?-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑧- 第27回 温かいデザイン(3)
第27回 温かいデザイン(3) 第26回 温かいデザイン(2)
第26回 温かいデザイン(2) 第96回 「理想のリーダー像」が人によって異なることが生み出す上司と部下のすれ違い-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑦-
第96回 「理想のリーダー像」が人によって異なることが生み出す上司と部下のすれ違い-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑦- IoTってなに?
IoTってなに? 第25回 温かいデザイン(1)
第25回 温かいデザイン(1) 鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター
鉱脈ナビ@美容市場 - 美容にモヤモヤ感を抱える未充足クラスター 第95回 どうすれば上司-部下間のコミュニケーションはよいものになるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑥-
第95回 どうすれば上司-部下間のコミュニケーションはよいものになるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑥- ビジネスぐる地図で【クラウド情報共有】はじめませんか?
ビジネスぐる地図で【クラウド情報共有】はじめませんか? "型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から -
"型のマネだけにならない"ノウハウを可視化して現場に活かす - スキル・マインドの両面から - 第24回 人間を把握する(6)
第24回 人間を把握する(6) 鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット
鉱脈ナビ@お出かけ市場 - 「家ソト&街ナカの活性化」 に貢献する6ターゲット 第94回 「空気を読む」ことは賢い社会・組織を作り上げるのに有効なのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑤-
第94回 「空気を読む」ことは賢い社会・組織を作り上げるのに有効なのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う⑤- 第23回 人間を把握する(5)
第23回 人間を把握する(5) 自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」
自主調査レポート「鉱脈ナビ@家ナカ市場」 担当候補の家庭教師を探す
担当候補の家庭教師を探す 第93回 新入社員をひとくくりにして「レッテルを貼る」行為はなぜなくならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う④-
第93回 新入社員をひとくくりにして「レッテルを貼る」行為はなぜなくならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う④- 第92回 懲りたはずなのに、なぜバブル経済現象は繰り返し起こるのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う③-
第92回 懲りたはずなのに、なぜバブル経済現象は繰り返し起こるのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う③- 第22回 人間を把握する(4)
第22回 人間を把握する(4) 第91回 エスカレーターで片側をあけて乗る行為は危険なのになぜ無くならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う②-
第91回 エスカレーターで片側をあけて乗る行為は危険なのになぜ無くならないのか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う②- 第21回 人間を把握する(3)
第21回 人間を把握する(3) 地図を使った安否確認!?
地図を使った安否確認!? 第90回 応援は選手のパフォーマンスを高めるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う①-
第90回 応援は選手のパフォーマンスを高めるのだろうか-社会心理学的視点で素朴な疑問に向き合う①- 第20回 人間を把握する(2)
第20回 人間を把握する(2) コミュニケーションについての定性調査のデータを公開
コミュニケーションについての定性調査のデータを公開 日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く
日常の些細な定性情報から本質的なニーズを導く 第19回 人間を把握する(1)
第19回 人間を把握する(1) 第89回 緻密な人間行動観察が明らかにする事実-従業員の幸福感の高さが組織の業績を左右する?-
第89回 緻密な人間行動観察が明らかにする事実-従業員の幸福感の高さが組織の業績を左右する?- 地図で情報を管理するメリットとは?
地図で情報を管理するメリットとは? 第18回 モノやシステムの本質を把握する(8)
第18回 モノやシステムの本質を把握する(8) 第88回 フレーミング・シフトはどのように進めるとよいか-「職場は学習の場」というフレーミング確立に向けて-
第88回 フレーミング・シフトはどのように進めるとよいか-「職場は学習の場」というフレーミング確立に向けて- 第87回 「職場とは何か」をとらえ直す-働くことのフレーミングをより建設的なものにシフトさせるには-
第87回 「職場とは何か」をとらえ直す-働くことのフレーミングをより建設的なものにシフトさせるには- 第17回 モノやシステムの本質を把握する(7)
第17回 モノやシステムの本質を把握する(7) Kaizen IT Summit でビジネスぐる地図の取り組みを発表しました!
Kaizen IT Summit でビジネスぐる地図の取り組みを発表しました! 第16回 モノやシステムの本質を把握する(6)
第16回 モノやシステムの本質を把握する(6) 第86回 職場を「学習する場」としてフレーミングするには-「作業の場」としてのフレーミングからの脱却-
第86回 職場を「学習する場」としてフレーミングするには-「作業の場」としてのフレーミングからの脱却- 第15回 モノやシステムの本質を把握する(5)
第15回 モノやシステムの本質を把握する(5) 無料の地図サービスとビジネスぐる地図の違いって何?
無料の地図サービスとビジネスぐる地図の違いって何? 第85回 職場集団をチームとして機能させる取り組み-「やらされ感」からの脱却への道筋-
第85回 職場集団をチームとして機能させる取り組み-「やらされ感」からの脱却への道筋- 第14回 モノやシステムの本質を把握する(4)
第14回 モノやシステムの本質を把握する(4) 第84回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(2)-「心理的安全(psychological safety)」を高める方策-
第84回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(2)-「心理的安全(psychological safety)」を高める方策- 第13回 モノやシステムの本質を把握する(3)
第13回 モノやシステムの本質を把握する(3) 第83回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(1)-「心理的安全(psychological safety)」の研究を参考に-
第83回 多様な意見が飛び交う社会や組織を築く鍵(1)-「心理的安全(psychological safety)」の研究を参考に- 撮影した写真をモバイル端末で登録できるようになりました!
撮影した写真をモバイル端末で登録できるようになりました! 第12回 モノやシステムの本質を把握する(2)
第12回 モノやシステムの本質を把握する(2) 第82回 自国第一主義が社会に蔓延するプロセスを考える-集団間関係に関する社会心理学研究をふまえて-
第82回 自国第一主義が社会に蔓延するプロセスを考える-集団間関係に関する社会心理学研究をふまえて- 第11回 モノやシステムの本質を把握する(1)
第11回 モノやシステムの本質を把握する(1) インポート機能を使いこなそう!
インポート機能を使いこなそう! 第81回 自国第一主義は自国民を守るか-集団主義に関する社会心理学的研究をふまえて-
第81回 自国第一主義は自国民を守るか-集団主義に関する社会心理学的研究をふまえて- Agile Japan 2017 でビジネスぐる地図の取り組みを発表しました!
Agile Japan 2017 でビジネスぐる地図の取り組みを発表しました! トライアルサイトを読みこなそう
トライアルサイトを読みこなそう 第10回 3つの思考方法
第10回 3つの思考方法 第80回 自国中心主義の行きつく果て:「意図せざる結果」としての共貧
第80回 自国中心主義の行きつく果て:「意図せざる結果」としての共貧 食品宅配業者様向けの活用方法
食品宅配業者様向けの活用方法 第9回 潮流を探る
第9回 潮流を探る 第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか?
第79回 ロイヤルティ・プログラムの効果について:現金値引きよりもサービスポイントの方が魅力的なことがあるのだろうか? 70代を迎える団塊世代の兆しを探る
70代を迎える団塊世代の兆しを探る 第8回 システム・サービスのフレームワークの把握
第8回 システム・サービスのフレームワークの把握 第78回 『振り込め詐欺』の被害はなぜなくならないか
第78回 『振り込め詐欺』の被害はなぜなくならないか ラインとポリゴンの使い方をご紹介します
ラインとポリゴンの使い方をご紹介します 日報機能のご紹介
日報機能のご紹介 第7回 構造の把握(2)
第7回 構造の把握(2) 第77回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(6)-集合現象に関する社会心理学研究を参考に-
第77回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(6)-集合現象に関する社会心理学研究を参考に- トライアルご利用者からのよくあるご質問
トライアルご利用者からのよくあるご質問 モバイルマップ管理情報登録機能のご紹介
モバイルマップ管理情報登録機能のご紹介 第6回 構造の把握(1)
第6回 構造の把握(1) トライアルを申し込むとこうなります
トライアルを申し込むとこうなります リフレームに必要な3つの「マインドセット」
リフレームに必要な3つの「マインドセット」 第76回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(5)-説得行動に関する社会心理学研究を参考に-
第76回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(5)-説得行動に関する社会心理学研究を参考に- 第5回 システム的見方による発想
第5回 システム的見方による発想 アナログは今後どうなるのか
アナログは今後どうなるのか 第75回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(4)-少数者影響過程の実証研究を参考に-
第75回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(4)-少数者影響過程の実証研究を参考に- 第4回 時間軸の視点
第4回 時間軸の視点 第74回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(3)-ラタネたちのシミュレーション実験を参考に-
第74回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(3)-ラタネたちのシミュレーション実験を参考に- 「わからない」に触れる価値
「わからない」に触れる価値 「リフレーム」について考える
「リフレーム」について考える 第3回 メンタルモデル(2)
第3回 メンタルモデル(2) 第73回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(2)-サッカー効果に注目して-
第73回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(2)-サッカー効果に注目して- 第2回 メンタルモデル(1)
第2回 メンタルモデル(1)
会社内の「弱い紐帯(ちゅうたい)」
 第72回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(1)-投票行動に注目して-
第72回 ひとりの行動が社会変動に結びつくとき(1)-投票行動に注目して- 「インサイト」について考える【後編】
「インサイト」について考える【後編】 「インサイト」について考える【前編】
「インサイト」について考える【前編】 第1回 身体モデル
第1回 身体モデル 第71回 信頼性の高い行動観察を行うために(5)-「他人の目」からの解放は人間行動にいかなる影響を及ぼすか-
第71回 信頼性の高い行動観察を行うために(5)-「他人の目」からの解放は人間行動にいかなる影響を及ぼすか- 第70回 UXを考える(6)
第70回 UXを考える(6) 第70回 信頼性の高い行動観察を行うために(4)-「他人の目」を意識することはどれほど行動に影響するか-
第70回 信頼性の高い行動観察を行うために(4)-「他人の目」を意識することはどれほど行動に影響するか- 第69回 UXを考える(5)
第69回 UXを考える(5) 第69回 信頼性の高い行動観察を行うために(3)-人々の行動に表れる「社会への信頼」-
第69回 信頼性の高い行動観察を行うために(3)-人々の行動に表れる「社会への信頼」- 第68回 UXを考える(4)
第68回 UXを考える(4) 第68回 信頼性の高い行動観察を行うために(2)-「攻撃行動」の背後で働いている心理②-
第68回 信頼性の高い行動観察を行うために(2)-「攻撃行動」の背後で働いている心理②- 第67回 UXを考える(3)
第67回 UXを考える(3) 第67回 信頼性の高い行動観察を行うために(1)-「攻撃行動」の背後で働いている心理①-
第67回 信頼性の高い行動観察を行うために(1)-「攻撃行動」の背後で働いている心理①- 「返報性」のキャッチボール
「返報性」のキャッチボール 第66回 UXを考える(2)
第66回 UXを考える(2) 第66回 行動観察を活かすための課題 - 観察した行動からその発生原因を正しく推測できるか -
第66回 行動観察を活かすための課題 - 観察した行動からその発生原因を正しく推測できるか - 赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには?
赤ちゃんの泣き声を許せる自分になるには? 第65回 UXを考える(1)
第65回 UXを考える(1) 第65回 職場のチームワーク再考(2)-職務特性によって異なるチームワーク-
第65回 職場のチームワーク再考(2)-職務特性によって異なるチームワーク- グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性
グルメ口コミサイトに見る、サービスの事前期待と事後評価の重要性 第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る
第64回 制約条件を考える(10)一を知り十を知る ブランディングとしての組織づくり
ブランディングとしての組織づくり 第64回 職場のチームワーク再考(1)-職場はチームになりうるのか-
第64回 職場のチームワーク再考(1)-職場はチームになりうるのか- パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か?
パリのメトロにて:サービスの「主語」は誰か? 第63回 制約条件を考える(9)
第63回 制約条件を考える(9) 第63回 組織の集合知性を育むには(4)-メンバーの視野を広げる働きかけとは-
第63回 組織の集合知性を育むには(4)-メンバーの視野を広げる働きかけとは- 京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮
京都嵐山駅で見かけた、観光気分を盛り上げる配慮 ジムとモチベーションと私
ジムとモチベーションと私 第62回 制約条件を考える(8)
第62回 制約条件を考える(8) 「ゆるくつながる」
「ゆるくつながる」 第62回 組織の集合知性を育むには(3)-視野の狭まりと広がりがもたらす影響-
第62回 組織の集合知性を育むには(3)-視野の狭まりと広がりがもたらす影響- ロボットのいる社会から人の社会を見る
ロボットのいる社会から人の社会を見る 第61回 制約条件を考える(7)
第61回 制約条件を考える(7) 第61回 組織の集合知性を育むには(2)-組織に潜在する集合知性の創発を阻む障壁-
第61回 組織の集合知性を育むには(2)-組織に潜在する集合知性の創発を阻む障壁- 第60回 制約条件を考える(6)
第60回 制約条件を考える(6) 第60回 組織の集合知性を育むには(1)-集団に宿る知性とは-
第60回 組織の集合知性を育むには(1)-集団に宿る知性とは-
第59回 制約条件を考える(5)
 第59回 会議の社会心理学(8)-職場の仲間と情報を共有するための知恵-
第59回 会議の社会心理学(8)-職場の仲間と情報を共有するための知恵- 第58回 制約条件を考える(4)
第58回 制約条件を考える(4) 第58回 会議の社会心理学(7)-話し合えば情報共有できるという幻想の罠-
第58回 会議の社会心理学(7)-話し合えば情報共有できるという幻想の罠- 第57回 制約条件を考える(3)
第57回 制約条件を考える(3) 第57回 会議の社会心理学(6)-「裸の王様」現象による決定の歪み-
第57回 会議の社会心理学(6)-「裸の王様」現象による決定の歪み- 第56回 制約条件を考える(2)
第56回 制約条件を考える(2) 第56回 会議の社会心理学(5)-話し合いは民意を反映するか-
第56回 会議の社会心理学(5)-話し合いは民意を反映するか- 第55回 制約条件を考える(1)
第55回 制約条件を考える(1) 第55回 会議の社会心理学(4)-話し合いは創造的アイディアを生み出すか-
第55回 会議の社会心理学(4)-話し合いは創造的アイディアを生み出すか- 第54回 物語性について考える(9)
第54回 物語性について考える(9) 第54回 会議の社会心理学(3)-話し合いが暴走してしまうとき②-
第54回 会議の社会心理学(3)-話し合いが暴走してしまうとき②- 第53回 物語性について考える(8)
第53回 物語性について考える(8) 第53回 会議の社会心理学(2)-話し合いが暴走してしまうとき①-
第53回 会議の社会心理学(2)-話し合いが暴走してしまうとき①- 第52回 物語性について考える(7)
第52回 物語性について考える(7) 第52回 会議の社会心理学(1)-話し合えば的確な決定を導けるか-
第52回 会議の社会心理学(1)-話し合えば的確な決定を導けるか- 第51回 物語性について考える(6)
第51回 物語性について考える(6) 第51回 やるべきことを先送りしてしまう心理的罠から抜け出せるものだろうか-「双曲割引」の意思決定バイアスの克服法をめぐって-
第51回 やるべきことを先送りしてしまう心理的罠から抜け出せるものだろうか-「双曲割引」の意思決定バイアスの克服法をめぐって- 第50回 物語性について考える(5)
第50回 物語性について考える(5) 第50回 なぜ、やるべきことを先送りしてしまうのか-「双曲割引」の意思決定バイアス-
第50回 なぜ、やるべきことを先送りしてしまうのか-「双曲割引」の意思決定バイアス- 第49回 物語性について考える(4)
第49回 物語性について考える(4) 第49回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(5)-なぜ縁起をかついでしまうのか-
第49回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(5)-なぜ縁起をかついでしまうのか- 第48回 物語性について考える(3)
第48回 物語性について考える(3) 第48回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(4)-「メンタルショットガン」の影響-
第48回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(4)-「メンタルショットガン」の影響- 第47回 物語性について考える(2)
第47回 物語性について考える(2) 第47回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(3)-「確証バイアス」の影響-
第47回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(3)-「確証バイアス」の影響- 第46回 物語性について考える(1)
第46回 物語性について考える(1) 第46回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(2)-「あと知恵バイアス」の影響-
第46回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(2)-「あと知恵バイアス」の影響- 第45回 適合性について考える
第45回 適合性について考える 第45回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(1)-「利用可能性」ヒューリスティックの影響-
第45回 人間行動の直観的判断の不可解さと面白さについて(1)-「利用可能性」ヒューリスティックの影響- 第44回 制約条件について考える
第44回 制約条件について考える 第44回 専門家の直感は信用できるか
第44回 専門家の直感は信用できるか 第43回 サインについて考える
第43回 サインについて考える 第43回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(6)-交渉場面を題材に④-
第43回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(6)-交渉場面を題材に④- 第42回 さまざまな配慮
第42回 さまざまな配慮 第42回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(5)-交渉場面を題材に③-
第42回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(5)-交渉場面を題材に③- 第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手-
第41回 表示を観察する(2)-効率の良い情報入手- 第41回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(4)-交渉場面を題材に②-
第41回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(4)-交渉場面を題材に②- 第40回 表示を観察する(1)
第40回 表示を観察する(1) 第40回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(3)-交渉場面を題材に①-
第40回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(3)-交渉場面を題材に①- 第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4)
第39回 さりげない“もてなし”を観察する(4) 第39回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(2)-行動経済学と社会心理学③-
第39回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(2)-行動経済学と社会心理学③- 第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3)
第38回 さりげない“もてなし”を観察する(3) 第38回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(1)-行動経済学と社会心理学②-
第38回 「なんとなく」な意思決定の背後にある心理(1)-行動経済学と社会心理学②- 第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2)
第37回 さりげない“もてなし”を観察する(2) 第37回 人間の行動は「不合理」なのだろうか-行動経済学と社会心理学①-
第37回 人間の行動は「不合理」なのだろうか-行動経済学と社会心理学①- 第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1)
第36回 さりげない“もてなし”を観察する(1) 第36回 他者の心を正しく読むことができるか
第36回 他者の心を正しく読むことができるか 第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する
第35回 「結果-原因」の関係から人間の行動を観察する 第35回 他者のしぐさから、その他者の心を読み取れるか
第35回 他者のしぐさから、その他者の心を読み取れるか 第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する
第34回 「目的-手段」の関係から対象物を観察する 第34回 コミュニケーションで伝わるもの
第34回 コミュニケーションで伝わるもの 第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2)
第33回 マクロとミクロの視点で観察する(2) 第33回 チーム力、組織力とは何かについて考える(8)-"急がば回れ"のミッション共有戦略-
第33回 チーム力、組織力とは何かについて考える(8)-"急がば回れ"のミッション共有戦略- 第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1)
第32回 マクロとミクロの視点で観察する(1) 第32回 チーム力、組織力とは何かについて考える(7)-ミッション共有は意外と難しい-
第32回 チーム力、組織力とは何かについて考える(7)-ミッション共有は意外と難しい- 第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2)
第31回 階層型要求事項抽出方法-REM(2) 第31回 チーム力、組織力とは何かについて考える(6)-ミッションの共有への取り組み-
第31回 チーム力、組織力とは何かについて考える(6)-ミッションの共有への取り組み- 第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1)
第30回 階層型要求事項抽出方法-REM(1) 第30回 チーム力、組織力とは何かについて考える(5)-プロアクティブな実践の基盤-
第30回 チーム力、組織力とは何かについて考える(5)-プロアクティブな実践の基盤- 第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2)
第29回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する (2) 第29回 チーム力、組織力とは何かについて考える(4)-プロアクティブ行動という視点-
第29回 チーム力、組織力とは何かについて考える(4)-プロアクティブ行動という視点- 第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1)
第28回 消費者のインサイトに仮想コンセプトを使って観察する(1) 第28回 チーム力、組織力とは何かについて考える(3)-レジリエンスを高める組織マネジメント②-
第28回 チーム力、組織力とは何かについて考える(3)-レジリエンスを高める組織マネジメント②- 第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する
第27回 サービスに仮想コンセプトを使って観察する 第27回 チーム力、組織力とは何かについて考える(2)-レジリエンスを高める組織マネジメント①-
第27回 チーム力、組織力とは何かについて考える(2)-レジリエンスを高める組織マネジメント①- 第26回 チーム力、組織力とは何かについて考える(1)-レジリエンス-
第26回 チーム力、組織力とは何かについて考える(1)-レジリエンス- 第26回 サービスを構造的に観察する(3)
第26回 サービスを構造的に観察する(3) 第25回 サービスを構造的に観察する(2)
第25回 サービスを構造的に観察する(2) 第25回 相互理解のコミュニケーションを考える-互いに信頼し、困難と向き合うために-
第25回 相互理解のコミュニケーションを考える-互いに信頼し、困難と向き合うために-  第24回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(6)-リスク認知とリスク評価の心理学-
第24回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(6)-リスク認知とリスク評価の心理学- 第24回 サービスを構造的に観察する(1)
第24回 サービスを構造的に観察する(1) 第23回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(5)-リスク・コミュニケーションとクライシス・コミュニケーション-
第23回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(5)-リスク・コミュニケーションとクライシス・コミュニケーション- 第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う
第23回 事前期待と事後評価の差分からサービスの評価を行う 第22回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(4)-アサーティブなコミュニケーションについて-
第22回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(4)-アサーティブなコミュニケーションについて- 第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3)
第22回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(3) 第21回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(3)-説得と心理的リアクタンス(反発)の関係に注目して-
第21回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(3)-説得と心理的リアクタンス(反発)の関係に注目して- 第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2)
第21回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(2) 第20回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(2)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に②-
第20回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(2)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に②- 第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1)
第20回 サービスの設計項目から、サービスシステムの問題点を探る(1) 第19回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(1)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に①-
第19回 効果的な説得的コミュニケーションのあり方をめぐって(1)-依頼や要請の効果的方略の研究を参考に①- 第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7)
第19回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(7) 第18回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(6)-社会的影響力と説得的コミュニケーションの視点から-
第18回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(6)-社会的影響力と説得的コミュニケーションの視点から- 第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6)
第18回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(6) 第17回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(5)-コミュニケーション行動研究の知見から③-
第17回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(5)-コミュニケーション行動研究の知見から③- 第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5)
第17回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(5) 第16回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(4)-コミュニケーション行動研究の知見から②-
第16回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(4)-コミュニケーション行動研究の知見から②- 第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4)
第16回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(4) 第15回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(3)-コミュニケーション行動研究の知見から①-
第15回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(3)-コミュニケーション行動研究の知見から①- 第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3)
第15回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(3) 第14回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(2)-援助行動研究の知見から-
第14回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(2)-援助行動研究の知見から- 第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2)
第14回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(2) 第13回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(1)-S. Milgramのロストレター・テクニック-
第13回 何気ない行動から人間の社会性と心理を解明する取り組み(1)-S. Milgramのロストレター・テクニック- 第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)
第13回 70デザイン項目を活用してシステム、製品の使用実態や問題点を探る(1)  第12回 チームワークの良さは観察すればわかるか?- “百聞は一見にしかず”行動観察の意義の核心をめぐって-
第12回 チームワークの良さは観察すればわかるか?- “百聞は一見にしかず”行動観察の意義の核心をめぐって- 第12回 70デザイン項目とアブダクション
第12回 70デザイン項目とアブダクション 第11回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(2)-チーム・マネジメントの心理学②-
第11回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(2)-チーム・マネジメントの心理学②- 第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2)
第11回 世の中の動向、ファッションを観察する(2) 第10回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(1)-チーム・マネジメントの心理学①-
第10回 どうすれば優れたチームワークを育むことができるか(1)-チーム・マネジメントの心理学①- 第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1)
第10回 世の中の動向、ファッションを観察する(1) 第9回 俯瞰してHMIを観察する
第9回 俯瞰してHMIを観察する 第9回 チームワークと行動観察-"こころがひとつになる"と何が違ってくるのか-
第9回 チームワークと行動観察-"こころがひとつになる"と何が違ってくるのか- 第8回 組織の規範変革と社会心理学-集団に「こころ」を想定することの是非をめぐって-
第8回 組織の規範変革と社会心理学-集団に「こころ」を想定することの是非をめぐって- 第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する
第8回 ユーザとそのインタラクションについて観察する 第7回 組織の規範とメンバーの職務動機づけ(やる気)の関係-リターン・ポテンシャル・モデルを参考にして-
第7回 組織の規範とメンバーの職務動機づけ(やる気)の関係-リターン・ポテンシャル・モデルを参考にして- 第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2)
第7回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(2) 第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1)
第6回 製品(システム)とそのインタフェース部について観察する(1) 第6回 部下のやる気を引き出す働きかけとは?-コーチングの視点に基づいて-
第6回 部下のやる気を引き出す働きかけとは?-コーチングの視点に基づいて- 第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察-
第5回 直接観察法について-自然の状況下での観察- 第5回 人間のやる気はどのように行動に表れるだろうか-動機づけに関する社会心理学研究の視点から-
第5回 人間のやる気はどのように行動に表れるだろうか-動機づけに関する社会心理学研究の視点から- 第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る
第4回 観察を支援する70デザイン項目について知る 第4回 部下のやる気と行動を引き出す管理職の働きかけとは-リーダーシップに関する社会心理学研究の視点から-
第4回 部下のやる気と行動を引き出す管理職の働きかけとは-リーダーシップに関する社会心理学研究の視点から- 第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する-
第3回 人間について知る-多様なユーザの特徴を理解する- 第3回 多数者意見の影響力は個人の行動をどのくらい束縛するか-同調行動に関する社会心理学の研究-
第3回 多数者意見の影響力は個人の行動をどのくらい束縛するか-同調行動に関する社会心理学の研究- 第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面-
第2回 人間-機械系について知る-HMIの5側面- 第2回 流行や普及の社会現象の発生メカニズムと行動観察-T.C. Schellingの「限界質量」の理論を題材にして-
第2回 流行や普及の社会現象の発生メカニズムと行動観察-T.C. Schellingの「限界質量」の理論を題材にして- 第1回 観察の方法
第1回 観察の方法 第1回 行動を観察すれば人間心理のどこまでを明らかにすることができるのだろうか-S. Milgramの「空を見上げる人々」実験を題材にして-
第1回 行動を観察すれば人間心理のどこまでを明らかにすることができるのだろうか-S. Milgramの「空を見上げる人々」実験を題材にして-

